 読者様
読者様携帯がずっと大雨警報をお知らせしてる…避難指示?
台風や大雨、地震のたびに届く「避難指示」。
けれど、実際には周りの人も動いていない、家族からも「大げさすぎる」と言われてしまう。
そんなとき、ひとりで判断して避難するのはとても勇気がいります。
あなたも「家で様子を見るしかなかった」と感じたことがあるかもしれません。
この記事では、「避難指示が出たけど避難しなかった」という選択を否定するのではなく、「家族と命を守るにはどう備えるか」という視点から、避難所ではなく自宅での過ごし方や心構えについてお伝えします。
ぜひ、最後までご覧ください。
どうして避難指示が出ても動けないの? 心の中の「迷い」を知る
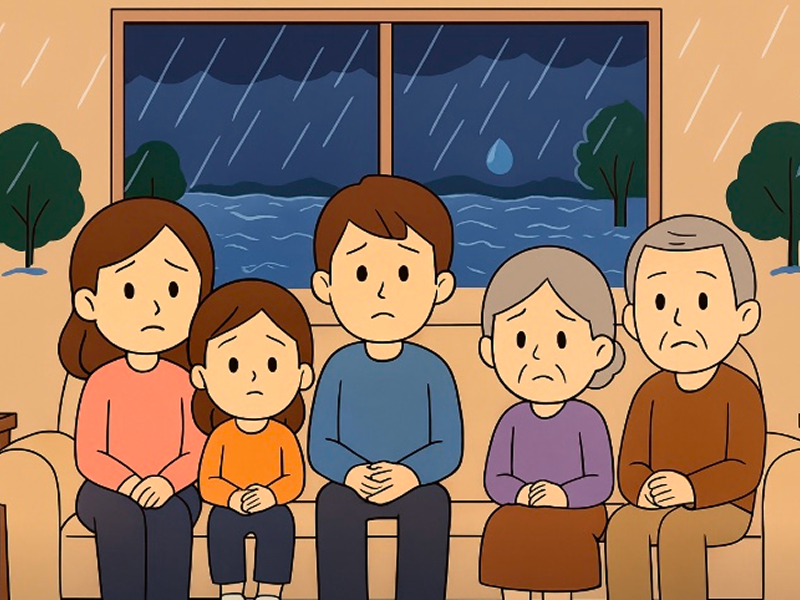
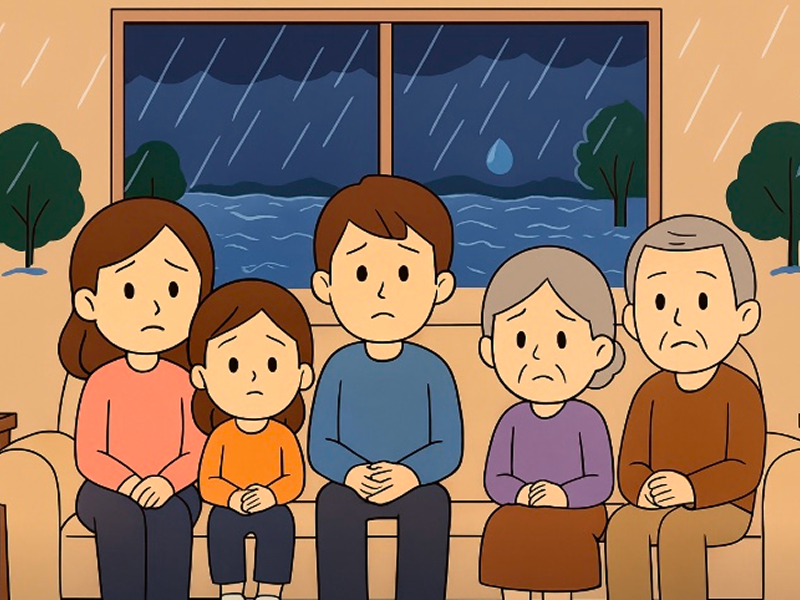



避難指示が出ても、様々な理由があってすぐに動けないのはよくある話です。
「子どもを起こすのも大変だし、外は雨が強い」「両親も動きたがらないし、近所の人もまだ家にいる」──そんな状況の中で、誰だって迷ってしまうものです。
不安を感じつつも、「今までも大丈夫だったし、今回も平気かもしれない」と自分に言い聞かせてしまうのは、ごく自然な心理です。
けれど、過去の経験を基準にした「安心感」が、時に避難を遅らせてしまうことがあります。
次に、その「前回も無事だった」という思い込みがどんな危険を生むのか、もう少し詳しく見ていきましょう。
避難を迷う心理とは
避難指示が出ても行動に移せない理由の一つに、「正常性バイアス」があります。
正常性バイアスとは?
- 危険な状況でも「自分は大丈夫だ」「今回も平気だろう」と思い込んでしまう心理のこと
- 自分に都合の悪い情報・危険を過小評価してしまい、行動が遅れるという特徴がある
また、ウェザーニュースの調査では、避難しないことについて「周囲が避難していないから」「何を持っていけばいいかわからない」「避難所に行くのが不安」といった理由が多く挙がっています。
不安や迷いがあるのは自然なことです。
だからこそ、あらかじめ「どう動くか」を考えておくことが大切なのです。
過去の災害と比較する危険性
前述したように、「前の台風のときも大丈夫だったから、今回も大丈夫だろう」と考えるのは危険です。
災害の規模やタイミングは毎回異なる
- 地盤が緩む
- 雨の降り方が変化する
- 震度が大きい
- 同じ場所でも被害の出方はまったく違う
つまり、前回大丈夫だったとしても、今回はそうじゃない可能性があります。
「前回無事だった」は根拠にはなりません。
実際の被害事例から学ぶ
2021年の熱海土石流では、避難情報が出ていたにもかかわらず多くの方が避難せず、甚大な被害が出ました。
このように「避難のタイミングを逃したこと」が直接的な被害につながったケースは少なくありません。
迷ったときには「念のため避難」。
それが結果的に命を守る判断になります。
「前回も大丈夫だった」から抜け出すためのポイント
- 災害は毎回ちがう:状況が変われば災害による被害も変わる。今回も同じとは限らない
- 「今」を基準に判断する:過去よりも「現状、今後起こりうる危険性」を優先する
- 備えることで安心をつくる:行動によって不安が減り、家族を守る力になる
「家にとどまる」判断で起こりうること 避難しないリスクを考える





避難しないという選択には、誰もがそれなりの理由を持っています。
「外は危ないから出たくない」「家のほうが落ち着く」「家族が動かない」──どれも間違いではありません。
けれど、その「とどまる」という判断が、思いがけない危険を招くこともあります。
大雨や地震などの災害は、ほんの数分で状況が一変します。
「もう少し様子を見よう」と思っているうちに、逃げ道がなくなってしまうことも珍しくありません。
次に、実際にどのようなリスクがあるのかを見ていきましょう。
命の危険を招くパターン
大雨による浸水や土砂災害が発生すると、自宅にとどまることがかえって危険になる場合があります。
自宅にいることで危険となる状況とは?
- 最初はただの雨でも、数時間で一気に水かさが増し、玄関先まで水が押し寄せる
- 地面がゆるめば、いつ土砂が崩れてくるかわからない
- 避難が遅れれば、道路が冠水して車が動かなくなったり、土砂が家の裏まで迫る
- 逃げる道が断たれてしまう恐れがある
「もう少し様子を見よう」と思っているうちに、外に出ることすらできなくなるケースも少なくありません。
孤立した結果、救助を待っても手が届かない――そんな危険が現実に起こりうるのです。
救助が来ない状況もある
「もしものときは消防や自衛隊が助けに来てくれる」と思う方も多いでしょう。
救助が来ない状況とは?
- 広範囲で被害が出る大規模災害では、救助の手がすぐに届かない
- 道路が寸断され、通信が途絶え、被害の全容がつかめないまま時間だけが過ぎていく
- 救助要請が殺到し、出動までに数日かかることもある
実際、過去の豪雨災害では「屋根の上で一晩過ごした」「食料や水が尽きた」という事例もありました。
助けを待つしかない状況に陥らないためにも、「自分の命は自分で守る」という意識を持って行動することが大切です。
家族全体への影響
避難しないという判断は、自分だけでなく家族全体を危険にさらすことになります。
家族にはどんな影響があるか?
- 小さな子どもや高齢者は、自分で状況を判断したり、素早く避難したりすることが難しい
- 暗闇や大雨の中での避難は大人でも恐怖を感じる
- もし子どもを抱え、足元が見えない中を歩くのは困難
- 避難が遅れたことで家族が離ればなれになってしまうケースもある
「もう少し早く決断していれば」と悔やんでも、災害の最中にはどうにもならないことが多いのです。
守るべき家族の存在を考えれば、「まだ大丈夫」と思うよりも「今なら間に合う」と考えるほうが、ずっと安全です。
命を守るために、「できること」とは?
- 災害は早めの行動(避難)がカギ
- 安全なうちに避難を始めよう
- 迷ったら「逃げる」を選ぶ
- 情報をこまめに確認する
- 家族と声をかけ合う
- 助けを待つより動く勇気を持つ
- 子ども・高齢者を最優先にする
家族をどう動かす?避難をためらう人への伝え方と備え方
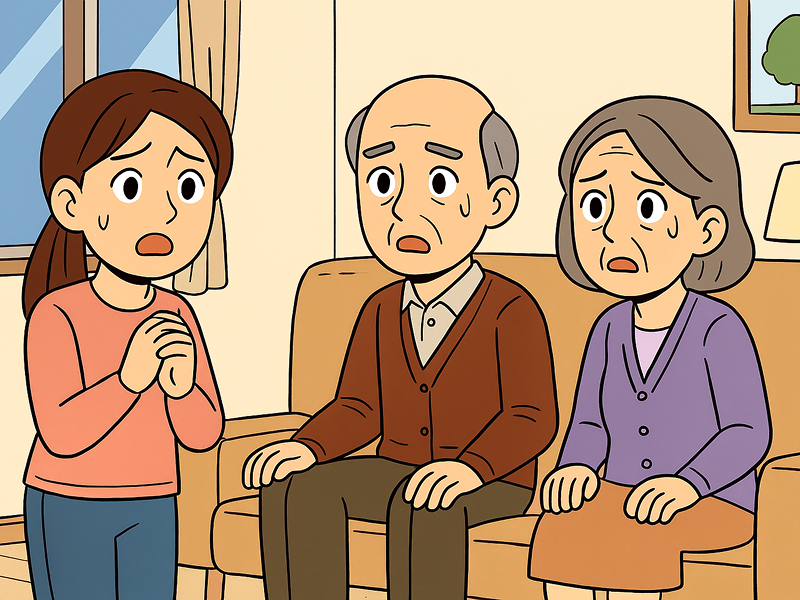
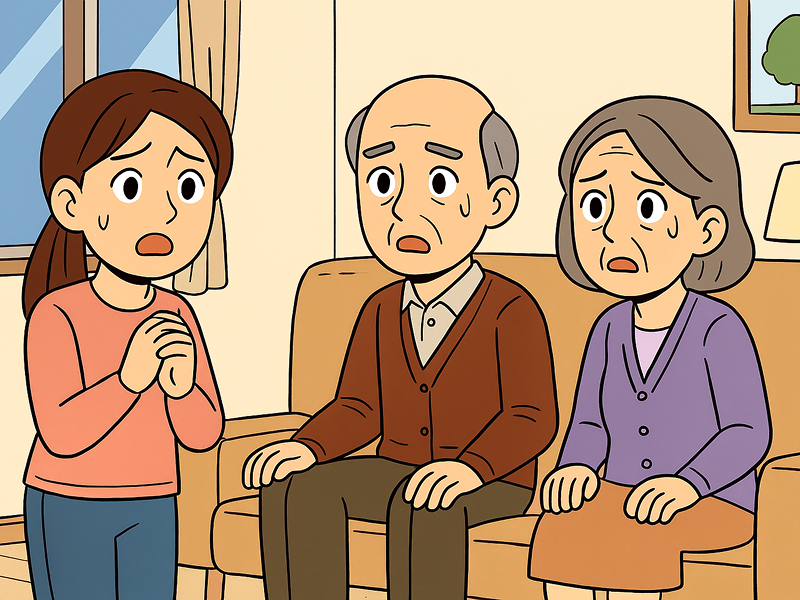



避難は私一人じゃ意味ないし、説得する必要があるかも。



とくに高齢の家族や子どもがいる場合、「避難したほうがいい」とわかっていても、実際に行動へ移すのは簡単ではないですよね。
家族が「大丈夫」「大げさだ」と言って動かないとき、どう声をかければいいのか悩む人も多いはずです。
でも、命を守るためには「言いにくくても伝える勇気」が必要です。次に、家族の心を動かすための工夫を見ていきましょう。
説得のためのポイント
高齢の家族が「避難は大げさだ」「もう歳だから動けない」と言うことはよくあります。
そんなときに「危ないから行こう」と言っても、なかなか響かないものです。
説得のためのポイント
- 「自分が困る」ではなく「周りに迷惑をかけるかもしれない」という視点を伝える
- 「もし何かあって助けを呼べなかったら、みんなも心配するよ」と伝えてハードルを下げる
- 過去の災害事例を一緒に見ながら、「このときも、避難が少し遅れた人が多かったみたい」と共感の形で話す
「避難しよう」ではなく「一緒に行こう」と言葉を変えるだけで、印象はずいぶん変わります。
避難計画を事前に立てておく
避難は「そのとき考える」のでは遅いものです。
あらかじめ「マイ・タイムライン(自分と家族の避難行動計画)」を作っておくことで、「どのタイミングで」「どこへ」「何を持って」行くのかが明確になります。
| 時間・状況 | 行動内容 | 担当者 | 確認ポイント |
| 気象情報が出た時 | テレビやアプリで最新情報を確認 | 父 | 避難所・ルートの再確認 |
| 大雨注意報が発令 | 非常持ち出し袋を玄関に移動 | 母 | 食料・水の残量確認 |
| 避難指示(警戒レベル4)発令 | 家族全員で避難開始 | 全員 | 連絡手段・集合場所の確認 |
| 避難後 | 安否確認・SNS投稿は控える | こども | 情報の信頼性を確認 |
上記のように、家族で役割分担を決めておくのも大切です。
小さなことでも事前に決めておくと混乱が減ります。
非常用持ち出し袋や備蓄品をまとめておけば、「何を持っていけばいいかわからない」という不安もなくなります。
そして「準備してある」という安心感が、いざというときの行動力につながります。
非常用持ち出し袋を準備しておこう
避難指示が出たとき、「何を持っていけばいいかわからない」という声はとても多いものです。
けれど、あらかじめ非常用持ち出し袋(防災バッグ)を用意しておけば、いざというときに慌てず行動できます。
非常用持ち出し袋の中身について
- 飲料水(1人1日1リットル×3日分)
- 食料(缶詰・乾パン・レトルト・氷砂糖・ようかんなど)
- 懐中電灯・乾電池・モバイル充電器
- 常備薬・保険証コピー・現金
- マスク・タオル・衛生用品
- ラジオや笛(助けを呼ぶため)
家族構成によって、中身を調整しましょう。
小さな子どもがいるなら粉ミルクやおむつ、高齢者がいるなら介護用品や薬が欠かせません。
「持ち出し袋を作るのは大変」と思うかもしれませんが、1日1つずつでも構いません。
リュックを玄関の見える場所に置くだけでも、「いつでも避難できる安心感」につながります。
地域の協力を得る方法
家族の力だけで避難を完結させるのは難しい場合があります。
そんなときは、地域の力を頼ることも大切です。
災害時に地域の協力を得るためには、地域付き合いが大切
- 自治会や防災リーダー、近所の人たちと日ごろから顔を合わせ、簡単な情報交換をしておく
- 高齢の家族がいる家庭では、「○○さんの家は高齢の方がいる」と地域に知ってもらう
- 地域の防災訓練に参加し、避難所の場所やルート、避難所でのサポート体制も確認しておく
災害は「地域で助け合う」ことが生死を分けることもあります。
お互いの顔が見える関係を作っておくことこそ、最大の備えです。
高齢の家族や介助が必要な場合は「福祉避難所」を確認しておこう



寝たきりのおじいちゃんがいると避難所に行くのは大変だし、人が多い場所では落ち着けないの。どうしたらいい?
そんなときに頼れるのが、「福祉避難所」です。
福祉避難所とは?
- 一般の避難所とは別に、介護や医療的な支援を必要とする人のために設けられた特別な避難施設
- ベッドや介助スペースがあり、スタッフによる支援が受けられる
- 高齢者や体の不自由な方でも安心して過ごせる環境が整えられている
- 誰でもすぐに利用できるわけではなく、事前に自治体へ登録や相談が必要
- 多くの自治体では「要配慮者名簿」に登録された人を対象に、災害時に受け入れ先を調整
「うちの親は対象になるの?」「どこに福祉避難所があるの?」そう感じたら、平時のうちに自治体の福祉課や地域包括支援センターに確認しておきましょう。
早めに登録や確認をしておけば、いざというときに慌てずに避難行動をとることができます。
家族みんなが安心して過ごせるように、「どこへ避難するか」だけでなく「誰がどんな支援を受けられるか」まで考えておくことが大切です。
家族を動かすために意識したいポイント
- 「避難しよう」より「一緒に行こう」と伝える
- 過去の災害を一緒に振り返る
- 家族で役割分担と避難計画を立てる
- 準備してある安心感が行動を早める
- 家族構成に応じた「非常用持ち出し袋」を用意する
- 地域とつながることで助け合いが生まれる
- 福祉避難所も選択肢に入れる
避難に迷ったとき、どうすればいい? 自宅避難の判断と備えのヒント
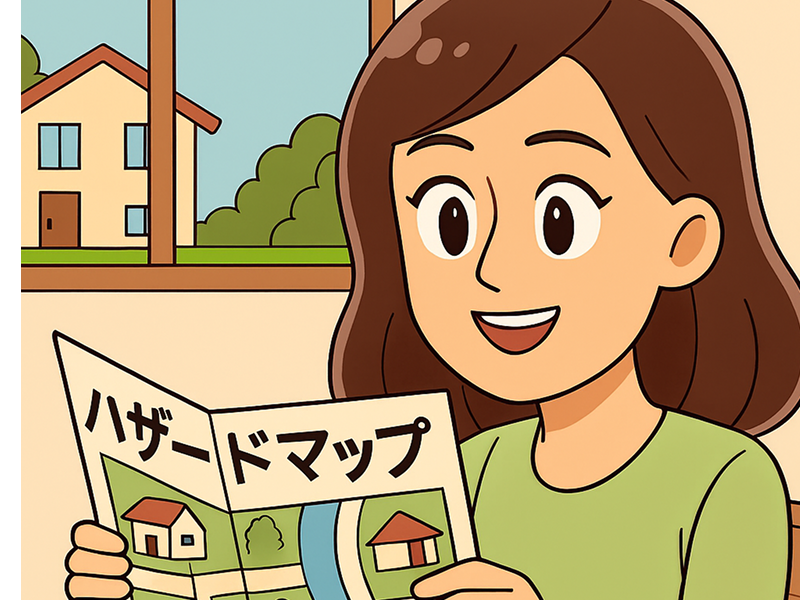
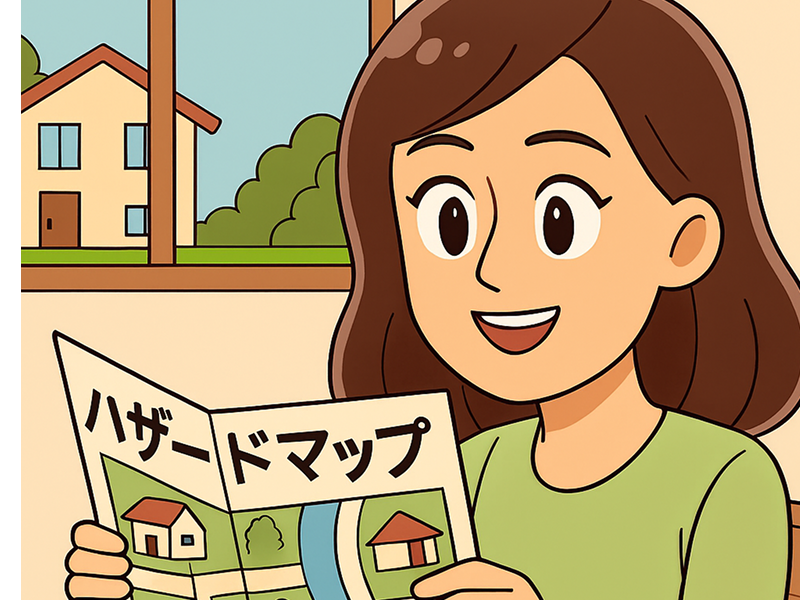



避難指示が出ても、この程度じゃ大丈夫でしょって自分で決めているところがあるかも。
避難指示が出たとき、「本当に避難すべき?」「この雨ならまだ大丈夫かも」と迷ってしまう方は少なくありません。
家族の意見が分かれたり、周囲の様子を見てしまったり──その「迷い」こそが、避難を遅らせる一番の原因になります。
でも、災害のときに大切なのは、「正しい情報を知り、あらかじめ判断の基準を持っておくこと」。
次に紹介する方法を知っておけば、いざというときに落ち着いて行動できます。
ハザードマップを活用する
まず、自宅がどんな災害リスクを抱えているのかを把握しましょう。
自治体のハザードマップやハザードマップポータルサイトでは、「洪水」「土砂災害」「高潮」「津波」など、想定される危険エリアが確認できます。
ハザードマップをどう活用するか
- 自宅や職場、子どもの通学路などを地図上でチェックし、危険区域に該当していないかを確認する
- 「どの方向に逃げれば安全か」を事前に確認し、避難時の迷いを減らす
- 家族全員でマップを確認し、「どこが安全か」「どの避難ルートを使うか」を話し合っておく
家族みんなが把握できるように、印刷して冷蔵庫や玄関に貼っておくのもおすすめです。
避難情報の段階と違い
災害時の避難情報には「警戒レベル」があります。
| 警戒レベル | 行動の目安 | 対象者・状況 |
|---|---|---|
| レベル1 | 今後の気象情報に注意 | 早めの情報収集を始める段階 |
| レベル2 | 避難行動の確認を始める | ハザードマップや避難所の場所を確認 |
| レベル3 | 高齢者や障がいのある人が避難を開始 | 「高齢者等避難」情報。家族は準備を整える |
| レベル4 | 全員が避難を完了する段階(※避難指示) | すぐに安全な場所へ避難! |
| レベル5 | すでに命の危険がある状態 | すぐ避難できない場合は、建物の上階などで命を守る行動を |
特にレベル4「避難指示」が出た時点で、すぐに安全な場所へ移動することが基本です。
以前まであった「避難勧告」は2021年に廃止され、現在は「避難指示」に一本化されています。
「まだ避難勧告が出ていないから大丈夫」という判断はもう通用しません。
テレビ・ラジオ・防災アプリなどで情報をこまめにチェックし、「避難情報が出たら即行動」を習慣づけましょう。
迷ったときは、「やりすぎた」と思うくらいがちょうどいいのです。
自主避難という選択肢も
「避難指示が出ていないから、まだ大丈夫」と思ってしまうことがありますが、本当に安全なのは、「指示が出る前に動くこと」です。
これを「自主避難」と言います。
自主避難とは、避難指示を待たずに自ら判断して避難すること。
自主避難のポイント
- 「川の水が増えてきた」などの「違和感」を感じた時点で動くこと
- 自治体によっては自主避難できる施設(避難所)を平時から公開している場合もある
- あらかじめ確認しておけば、「どこに行けばいいか分からない」という不安を軽減できる
「避難指示が出たから行く」ではなく、「危ないと感じたら動く」。
それがこれからの時代の新しい避難スタイルです。
自宅避難という選択──メリットとリスクを知る
避難所に行くことだけが「避難」ではありません。
家の立地が安全で、災害の危険が少ない場合は、自宅避難(在宅避難)という選択肢もあります。
自宅避難は「安全な立地と備え」が前提です。
ハザードマップで危険区域に入っていないか確認し、最低でも3日分の食料と水、簡易トイレを準備しておきましょう。
| 自宅避難のメリット(良い点) | 考えられるリスク(注意点) |
|---|---|
| 家族が安心して過ごせる | 停電・断水・通信途絶で孤立する可能性 |
| 高齢者や子どもへの負担が少ない | 食料・水・トイレなどの備蓄が必要 |
| 感染症や人混みのストレスを避けられる | 救助や支援が届くまで時間がかかる場合がある |
| プライバシーが確保しやすい | 情報が入りにくく、状況判断が遅れることも |
| ペットと一緒に避難しやすい | 建物の安全性(地盤・浸水・倒壊リスク)を確認する必要あり |
「避難しない」ではなく「家で安全に過ごす準備をする」。
それが、自宅避難を成功させる一番のポイントです。
判断に迷わないためのポイント
- ハザードマップでリスクを把握する
- 家族で安全な避難ルートを決めておく
- 警戒レベル4=全員避難と覚えておく
- 情報を待たずに早めに動く・自主避難を習慣づける
- 「迷ったら避難」を合言葉にする
「避難しない」を防ぐために、今日からできる小さな備え
本記事では、避難できない心理、避難しないことのリスク、家族を動かす工夫、そして判断に迷わないための準備についてお伝えしてきました。
「避難指示が出ても家にいた」──そんな経験は、誰にでもあり得ます。
それは無関心ではなく、不安や迷い、そして家族を思う気持ちがあったからこそです。
けれど、災害は待ってくれません。
ほんの少し行動を早めるだけで、守れる命があります。
そのために必要なのは、特別な知識や体力ではなく、「今できる備えを重ねること」です。
今日からできる、小さな防災アクション
- ハザードマップで自宅周辺の危険を確認する:どんな災害が想定されているのか確認
- マイ・タイムラインを作る:「いつ」「誰が」「何をするか」を整理しておく
- 非常用持ち出し袋を整える:玄関に置いて、いつでも避難できる安心感
- 自宅避難という選択を考える:安全な立地なら、家で過ごすための水・食料・トイレの備えをしておく
- 福祉避難所や親戚宅など、避難先の選択肢を確認する:特に高齢者や介助が必要な家族がいる場合は、事前に相談・登録をしておく
- 家族と話し合う時間を持つ:「どこへ」「いつ」「どうやって」避難するかを共有しておく
こうした準備が、いざというときの冷静な判断につながります。
「何もなかったらよかったね」と笑える準備をしておくことは、決して大げさではありません。
それは、あなた自身と大切な人の未来を守るための、やさしい勇気です。
あなたの小さな行動が、大切な家族の命を救えるということを忘れないでくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
女性の一人暮らしでもできる『万が一』への防災準備についてご存知ですか?早めに防災対策をして、いざという時のために準備しておきましょう。
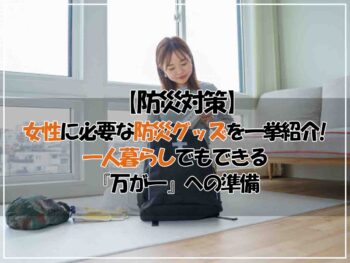
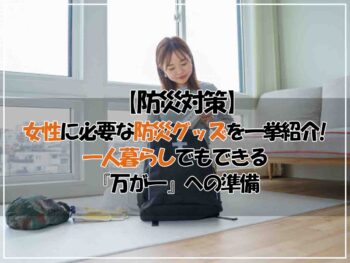

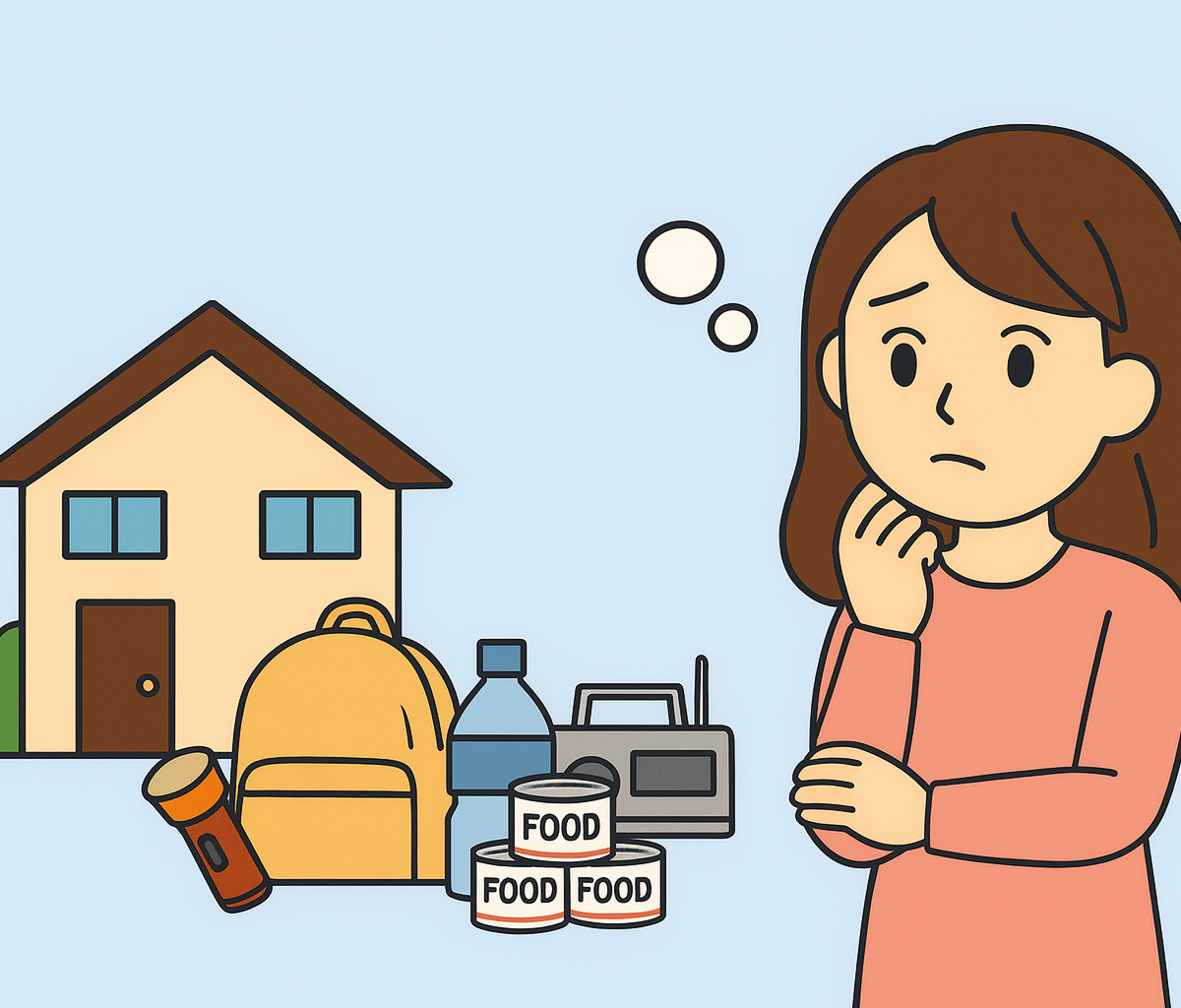

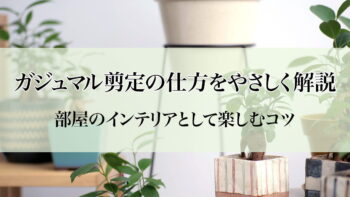




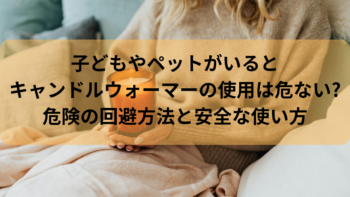

コメント