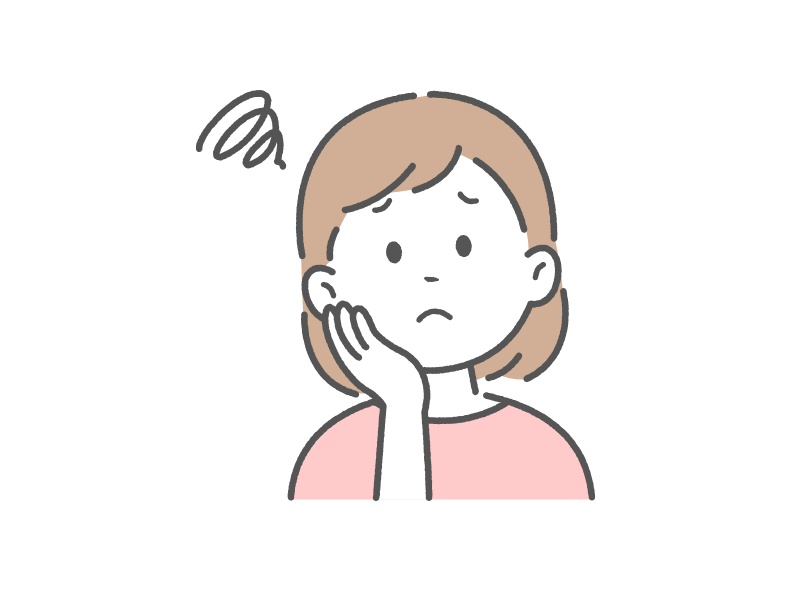 保護者さま
保護者さま「センター試験廃止って、大丈夫なのかな」
多くの保護者や受験生が抱える、理想と現実の狭間にある切実な不安だと思います。
2021年、30年以上続いた「大学入試センター試験」が幕を閉じ、「大学入学共通テスト」へと移行しました。
かつて自分たちが経験した「努力がそのまま点数に表れる」仕組みが終わり、思考力や判断力を重視する新しい共通テストに変わる。
確かに、社会の変化に合わせた改革は必要かもしれません。
一方で、これまで全国一律の公平な基準で評価されていた仕組みが変わり、不安が広がっています。
教育に熱心な家庭ほど、子どもの努力が正当に評価されてほしいと願うものです。
改革の理想は理解できるものの、現場の混乱や地域格差、採点体制の不透明さなど課題も多いのが現実です。
- センター試験廃止の背景や目的、共通テスト導入の狙い
- 保護者から見た課題と不安を整理
- 保護者としてどのように向き合えばよいのか
保護者は、子どもが前向きに学習に取り組めるよう支える役割が求められます。
制度を感情だけでなく、冷静に理解するための第一歩として、ぜひ参考になさってください。
センター試験廃止の背景と目的
-1074x716.avif)
-1074x716.avif)
長年続いた大学入試センター試験は、「知識の暗記中心」と批判され、社会で求められる思考力や判断力を十分に測れないとの指摘がありました。
こうした課題を受け、政府は「大学入学共通テスト」を導入し、より多面的な学力評価を目指したのです。
なぜ共通テストが導入されたのか
共通テスト導入の背景には、急速に変化する社会に対応できる人材を育てたいという政府と文部科学省の狙いがあります。
センター試験から共通テストへ変化した点は以下のとおりです。
- 「知識を使って考える力」「自ら答えを導き出す力」を問う方向へ転換
- 単に正解を覚えるのではなく、未知の課題に対して柔軟に対応する力が不可欠
- 国語や数学では記述式や思考力を問う問題を導入
- 英語では「読む・聞く・話す・書く」の4技能を評価
こうした改革は「より深い学び」を促す狙いがある一方で、受験生や保護者にとっては制度の変化が大きく、準備や対策に戸惑いを感じる声も多く聞かれます。
親世代にとってセンター試験は『分かりやすい基準』
親世代にとって、センター試験は「全国一律で同じ問題」「得点で評価が決まる」という、非常に分かりやすい基準でした。
自分の努力がそのまま数字として表れる安心感があり、地方や都市部といった地域差も少なく、公平だと感じられた人が多いでしょう。
一方、現在の共通テストは思考力・判断力を重視する出題形式に変わり、「どんな問題が出るのか」「どう対策すればいいのか」が見えづらいと感じる保護者も少なくありません。
特に、親が経験してきたセンター試験と比較して「基準があいまい」「運に左右されそう」と不安を抱く声も多く聞かれます。
教育改革の趣旨は理解していても、子どもの受験に直結する制度変更はどうしても心配になります。
「努力すれば報われる」という感覚を持つ親世代ほど、評価基準の変化に戸惑いを感じるのは自然なことです。
共通テスト移行の流れ
共通テストからセンター試験へ移行した流れは下記のようになります。
| 項目 | 1979年〜1989年 共通第1次学力試験の時代 | 1990年〜2020年 センター試験の時代 | 2021年〜2024年 共通テスト第1期 | 2025年〜 新課程の共通テスト |
| 名称 | 共通第1次学力試験 | 大学入試センター試験 | 大学入学共通テスト | 大学入学共通テスト (新課程入試) |
| 開始年 | 1979年 | 1990年 | 2021年 | 2025年 |
| 主な対象 | 国公立大学志望者のみ | 国公立大学に加え、私立大学も参加可能に | 国公立・私立大学 | 国公立・私立大学 |
| 主な評価 | 基礎的な学力を測る | 知識をしっかり身につけているかを測る目的 | 知識を活用し、考える力・判断する力を測る(思考力重視) | 知識活用に加え、デジタル社会で必要な力を測る |
| 出題傾向 | 各大学の2次試験に進むための足切り的な役割 | マークシート方式、暗記した知識の正確な再現が評価ポイント | 問題文が長文化、グラフや表などの資料を読み解く問題が増加 | 問題傾向は第1期を踏襲しつつ、新教科「情報」が追加 |
| 教科数/科目数 | 5教科7科目 | 5教科7科目を基本に選択制 (柔軟性あり) | 5教科7科目を基本に選択制 | 7教科21科目 (従来の6教科30科目から整理) |
| 満点 | 大学による | 900点が多い | 900点 | 1000点に増加 (「情報」の追加に伴う) |
| 特筆事項 | 全国統一試験のスタート | ・私立大学参加による入試の中心的存在に ・保護者世代が経験した試験 | 社会変化に対応した評価視点の大きな改革 | 新学習指導要領に対応、「情報」が必須科目に |
1979年〜1989年:共通第1次学力試験の時代
大学入試に「全国共通の試験」が登場したのは、1979年のことでした。
- 国語・数学・外国語・理科・社会の5教科7科目で構成
- 基礎的な学力を測ることを目的
- 共通第1次試験で一定の点数を取り、クリアした人だけが各大学の2次試験(個別試験)に進める
この画期的なシステムは、大学入試の公平性を高める大きな一歩となった。
1990年〜2020年:センター試験の時代
1990年、共通第1次試験は「大学入試センター試験」へと生まれ変わりました。
最も大きな変更点は、私立大学も参加できるようになったことです。
5教科7科目を基本としながらも、大学や学部によって必要な科目を選択できる柔軟性もありました。
2021年〜2024年:共通テスト第1期
30年間続いたセンター試験が終わりを告げ、「大学入学共通テスト」がスタートしました。
- センター試験と比べて問題文が長くなり、グラフや表などの資料を読み解く問題が増加
- 英語ではリスニングの配点が大幅に上がる
- 数学では試験時間が延長
知識を前提としつつ、どう活用できるかを問い、より実践的な力を試されている。
2025年〜:新課程での共通テスト
そして今年2025年1月から、共通テストはさらに新しい段階に入りました。
「新課程入試」と呼ばれるもので、高校の学習指導要領が変わったことに伴う変更です。
- 最も大きな変化は、「情報」という新しい教科が加わった
- プログラミングやデータ活用など、デジタル社会で必要な力を測る科目が必須
- 従来の「6教科30科目」から「7教科21科目」へと整理
- 満点も900点から1000点に変更
一見複雑に見えますが、本質は変わっていません。
時代に合わせて、お子さんたちが将来社会で活躍するために必要な力を適切に評価しようとしているのです。
科目が増えたり変わったりすることに不安を感じるのは自然なことですが、学校での学習内容に沿って準備すれば大丈夫!
お子さんの努力は、しっかりと評価される仕組みになっていますよ。
センター試験廃止に反対する主な3つの理由
-1074x716.avif)
-1074x716.avif)
共通テストへの移行から数年が経ちますが、「センター試験のほうがよかった」という声は今も少なくありません。
全国一律の公平な評価、明確な採点基準、そして努力が結果に結びつく安心感があるからです。
ここでは、多くの保護者が感じるセンター試験廃止への反対理由を、主な3つの視点から整理してみます。
公平性の低下と地域格差
センター試験は、全国どこでも同じ日に同じ問題を解くという「公平性」が最大の特徴でした。
採点も機械的に行われ、誰がどこで受けても同じ基準で評価されます。
この安心感こそ、多くの受験生と保護者に支持されてきた理由のひとつです。
共通テストは、思考力を問う複雑な設問や、英語4技能評価などの導入しました。
問題点は以下のとおりです。
- 学校や地域によって準備環境に差が出やすい
- 都市部:民間英語試験を受けやすい
- 地方:会場が限られ、受験機会が少ない
記述式問題の導入が検討された際には、採点基準のばらつきや人手不足の懸念も浮上した。
努力しても評価が採点者の主観に左右されるのでは……という不安は、親世代にとって大きな不信感につながっています。
制度改革の理想と現場の実情との間に、いまだ大きな溝があるのが現状です。
努力しても報われない気がする……
センター試験のように明確な得点で合否が見える仕組みではなくなり、基準が複雑化したことで、努力の成果の評価かが分かりづらくなったのです。
特に、思考力・判断力を重視する問題では「解き方」に正解が一つとは限らず、模試や学校ごとの指導方針によっても評価が変わる場合があります。
また、改革の過程で制度が何度も変更され、保護者や生徒が正確な情報をつかみにくいことも混乱を招いています。
「情報を調べても内容がコロコロ変わる」「学校の先生も戸惑っている」という現場の声も多く、制度への信頼が揺らいでいるのが実情です。
努力が結果に反映される仕組みであってほしい……との願いが、保護者の本音になっています。
共通テストの課題と今後の展望
-1074x806.jpg)
-1074x806.jpg)
共通テストは「知識から思考力へ」という大きな転換を掲げて導入されましたが、理想と現実の間には課題が残ります。
記述式問題や英語4技能評価など、評価の幅を広げる試みはあったものの、採点の公平性や運用の複雑さが壁となり、十分に機能していません。
今後は、受験生が安心して挑める透明で一貫した評価制度の確立が求められています。
また、学校教育と大学入試の連携強化も、次の大きな課題といえるでしょう。
問題形式や難易度の変化
共通テストでは、従来のセンター試験と比べて「資料の読み取り」や「複数の情報を組み合わせて考える」問題が増えました。
思考力を問う良い試みではあるものの、以下の課題も生まれています。
- 問題文が長く、読解力や処理スピードが得点を大きく左右する
- 設問の意図がつかみにくく、「何を答えればよいのか分からない」という受験生の声も多い
- 記述式や英語4技能評価などの導入は公平性や採点の透明性の問題から見送りや縮小が相次いだ
採点基準の不明確さや、採点者によるばらつきの懸念が解消されないままでは、「思考力を評価する」という理想も形骸化(けいがいか)しかねません。
今後は、難易度の安定化や出題傾向の明確化、そして採点過程の透明化が重要です。
受験生が安心して挑める試験でなければ、制度への信頼は築けません。
改革の方向性を保ちながらも、現場の負担や受験生の実情に寄り添った形が求められています。
記述式導入の混乱
共通テスト改革の中で、最も大きな混乱を招いたのが「記述式問題の導入」でした。
従来のマークシート方式に比べ、表現力や思考力を測れるという利点が期待されましたが、現場では採点の公平性や実施体制に深刻な課題が浮き彫りになりました。
まず、全国で50万人を超える受験生の答案を短期間で採点するには膨大な人員と時間が必要です。
- 採点者の質や採点基準の統一をどう担保するかが問題
- 採点を民間業者に委託する案も出たが、コストや責任の所在があいまいなまま見送りになった
結果的に記述式は導入が延期・縮小され、現場には「準備に振り回された」という疲弊感だけが残った形です。
制度を実施する側・受ける側の双方が安心できる運用体制を整えることが、今後の課題と言えるでしょう。
親ができる最大のサポートは「理解と共感」
入試制度の変化に不安を感じるのは、子どもだけでなく保護者も同じです。
しかし、親ができる最大のサポートは「制度を批判すること」ではなく、「変化を理解し、子どもの気持ちに共感すること」が何よりの支えになります。
- どう前向きに対応していくかを一緒に考える姿勢
- 事実ベースで制度を理解し、子どもが冷静に準備できるよう導くことが重要
- 結果だけでなく「努力の過程」を認めてあげること
共通テストは、センター試験に比べて複雑で不透明な部分がありますが、「思考力や表現力を育てる」方向性自体は、大切な力を伸ばす機会にもなり得ます。
変化の時代を生きる子どもたちにとって、最も心強いのは、家庭での理解と共感なのです。
まとめ|「努力が報われる入試」を取り戻すために
30年続いたセンター試験は「知識の暗記中心」と批判され、社会で必要な思考力・判断力を測るため、2021年に大学入学共通テストへ移行しました。
目的は、変化の激しい社会に対応できる人材育成です。
- 「情報」という新しい教科が加わった
- プログラミングやデータ活用など、デジタル社会で必要な力を測る科目が必須
- 従来の「6教科30科目」から「7教科21科目」へと整理
- 満点も900点から1000点に変更
知識の活用や資料の読み解きを重視し、国語・数学での記述式導入や英語の4技能評価(後に記述式や英語4技能評価の一部は公平性や運用の問題で見送り・縮小)へと変更
親世代が経験したセンター試験は「努力がそのまま点数になる」「全国一律の公平性」という明確な基準でした。
共通テストは、思考力重視への転換で「採点基準があいまい」「努力が正当に評価されないのでは」という不安や不信感が広がっています。
特に、学校や地域による準備環境の格差、記述式導入時の混乱(公平性の懸念から見送り・縮小)は、公平性の低下として大きな懸念点です。
共通テストは理想と現実のギャップが課題です。
問題文の長文化や複雑化は処理スピードを要求し、難易度の安定化や採点過程の透明化が喫緊の課題になっています。
教育改革の真の目的は、子どもたちがこれからの社会を生き抜く力を育てることです。
今後は、受験生が安心して挑める一貫性のある評価制度の確立が求められます。
制度の変化は不安ですが、親ができる最大のサポートは「理解と共感」です。
制度を冷静に理解し、感情的な批判ではなく、子どもが前向きに学習に取り組めるよう導く姿勢が大切です。
結果だけでなく「努力の過程」を認め、家庭が一番の心の支えになることが求められます。

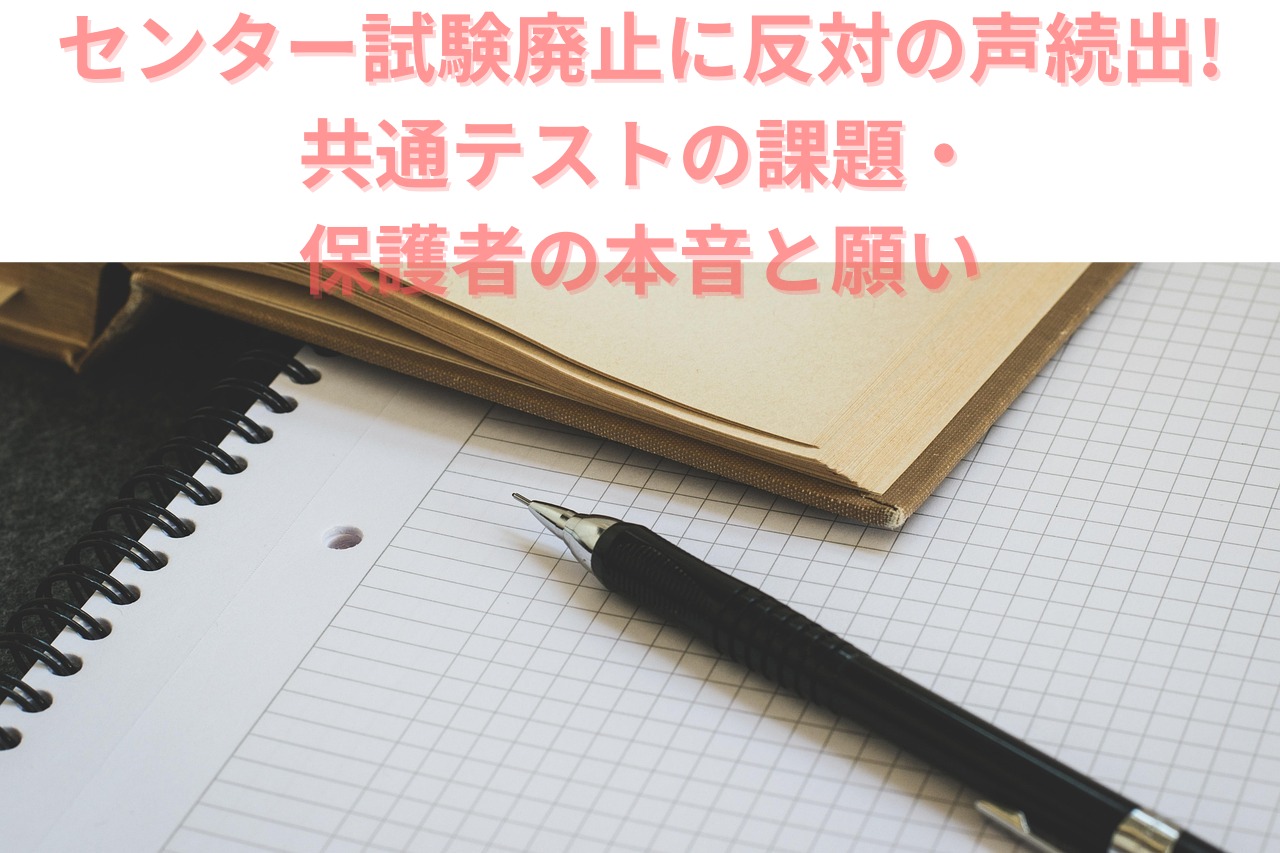
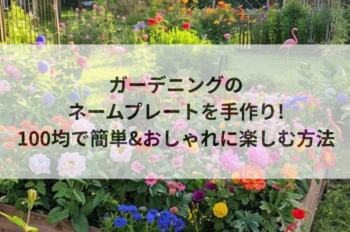
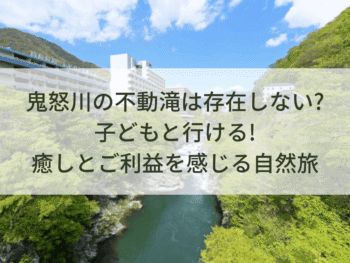
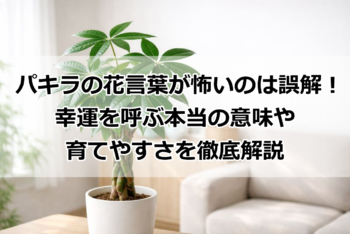
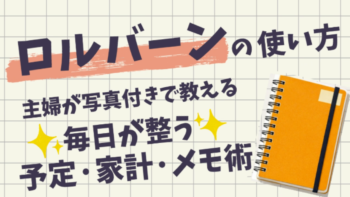
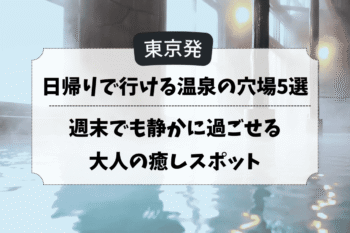



コメント