目に入ると春の訪れ感じる皮付きたけのこ。
風味豊かでみずみずしい食感が魅力の生のたけのこは、春には欠かせない食材ですよね。
しかし、長い時間をかけて料理していざ食べてみると、えぐみが……なんてことありませんか。
 読者さまA
読者さまA えぐみが残ったたけのこを食べても大丈夫?体に悪い?



ちゃんと下処理したはずなのに……
なぜえぐみが残ってしまうの?
たけのこのえぐみの正体はシュウ酸とホモゲンチジン酸という成分です。
ホモゲンチジン酸はアミノ酸の一種が変化したもので体に害はありませんが、シュウ酸は尿路結石の原因になるので、食べ過ぎには注意が必要です。
この記事では調理師歴10年の筆者が、たけのこの正しい下処理法と、えぐみが残った場合のおすすめの料理法を解説します。
正しく下処理すれば、えぐみもなく安心して美味しいたけのこ料理を味わえますよ。
ぜひ最後まで読んでみてください。
たけのこのえぐみの正体


皮付きのたけのこを料理して食べると、苦かったり喉がイガイガしたりしたことがあると思います。
苦みやイガイガの原因となる、えぐみについて知らないと、食べても問題がないのか悩んでしまいますよね。
たけのこのえぐみの成分は以下の2つです。
- ホモゲンチジン酸
- シュウ酸
それぞれの成分について詳しく解説します。
ホモゲンチジン酸
ホモゲンチジン酸はチロシンというアミノ酸の一種が酸化したものです。
チロシンは神経伝達物質ドーパミンの原料となり、集中力・記憶力を向上させたり、うつ病を改善したりする効果があります。
ホモゲンチジン酸は元がアミノ酸の一種なので、食べても害はありません。
茹でたたけのこについている白い粉はチロシンが固まったものです。ホモゲンチジン酸に変化する前なので、えぐみもなく、毒性もありません。参考:加藤薬局 管理栄養士からの一口メモ
シュウ酸
シュウ酸はほうれん草やコーヒーにも含まれる成分で、尿路結石の原因となるため、食べ過ぎには注意が必要です。
シュウ酸は水溶性なので、たっぷりのお湯で茹でることで減らせます。
シュウ酸はしらすやわかめ、かつお節など、カルシウムを多く含む食材と一緒に摂取すると、体に吸収されにくくなります。 参考:自衛隊札幌病院 地域医療室連携便り
アレルギーにも注意
たけのこは食物アレルギーを引き起こす可能性のある食材です。
たけのこを食べて蕁麻疹やかゆみが出た場合は、すぐに病院へ行きましょう。
たけのこにはアレルギーに似た症状を引き起こす、ヒスタミンやアセチルコリンという成分が含まれています。
ヒスタミンによって起こるかゆみなどの反応は、仮性アレルギーと呼ばれます。
アレルギーの無い人でも、一度に大量に食べたり体調が悪かったりすると、仮性アレルギーを起こすことがあります。
たけのこのえぐみを残さない下処理法


たけのこのえぐみを取るには、下処理が大切です。
えぐみ成分のホモゲンチジン酸もシュウ酸も、アルカリ性の水に溶けやすい性質です。
そのため、米ぬかや重曹と一緒に茹でることで、えぐみを軽減できます。
ここでは正しい下処理法を詳しく説明します。
たけのこの下処理の材料
たけのこの下処理には以下のものを準備しましょう。
- たけのこ … 3本
- 米ぬか … 1カップ
- 鷹の爪 … 1~2本
- 大きめの鍋



鷹の爪は防腐作用や殺菌効果があり、たけのこを傷みにくくしてくれます。
米ぬかがない場合は、重曹や米のとぎ汁、生米でも代用できます。
米ぬか以外を使う場合の分量や注意点は、以下を参考にしてください。
| 分量(たけのこ2本の場合) | 注意点 | |
|---|---|---|
| 重曹 | 水…2ℓ 食用重曹…小さじ2 | |
| 米のとぎ汁 | 米3合分のとぎ汁…2ℓ程度 | 1~2回目の濃いとぎ汁を使う 無洗米はぬかがないので使わない |
| 生米 | 水…2ℓ 生米…大さじ4 | 無洗米はぬかがないので使わない |
たけのこの下処理の手順
たけのこの下処理の手順を詳しく解説していきます。
土がついた外側の皮をむく。
たけのこの先端には、えぐみ成分が集中しているため、切り落とす。
火が通りやすくなるよう、たけのこの身が切れないところまで皮に切り込みを入れる。
たけのこの頭が出ないくらいたっぷりの水を入れる。
たけのこが浮いてこないよう、落し蓋は重みのあるものを使う。
落し蓋はお皿や小さめの鍋の蓋でも代用可能。
硬い部分に竹串がスッと入るくらいまで茹でる。
6時間~ひと晩、茹で汁につけたままにする。



たけのこは皮付きで茹でましょう。
たけのこの旨味や風味が逃げるのを防いでくれますよ。
また、皮の中の亜硫酸塩の効果で柔らかく仕上がります。
鍋にたけのこが入らない場合は、皮をむいて下処理しても大丈夫です。
もし、下処理後のたけのこがえぐければ、同じ手順で再度あく抜きをしてみてください。
- 米ぬかや鷹の爪の入った茹で汁ごと保存容器に移す
- 冷蔵庫で5~6日保存可能
- 皮をむかずに保存すれば風味が逃げにくい
下処理後のたけのこはどんどん風味が落ちていくので、早めに食べるのがおすすめです。
たけのこにえぐみが残る3つの原因


きちんと下処理したはずなのに、えぐみが残っている時ありますよね。
下処理後のたけのこに、えぐみが残る原因は3つあります。
- 収穫から時間が経っていた
- 茹で時間が短い
- 茹でた後すぐに引き上げた
ひとつずつ解説していきます。
たけのこの収穫から時間が経っていた
収穫してすぐのたけのこは、生のまま食べられるほどえぐみがありません。
たけのこのえぐみは時間が経つにつれ増え、翌日には2~3倍になります。
なるべく早く下処理して、えぐみを増やさないことが大切です。
日光に当たることも、たけのこのえぐみが増える原因です。
茹でるまでは新聞紙などで包んで、日光に当たらないように保存しましょう。
たけのこの茹で時間が短い
茹で時間が短いと、細胞の中のえぐみ成分を十分に取り除けません。
柔らかくなるまで加熱して細胞が壊れると、えぐみ成分がしっかりと茹で汁に溶け出します。
たけのこの根元に竹串が通るくらいまで、弱火で1時間ほど茹でましょう。
アミノ酸のチロシンが、えぐみ成分のホモゲンチジン酸に変化するのを防げます。
茹でた後すぐにたけのこを引き上げた
たけのこを茹でた後にすぐ引き上げると、えぐみが残ってしまいます。
たけのこは茹で汁につけまま6時間~ひと晩冷ましましょう。
長く茹で汁に浸すことで、えぐみ成分がアルカリ性の水に良く溶け出します。
さらに、米ぬかの旨味や風味が、たけのこのえぐみを感じにくくしてくれます。
えぐみを感じにくいおすすめ料理法2つ


下処理後のたけのこに、えぐみが残っていると感じるかもしれません。
でも安心してください。
料理法を工夫すれば、えぐみを感じにくくできますよ。
ここではおすすめの料理法を2つ紹介します。
順番に解説していきます。
衣をつけて揚げる…天ぷらや唐揚げ
揚げ物はたけのこのえぐみを感じにくくしてくれる、おすすめの料理法です。
たけのこのえぐみ成分は油には溶け出しにくいので、油の膜がえぐみを感じにくくしてくれます。
さらに、天ぷらや唐揚げの衣が、えぐみ成分が直接舌に触れるのを防いでくれます。



衣に粉チーズを混ぜると、チーズの風味がえぐみをより軽減してくれますよ。
味の濃い料理…チンジャオロースやマーボー春雨
えぐみの残ったたけのこは、味の濃い料理に活用しましょう。
チンジャオロースやマーボー春雨の濃い味付けは、たけのこのえぐみを気にならなくしてくれます。
細い千切りや小さくカットすれば、たけのこに味がしみこみやすく、えぐみを気にせず美味しく食べられますよ。
えぐみのない旬のたけのこで春を満喫しよう!
たけのこのえぐみ成分の正体は、ホモゲンチジン酸とシュウ酸です。
ホモゲンチジン酸は体に害はありませんが、シュウ酸は尿路結石の原因となるため注意が必要です。
2つのえぐみ成分は、丁寧に下処理すれば取り除けます。
以下の3つの要点を押さえて下処理してくださいね。
- なるべく早く下処理する
- 米ぬかや重曹を入れて、根元が柔らかくなるまで1時間ほど茹でる
- 茹で汁につけたままひと晩冷ます
もし、えぐみが残っても天ぷらにすれば美味しく食べられますよ。
えぐみが心配で手を出しにくかった皮付きたけのこ。
旬ならではのたけのこの美味しさとともに、春の訪れを楽しんでみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。


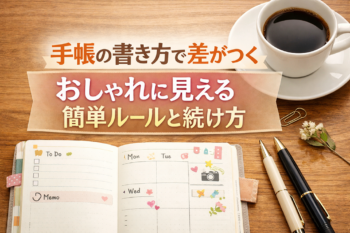
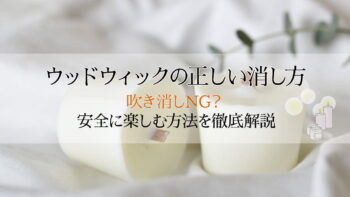
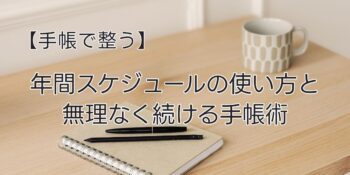
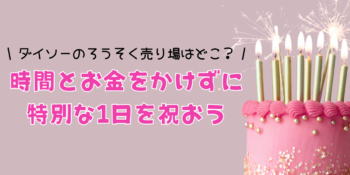
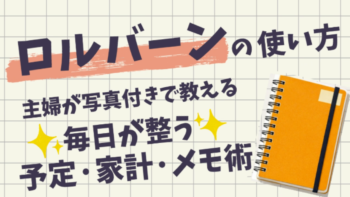
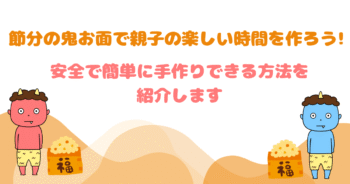
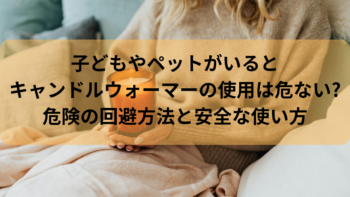

コメント