 読者様
読者様避難指示って言われてもすぐには動けない。
家族やペットのこともあるしどうしたらいいかしら。
避難指示が出た時「すぐに動けない」と感じる人は多いのではないでしょうか。
家族の介護・健康面・ペットの存在など避難所での生活に対する不安は図り知れません。
災害時に「避難指示が出ているのに避難しない人がいる」と報道されることがあります。
一見すると、自己判断で避難を拒んでいるように映るその行動の裏には、さまざまな事情が隠れています。
この記事では、「避難しない」という選択の背景にある理由や避難時の準備点などを紹介します。
- 避難指示が出ても避難しない人の背景や事情
- 避難所に行かない避難の方法
- 避難準備の具体例と工夫
読者の皆様がご自身やご家族の避難について改めて見直すきっかけとなれば幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
避難指示が出てもすぐに避難しない人の事情とその背景


災害が起きた際に、避難しない人を見て「なぜ?」と思ったことがある方もいるかもしれません。
その背景には思い込み・心理的な作用・家庭事情などがあります。
次の章で詳しく解説しますね。
避難指示に従えない心理的な理由とは
人は危機が迫った時でも「自分は大丈夫」と思い込んでしまう傾向があります。
これは「正常性バイアス」と呼ばれ、避難の判断を遅らせる大きな要因です。
「周囲の人も避難していないから」「避難所に行っても不安」という集団同調性や心理的負担も、避難をためらう理由となります。
避難指示が出た時も冷静に対応できるよう、普段から災害が起きた場合の避難について考えておくことが重要です。
避難しないのではなく避難できない現実
避難が困難な人は、私たちの身近にたくさんおられます。
たとえば、以下のような方々です。
- 高齢者、認知症や難聴などサポートが必要な人
- 障害を持つ家族がいる家庭
- 医療的ケア(在宅酸素・服薬など)が必要な人
- 乳幼児を抱える家庭
- ペットを飼っており、同行避難できる場所がない人
- 日本語が不自由な外国人や、避難情報にアクセスしづらい人
このように避難指示が出た時でも避難場所に迷ったり、避難をためらうことがあります。
家族だけでは避難が困難な場合は、医療サポートや福祉サポートが必要です。
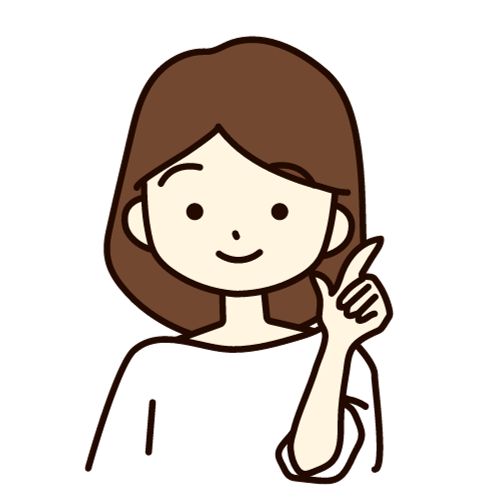
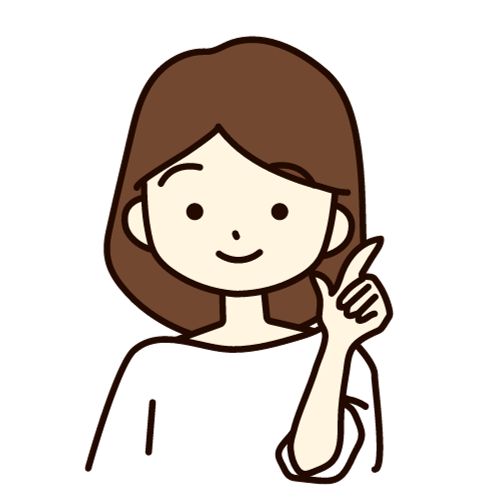
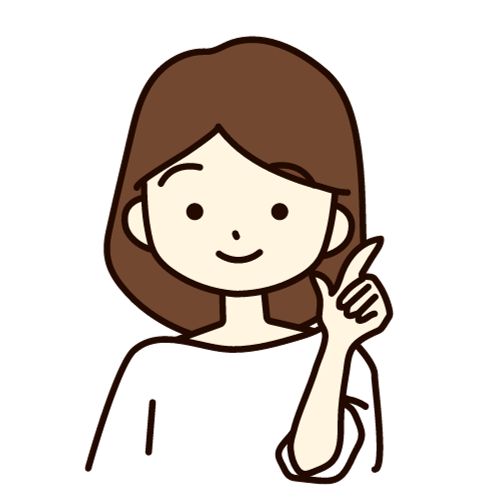
「避難しない」のではなく、「避難できない」状況にあるのです。
認知症の家族がいる場合の避難の難しさ
家族に認知症の方がいる場合、避難行動はさらに複雑になります。
認知症の方々は、普段と違う環境に強い不安や混乱を感じたりすることが多いです。
見慣れない場所や人との接触が続くと混乱しやすく、夜間に不穏な言動が出ることもあります。
避難所での生活に対する不安が大きく、家族は「避難所に行けない」という判断に至ることがあります。
また、周囲の理解が得られにくいことも課題です。
「迷惑をかけてしまうかもしれない」「落ち着かせるのに他の人の手を借りることになるのでは」といった不安が、避難そのものをためらわせる要因になります。
避難の選択には、本人だけでなく介護する家族の心理的負担も大きく影響しているのです。
避難所に行かないという選択肢


避難指示が出たら、避難所に行くと思われている方が多いと思います。
しかし、最近では避難所以外での過ごし方も増えつつあります。
分散避難や自宅避難と呼ばれるものです。
また、特別な配慮が必要な人のための福祉避難所と呼ばれるものもあります。
メリット・デメリットがあるため両側を知って、避難時の選択肢を広げましょう。
ひとつずつご紹介します。
分散避難
近年では新型コロナウイルスの流行があり、感染予防という観点から「分散避難」という考え方が浸透してきました。
分散避難とは?
災害時に避難者が一箇所の避難所に集中するのではなく、自宅や親戚・知人宅、ホテル、車中泊など複数の場所に分かれて避難する方法です。この方法は、避難所の混雑を避け、感染症のリスクを低減するために有効とされています。
水害時の分散避難推進の手引き
分散避難にはメリットとデメリットが存在します。
それぞれをわかりやすく表にまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 人混みを避けることができる | 支援物資が届きにくい場合がある |
| 集団での避難による感染症リスクを下げられる | 行政に避難状況が把握されにくい場合がある |
| 家族ごとの避難先を選ぶことができる |
メリット・デメリットはありますが、指定された避難所以外にも、自分や家族にとって安心できる場所を複数確保することで、避難のハードルを下げることができます。
自宅避難
建物の構造や立地条件が安全と判断できる場合は、自宅で避難生活を送るという選択肢もあります。
自宅避難のメリット・デメリットも表にまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 落ち着いた環境を保てる | 停電・断水への備えが必要 |
| 環境の変化に敏感な高齢者や子どもが安心できる | 建物の安全性の確認が不可欠 |
| プライバシーが守られる |
食料・水・電源・トイレなど、ライフラインを自力で維持できる備えが必要ですが、しっかりと準備をすることで避難先の選択肢になります。
行政も、すべての人を避難所に収容できるとは限らないため、在宅避難を支援する流れが広がっています。
福祉避難所
要配慮者(高齢者、障害者、妊産婦など)を受け入れる福祉避難所という制度があります。
福祉避難所とは、災害時に一般の避難所では生活が困難な高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、傷病者などの要配慮者を受け入れるために設置される避難所です。
平時には福祉施設や学校などの公共施設を指定し、自治体が中心となって管理・運営します。
一般の避難所では生活が困難な方々のための場所ですが、開設には時間がかかり、事前登録が必要な自治体もあります。
地域の福祉避難所の場所・利用条件を把握しておくことが大切です。
避難所に行かない選択をした場合の備えとは


避難所に行かない選択をした場合、どんな備えが必要か具体的な例を挙げて紹介します。
家族に合わせた非常用持ち出し袋の準備
避難所に行くかどうかに関わらず、万が一に備えて持ち出し袋は準備しておきましょう。
| 対象 | 主なアイテム例 |
|---|---|
| 高齢者 | お薬手帳・保険証コピー・紙オムツ・補聴器+電池・老眼鏡・口腔ケアグッズ |
| 乳幼児 | 紙オムツ・おしりふき・ミルク・哺乳瓶・着替え・母子手帳・離乳食スプーン |
| 持病のある人 | 常用薬・服薬スケジュール・医師の指示書コピー・処方箋予備・血圧手帳 |
| 共通 | 飲料水・レトルト食品・モバイルバッテリー・タオル・ティッシュ・懐中電灯・現金 |
準備物は、他にもたくさんありますが医療サポートを受けるまでに時間がかかる場合があるため、常備薬や普段飲んでいるお薬手帳や医師の指示書コピーなどがあると安心です。
日頃の話し合いと避難計画の重要性
急な避難指示に慌てないためには、事前の話し合いが欠かせません。
「誰が誰を連れてどこへ行くか」「どのタイミングで動くか」など、避難計画を家族で共有しておくことで、判断の迷いを減らすことができます。
ハザードマップを共有し、避難場所や危険箇所をあらかじめ確認しておくことも大切です。
携帯電話での連絡が困難な場合に備え、家族間で避難先を共有しておくことで、いざという時の安心感につながります。
地域とのつながりが“孤立”を防ぐ
避難が難しい家庭ほど、地域とのつながりが大きな助けになります。
自治体が開催する防災訓練や地域のサロンなどに参加し、顔見知りを増やしておくことが大切です。
民生委員や自治会の方に、自宅の事情(介護が必要・障害のある家族がいるなど)を事前に伝えておくと、支援の対象として把握してもらいやすくなります。
特に一人暮らしの高齢者や、支援が必要な家族を抱える家庭では、「助けて」と言える関係性を築いておくことも“備え”のひとつになるでしょう。
避難指示が出ても避難しない理由と命を守るためにできる備え
避難できない理由は、さまざまです。
家族の介護・健康上の理由・障害や乳幼児の存在・ペットとの暮らしなど避難できない事情があることも。
決して命を軽視しているわけではなく、家族の状態や現実的な問題の中で苦渋の判断をしています。
大切なのは、その背景を知り、責めるのではなく理解を深めることです。
また、人は危機が迫ったときでも「自分は大丈夫」と思い込んでしまう「正常性バイアス」によって、避難の判断が遅れることがあるとご紹介しました。
こうした背景を踏まえ、いざという時に命を守るために普段から備える必要があります。
- 避難所以外にも選択肢があることを知る(分散避難、自宅避難、福祉避難所)
- 自分たちの家族に合った非常用持ち出し袋を準備する
- 日頃から避難先や行動計画を家族で共有する
- 地域とのつながりを持ち、孤立を防ぐ
避難には正解はありません。
だからこそ、家族の状況に合わせた「わが家の避難」を考え、備えておくことが何よりも大切です。
避難にはいくつもの形があり、自分たちに合った方法を選び、備えることが命を守る第一歩となります。
まずは今日から、少しずつ“避難”について考えてみませんか?
最後までお読みいただきありがとうございました。

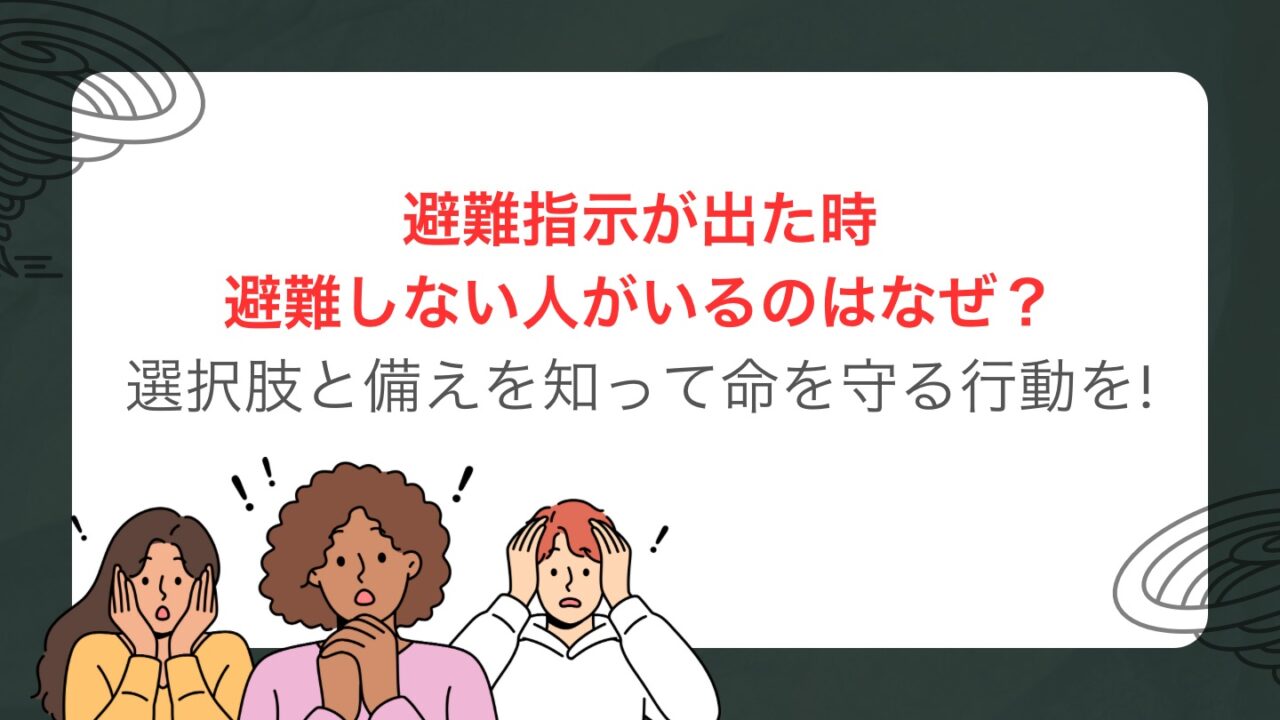
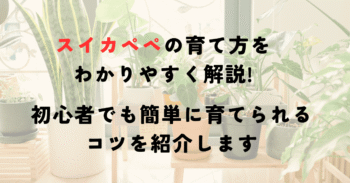
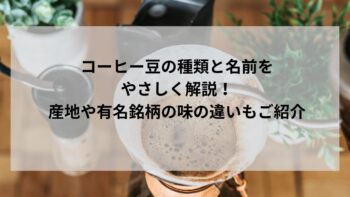

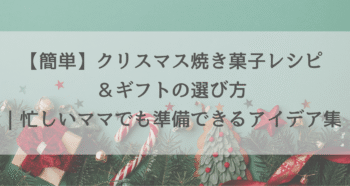

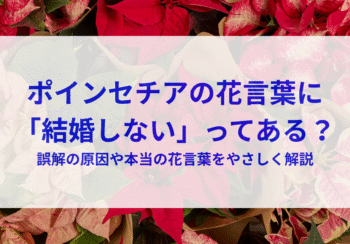

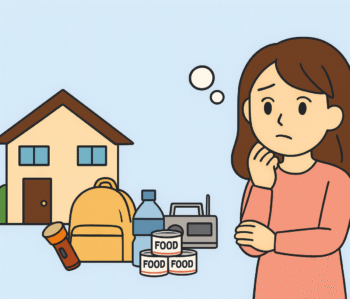
コメント