 読者さま
読者さま正月飾りはいつまで飾るの?うちの実家と夫の実家で違うみたいなんだけど、どうしたらいいのかしら?



お正月などの行事ごとは地域によって習わしが違ったりしますよね。
お互いのご実家を大切にしつつ、新しい年を気持ちよくスタートさせる方法をご紹介します。
門松やしめ飾り・鏡餅、松の内という言葉。
なんとなく知っているけど、子供にちゃんと説明できる自信はない。
そう思っているママも多いのではないでしょうか?
この記事では、それぞれの正月飾りの意味と年神様との関係性、正月飾りを出すタイミングと片付けるタイミングについて説明します。
忙しい人向けに簡単にできる飾り方と片付け方も紹介しています。
行事ごとを大切にしているママ向けに、子供と楽しく正月飾りについて学べるアイデアも紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください。
正月飾りはいつからいつまで飾るの?


正月の飾りは、新しい年に幸せをもたらしてくれる年神様をお迎えするために飾ります。
大掃除で家をきれいにし、年神様をお迎えする準備ができたことをあらわすものです。
いつ出して、いつ片付ければよいのか、順番に説明します。
正月飾りを出す時期はいつ?
正月の準備を始める「正月事始め」である12月13日以降いつでもよいとされています。
クリスマスが終わってから飾り始めることが多いですが、最も縁起が良いのは12月28日です。
28日には末広がりの「八」という字が入っています。
「末広がり」には先が広がっているイメージから、だんだんと繁栄・発展していくという意味が込められています。
そのため12月28日は最も縁起が良いとされています。
反対に避けた方がよい日は12月29日と31日です。
29日は「二重苦(にじゅうく)」と読めるため、縁起が悪いと言われています。
苦しみが重なってしまうことをイメージさせるため避けましょう。
31日に飾ることは「一夜飾り(いちやかざり)」と呼ばれ、急いで準備をするという意味合いがあります。
年神様に対し誠意がなく、失礼にあたるので避けた方が良いでしょう。
また、一日であわただしく準備するということが、葬儀の準備を連想させるとも言われており、そういった面からも縁起が悪いとされます。
正月飾りを片付けるのはいつ?
正月飾りを片付けるのは、松の内が終わってからです。
「松の内」とは新年の期間を表す言葉で、年神様が家に滞在している間のことをさします。
松の内の間に新年の挨拶や親戚周りなどのお正月の祝い事を行い、無病息災や商売繁盛などを祈ります。
松の内には地域差があり、基本的には1月7日までのところが多いですが、関西・四国地方では1月15日までとなっています。
そのため、関西・四国地方では1月15日の朝に、その他の地方では1月7日の朝に正月飾りを片付けます。



どうして地域によって松の内の日にちが違うのかしら?
もともと、松の内は小正月である1月15日とされていました。
しかし幕府が、江戸幕府の三代目将軍・徳川家光の月命日である20日に鏡開きを行うことを避け、鏡開きを1月11日に早めるよう制定しました。
お正月のお祝い事も鏡開きまでに済ませるよう、江戸を中心とした関東地方で松の内が1月7日まで早まったと言われています。
一方、幕府の影響が少なかった関西地方を中心とした地域では、古くからの習わしである1月15日が残ったため、地域差が出たと言われています。
1月20日まで飾る地域もありますし、沖縄では旧暦の1月14日(2月初旬頃)まで正月飾りを飾っています。
地域によっては独自の習慣があるので、住んでいる地域に合わせて正月飾りをしまうのが良いでしょう。
住んでいる地域の習慣が分からない場合、近くの神社に問い合わせたり、近所の家の様子を参考にするとよいです。
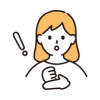
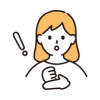
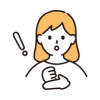
じゃあ今住んでいるところの習わしに合わせて片付ければいいのね!
片付けた後は神社に奉納して正月飾りを処分してもらいます。
正月飾りを使いまわすことは、縁起が良くないので避けましょう。
小正月である1月15日には、神社で「どんと焼き」「左義長(さぎちょう)」などと呼ばれる火祭りが行われます。
火祭りでお焚き上げしてもらうのが、正月飾りの正しい処分方法です。
忙しくて神社に行く時間が取れない場合、自宅でも処分できます。
自宅で処分する場合、大きな紙の上に処分する飾りを置き、塩を振りかけてお清めをして、紙で包んで捨てましょう。
年神様に感謝の意を示すためにも、一般のごみとは分けて捨てるのが好ましいです。
正月飾りの役割と年神様との関係


正月飾りには門松・しめ飾り・鏡餅の3つがあります。
それぞれに役割や年神様との関係があるので、ひとつずつ説明します。
門松


門松には、家に邪気が入り込まないように家を守る役目と、年神様をお迎えする目印という2つの役目があります。



神様は、門松を目印におうちを見つけるの?



その通りです!神様が迷わないように、門松は玄関の前の目立つところに置きましょう。
3本の竹を中心に立てて梅を添え、根元を松で囲み、藁で囲ったものが一般的です。
- 竹は成長が早く生命力が強いため子孫繁栄や発展を表します。
- 梅は寒い冬に花を咲かせることから生命力や忍耐力・気高さを表します。
- 松は一年中葉を落とさないため生命力があり、長寿を表します。
また、松という読み方が「祀る」に似ているため、神様を祀る木としてもふさわしい木と言われています。
門松は、年神様が見つけやすいように玄関の脇に一つずつ飾ります。
しかし、マンションなど共同住宅では共有スペースに物を置くことを禁止している場合もあるため、ルールをよく確認しましょう。
玄関脇に置けない場合は、玄関の内側に飾っても大丈夫です。
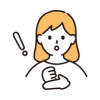
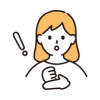
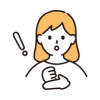
うちはマンションだから下駄箱の上に置こうかしら。
しめ縄


しめ飾りは、しめ縄に飾りを付けたもので、年神様をお迎えするときに、清浄な場所であることを示します。
年神様が現世に降りてくるための結界のような役目があり、前年の悪いものや災いが入って来ないように、という願いも込められています。



しめ飾りは神様がおうちに入ってくるときに、悪い人も一緒に入って来ないようにバリアしてくれるの?



素晴らしいです!だから、入口である玄関に飾るんですね。
しめ飾りの下をくぐり神域に入ると考えられており、玄関の上など少し高い場所に飾ります。
しめ飾りは注連縄(しめ縄)に、紙垂(しで)・裏白(うらじろ)・ゆずり葉などがついたものです。
- 紙垂(しで)
しめ飾りについた白い紙。神域を区切る意味を持ち、しめ飾りの向こうが清浄な場所であることを示します。
- 裏白(うらじろ)
シダという植物の別名。シダの葉は裏が白く、心が清らかであることを表します。また、シダの葉は左右対称であり、夫婦円満の象徴としても用いられます。
- ゆずり葉
新しい葉にあとを譲るように古い葉が落ち、落ちた葉が肥料となります。代々親から子へ受け継がれていくことに似ているため、子孫繁栄を表しています。
鏡餅


鏡餅は、お餅を「神様が宿る」と考えられていた鏡に見立てたもので、家を訪れた年神様が宿る場所となる飾りです。
昔は丸い鏡が主流だったため、鏡餅も丸い形になったと言われています。



鏡餅の中で神様は過ごすの?



神様がおうちにいる間は、鏡餅が居場所となります。神様が気持ちよく過ごせるよう、お餅にカビが生えたりしないようにしたいですね。
昔からお米には一粒一粒に神様が宿っていると言われてきました。
お米を一粒も残さず食べなさいと言われるのは、神様が宿っていると言われているためです。
神様が宿ったお米を固めたお餅は、さらに強い神様が宿る神聖な食べ物とされていました。
お餅を二段重ねにするのには諸説ありますが、「陰と陽」や「太陽と月」をあらわしている、「円満に年を重ねる」という願いを込めた、などと言われています。
みかんのイメージが定着していますが、本来は鏡餅の上に橙(だいだい)をのせます。
子孫繁栄を願う「代々」と同じ響きのためと言われています。
鏡餅は、家の中にいくつ飾っても良いとされています。
神棚、床の間、寝室など神様が来てほしい場所に飾るのが良いでしょう。
鏡餅は、お正月が過ぎたら木槌で叩いて鏡開きします。
鏡開きをすることで年神様をお見送りして、鏡餅を食べることで神様の力を体内に取り込みます。
刃物は切腹を連想させ縁起が悪いので、木槌で叩いて割るのが一般的です。
「鏡開き」も地域によって日にちが違ってきます。
一般的には鏡開きの日は1月11日ですが、京都では1月4日に、その他の関西地方では、1月15日や1月20日が鏡開きの日となっています。
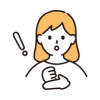
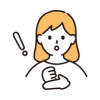
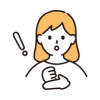
鏡開きも住んでいる地域の習わしに合わせて行えばいいのよね。
正月飾りのよくある疑問と工夫


ここまで正月飾りの意味や出すタイミング、片付けるタイミングについて説明しました。
でも、家事や仕事、育児で忙しい日々の中、つい正月飾りを出し忘れてしまったり、片付けるのを忘れて松の内を過ぎてしまったりしてしまいますよね。
片付け忘れてしまうと縁起が悪くなると言われたりしますが、本当なのか。
また、忙しい人向けに簡単にできる正月飾りの飾り方や片付け方を紹介します。
子供と楽しく正月飾りの意味や役割を学ぶ方法も紹介するので、ぜひチェックしてください。
正月飾りを長く出しすぎると縁起が悪い?
結論から言うと、松の内を過ぎてから片付けても運気が下がったり、縁起が悪いということはありません。
正月飾りは、松の内が明けたら片付けて処分するものですが、日々の忙しさに追われて遅くなってしまうこともあります。
松の内を過ぎてしまっても、気が付いたときに処分をすれば問題ありません。
ただ、特に門松やしめ飾りなど外から見えるものは、片付けがあまりにも遅いとだらしない印象を与えてしまうので、気付いたら早めに片付けることをおすすめします。
子どもにも伝えたい!行事の由来
子供に行事の意味や大切さを伝えたいと考えているママも多いと思います。
家族で楽しみながら、正月飾りについて学べるアイデアを3つ紹介します。
工作が好きな子供なら実際に自分で作ることで、どんな形をしていて何が使われているのかなど、楽しく作りながら知ることができます。
作りながら、「門松にはこんな意味があるんだよ」などと伝えてあげることで正月飾りの意味も学べます。
門松はラップの芯や紙コップ・ストローなどを竹に、割りばしや毛糸・つまようじなどを松に見立てることで簡単に作れます。
新聞紙や折り紙を使えば、鏡餅やしめ飾りも簡単に作れるでしょう。
市販のキットを活用する方法もあります。
自分で作った飾りならどこに飾ってあるかなど興味を持つので、自然と正月飾りに子供の意識がいくでしょう。
小学生ぐらいの子供なら、クイズ形式にして楽しく遊びながら正月飾りの意味を学ぶ方法もあります。
クイズを出題したあと、正月飾りの意味や形などを説明し、子供の理解を深めていきます。
可能であればクイズをおこなったあとで、正月飾りの売っているお店や神社へ実物を見に行くと、よりイメージがつきやすくなります。
年末が近づくと、神社や子育て支援センターなどで正月飾りを作るワークショップが開催されます。
そういったイベントに参加し、本物の材料に触れたり、プロから正月飾りの意味や由来を教えてもらうのもよいでしょう。
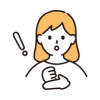
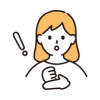
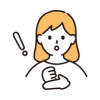
子供と一緒に正月飾りを作ると、楽しくお正月の行事について学べそう!
忙しい人向け!簡単正月飾り&片付け術
門松・しめ飾り・鏡餅すべてを用意するのは大変という方は、しめ飾りだけ用意しても大丈夫です。
忙しい人向けに簡単にできる正月飾りの飾り方と片付け術を紹介します。
- 木やガラス、プラスチック製の飾りにする
出すのもしまうのも簡単ですし、来年も使えるので買いに行く手間が省けます。
スリーコインズや100円ショップでも売っているので手軽に買えます。
- 松や竹をあしらったフラワーアレンジメントやリースで代用する
ひとつで門松としめ飾りの代用ができます。
神社に奉納に行けなければ、塩で清めて紙に包めば自宅で処分できます。
- 鏡餅は鏡開きしやすいものを用意する
食べやすく小分けされた餅が鏡餅型のケースに入っているものや、小さいものだとそのまま食べられるので鏡開きするときに楽です。
- 門松は卓上のものを用意する
奉納しに行くとしても、自宅で処分するとしても、小さい方が処分が楽です。



風水的には、ドライフラワーは陰の気を呼ぶので良くないんですよね?



それから、せっかくやってきた運気を跳ね返してしまうため、風水の観点からは玄関の扉に飾りをかけるのはNGです。
玄関の上部や扉の横、下駄箱の上などに飾りましょう。
風水的に一番大切なのは、玄関の掃除をしっかりした上で飾りを置くことです。
汚れた玄関には貧乏神が来ると言われています。
正月飾りをいつまで飾るのか理解して年神様を迎えよう!
年神様をお迎えするための正月飾りは、「正月事始め」の12月13日以降に出します。
縁起の悪い29日(二重苦)と31日(一夜飾り)は避け、特に縁起の良い28日に正月飾りを出すと良いと言われています。
正月飾りを片付けるのは「松の内」が終わって年神様が帰ってからです。
松の内は地域によって1月7日や1月15日など差があるので、自分の住んでいる地域の習わしに合わせましょう。
処分する際は、神社に奉納しお焚き上げしてもらうのが理想です。
忙しく奉納に行けない場合は、自宅で塩で清めてから紙に包んでごみとして捨てても構いません。
その際、年神様へ誠意を示すためにも一般のごみと分けて出すことが好ましいです。
正月飾りと年神様との関係は以下の通りです。
- 門松
家に邪気が入らないよう守る役割と年神様に家を見つけてもらう目印の役割がある。
用いられている松竹梅それぞれに長寿・子孫繫栄・生命力といった意味が込められている。
- しめ飾り
年神様にここは清浄な場所であると示す役割がある。
飾りそれぞれに清らか・夫婦円満・子孫繁栄といった意味が込められている。
- 鏡餅
年神様の宿る場所という役割がある。餅には強力な神様が宿ると言われている。
二段重ねには「陰と陽」「太陽と月」「円満に年を重ねる」など諸説ある。
上にのせる橙は「代々」とかけ子孫繁栄の意味が込められている。
正月飾りを長く出しすぎても運気が下がることはありませんが、周りの人にだらしない印象を与えないためにも、気付いたときに早めに片付けましょう。
子供と楽しく正月飾りの意味や役割を学ぶ方法として以下の3つの方法があります。
- 自宅で一緒に正月飾りを手作りする
- クイズ形式にして正月飾りの意味を学ぶ
- 地域のお正月の行事やイベントに参加する
忙しい人は、しめ飾りの用意だけでも十分です。
毎年使える木製などの飾りを使ったり、フラワーアレンジメントで代用する、鏡開きしやすい餅を用意する、処分しやすい小さいものにするといった工夫もできます。
幸せな一年を迎えることができるよう、自分に合った方法で楽しく正月飾りの準備をしてみてください。

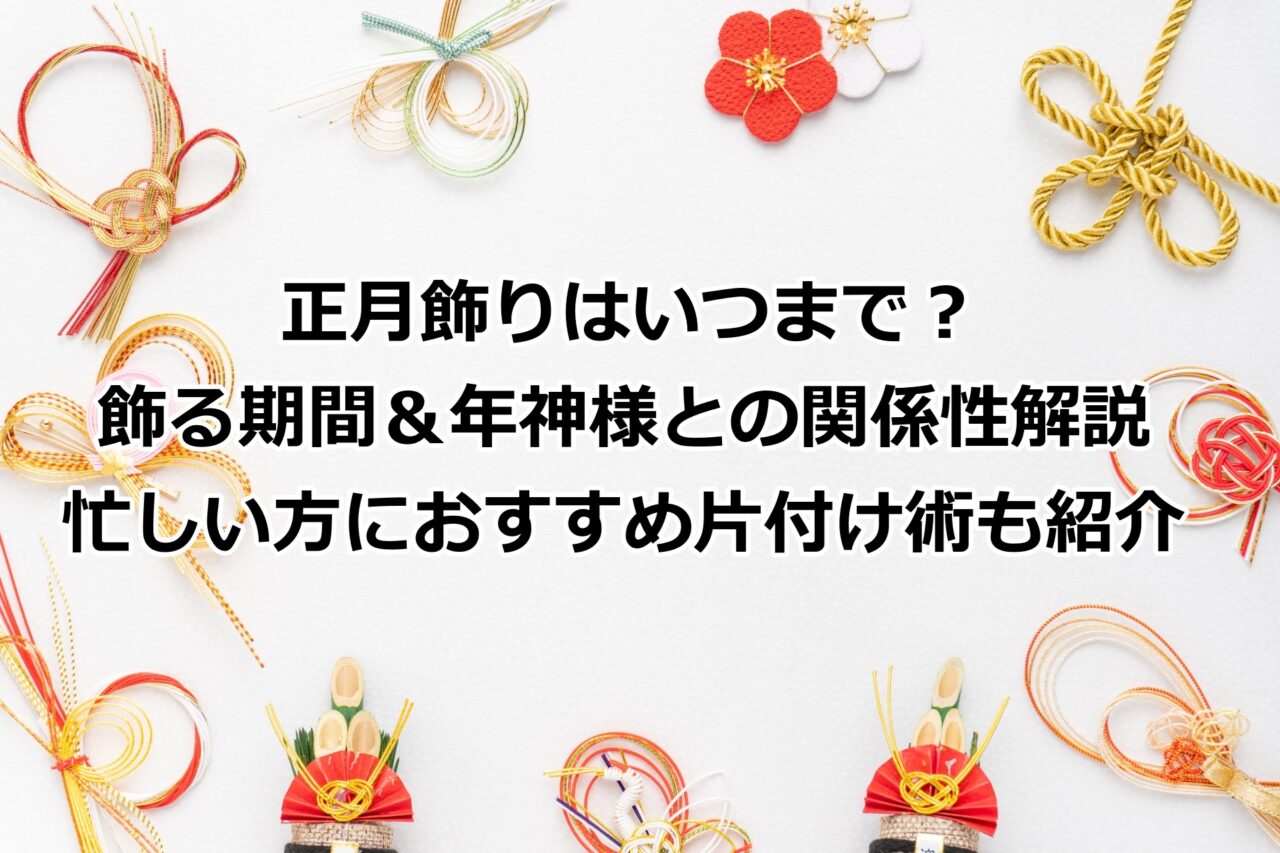
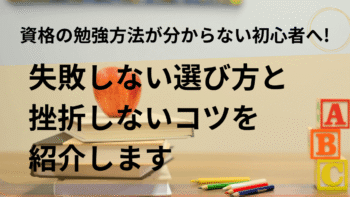

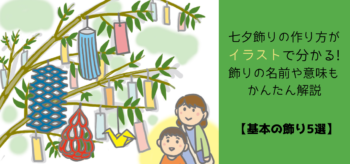

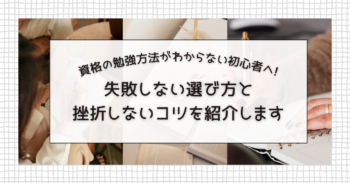

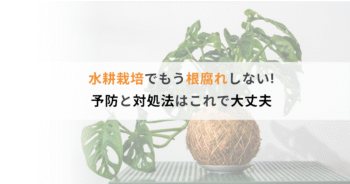

コメント