 読者様
読者様うちは毎年あげてるのに、義理のお姉さんは我が子にくれない
お正月に子どもたちが楽しみにしている「お年玉」。
ところが、「親戚の○○さん、うちの子にくれなかった…」「義理の両親がうちの子だけくれながった」と感じた経験はありませんか?
つい気になってしまうものの、直接は聞きづらく、毎年モヤモヤしてしまう方も多いはずです。
そういった問題を解決するために、この記事では以下について紹介しています。
- お年玉の本来の意味と文化
- お年玉の金額の相場や親戚の線引き
- 親戚が「お年玉をくれない」理由
- お年玉をくれない親戚への対応法3選
- お年玉をもらえなかった子どもへの対応
読み終わる頃には、お年玉をくれない理由や、くれない親戚への対応方法を知ることができます。
新年を気持ちよく迎えるヒントとして、ぜひ参考にしてください。
お年玉文化





渡す金額とか親戚の線引きとか、お年玉ってどんなルールがあるの?
お年玉を渡す金額や親戚の線引きについて悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
ここでは、お年玉とはそもそもどんな文化なのかについて紹介します。
意味や由来、金額の目安を理解しておくと、親戚同士の考え方の違いにも納得がいきやすくなります。
お年玉の意味と由来
お年玉の起源は「年神様」へのお供え物にあります。
もともとは新しい年の豊作や健康を祈って、年神様に供えた「餅」を家族で分け合う風習がお年玉の起源になっています。
時代の変化と共に「餅」から「お金」に変化しましたが、本来は「新しい年の幸せを分け与える」という意味が込められています。
単なる金銭的なやり取りではなく、「気持ちを伝える行為」であることを意識したいですね。
お年玉の渡し方は?ピン札やポチ袋について
お年玉は、清潔で新しいお金=新札を使うのがマナーとされています。
お正月は新年を迎えるお祝い事のため、お年玉は結婚祝いや入学祝いと同じご祝儀にあたります。



新札が用意できなかった場合は、比較的綺麗なピン札を使用しましょう。
ポチ袋は表面に子どもの名前、裏面に自分の名前を書いて渡しましょう。
キャラクターものから和柄まで多様ですが、相手の年齢や関係性に合わせたデザインを選ぶと印象が良くなります。
お年玉の金額の相場
お年玉の金額に関して正式なルールは存在しません。
しかし、お年玉の相場はありますので、そちらについて紹介します。
伊予銀行や三菱UFJニコスのサイト調査によると、平均額は以下の通りです。
| 年齢 | 一般的な相場 |
|---|---|
| 幼児(0〜5歳) | 500〜1,000円 |
| 小学校低学年 | 1,000〜2,000円 |
| 小学校高学年 | 3,000円前後 |
| 中学生 | 3,000〜5,000円 |
| 高校生 | 5,000〜10,000円 |
| 大学生以上 | 5,000〜10,000円 |
ただし、地域や家庭の経済状況によって差があります。
また、兄弟姉妹や親戚の間で金額のルールをそろえると、後から金額差で気まずくなることを防げます。



無理をせず、お金ではなく「お祝いの気持ちを込める」ことが一番大切です。
誰にあげる?親戚・甥・姪・いとこの線引き
お年玉を「誰にあげるか」は、家族構成や親戚づきあいの深さで異なります。
一般的には以下のような線引きがされています。
- 甥・姪(兄弟姉妹の子ども):最も多くの人が渡している対象
- いとこ(親戚の子ども):家族ぐるみで交流がある場合のみ
- 孫:祖父母から渡す
住信SBIネット銀行による「お年玉に関する意識調査」では、姪や甥に渡すと回答した人が6割以上いました。
一方で、いとこや親戚の子どもまで広げると、人数が増えて負担も大きくなります。
そのため、親戚間で「どこまで渡すか」をあらかじめ話し合っておくのがおすすめです。
家庭ごとに事情は違いますが、“毎年の不公平感を減らすこと”が長続きのコツです。
何歳まであげる?一般的な目安と地域差
「お年玉は何歳まであげるの?」という疑問もよく聞かれます。
こちらも明確なルールは存在しません。
一般的な目安としては、高校卒業まで(18歳頃)が多い傾向にあります。
楽天市場の「お年玉に関するアンケート」によると、このような結果でした。
- 「高校卒業まで」が約30%
- 「大学卒業まで」が約23%
- 「社会人になるまで」が約12%
ただし、地域差もあります。
関東では「高校までで一区切り」、関西や九州では「大学生でも渡すことが多い」といった文化も見られます。
しかし、年齢にばかり気を取られず、関係性や気持ちを重視するのが重要です。
お年玉をくれない親戚はなぜ?


「親戚の中で、うちの子だけお年玉をもらえなかった…」という経験、意外と多いものです。
でも、実はそこには単なる「悪意」では済まされない背景があることも。
ここでは、お年玉をあげない親戚の心理や事情を具体的に見ていきます。
相手を責める前に、「なるほど」と納得できる視点を持つことで、気持ちも軽くなります。
お年玉文化を経験していない
最近では、家庭によって「お年玉文化がない」ケースも増えています。
親戚付き合いが少なかったり、核家族で育った人の中には、そもそも自分がお年玉を“もらった記憶がない”という人も。
つまり「もらった経験がない=あげる発想がない」ということです。



特に都市部では、親戚同士の行き来が減り、昔ながらの正月の風習が薄れているそうです。
このため、「あげるのが常識」という感覚がない人も自然と増えているのです。
決して冷たいわけではなく、文化的背景の違いといえるでしょう。
もし相手がこのタイプなら、「うちの子がもらえなかった」と悲観せず、時代の流れのひとつとして受け止めてもよいかもしれません。
他人の目を気にしないタイプ
「人は人、自分は自分」と割り切っているタイプの人も、お年玉をあげないことがあります。
昔は「みんながやっているから」と渡す人も多かったですが、最近は価値観が多様化。
中にはこう考える人も増えています。
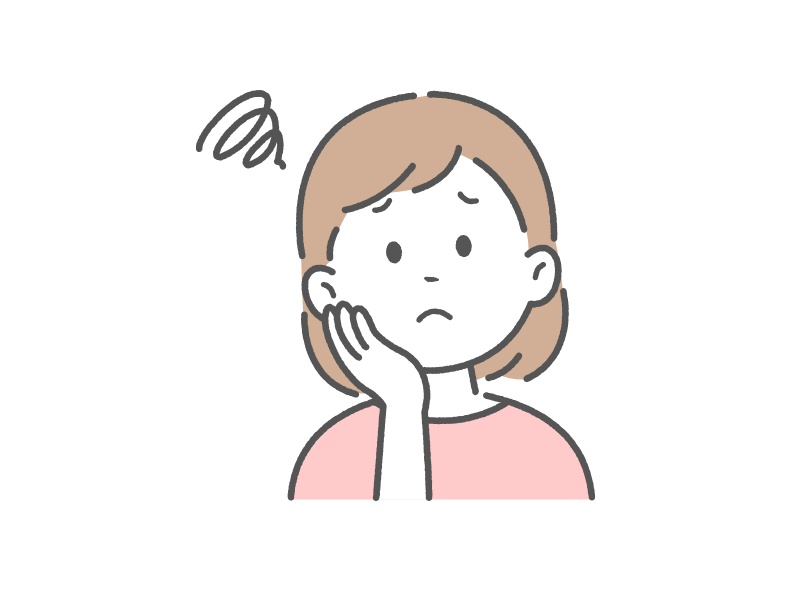
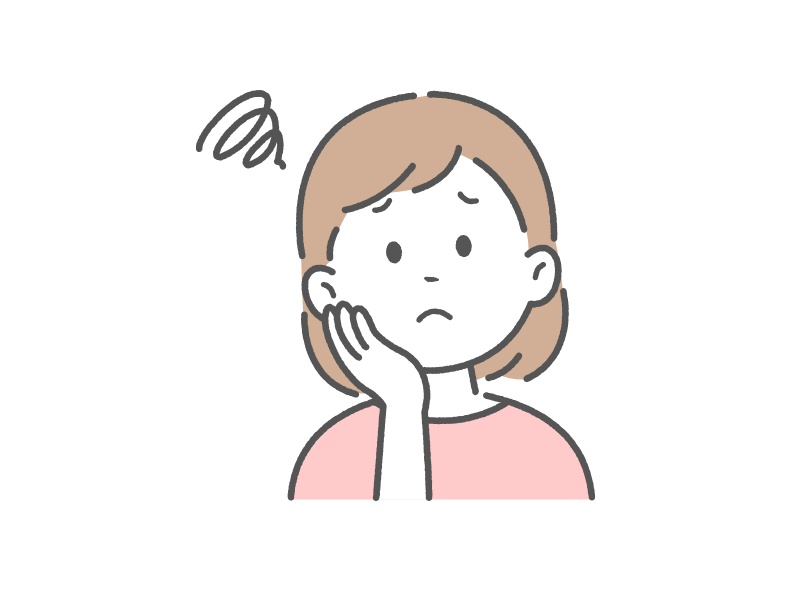
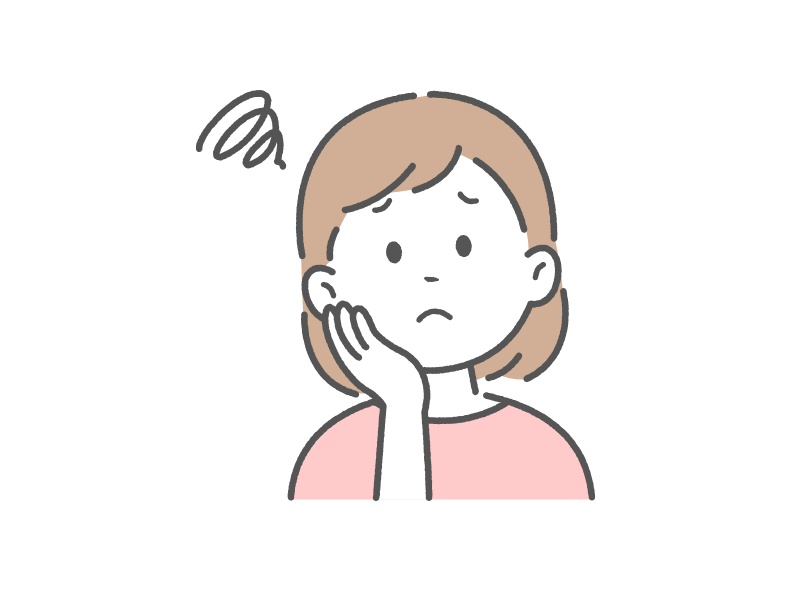
何もせず大金が手に入る「お年玉文化」は我が家の考えに合わない



お年玉を渡すことで上下関係が生まれる気がする
特にミニマリスト志向や“人間関係の距離感”を大切にする人の中には、「義務的な贈与」に違和感を持つケースも。
こうしたタイプの人にとっては、“あげない=冷たい”ではなく、“自分らしい選択”のようです。
経済的な理由で余裕がない
最も現実的な理由が、家計に余裕がないというものです。
特に近年は、物価高や教育費の増加で、親戚関係でもお年玉の負担を感じる人が少なくありません。
そのため、親戚に子どもが多い家庭では「全員に渡すのは正直きつい」という声も。
中には、「自分の子どもにも十分にあげられないのに…」と悩みながら、あえて渡さない選択をする人もいます。
経済的な事情は見えにくいもの。
“くれなかった”ではなく、“無理をしなかった”と考えると、少し優しい気持ちになれるかもしれません。
あげるメリットがない
子どもがいない夫婦や独身の人にとっては、「あげるだけで、もらう側の立場にならない」ため、負担感を覚えることもあります。
このケースでは渡す側も、受け取る側も気まずさを感じている場合があります。
渡す側の人は「自分たちには子どもがいないのに、毎年渡すのは不公平では?」と不満を抱えている可能性があります。
また一方で、もらう側の人も「お返しのしようがなくて気まずい」と感じているかもしれません。
また、親戚の集まりで“お年玉を渡す=子どもの人数分必要になる”ため、金額的にもプレッシャーを感じやすいです。
このような背景から、あえて「全員に渡さない」というルールを自分の中で決めているケースもあります。
受け取る側も、「それぞれの立場で判断している」と理解しておくと良いでしょう。
単に忘れている・気づいていない
意外と多いのが、単に忘れていたり、気づいていないだけというケースです。
お正月は親戚同士での挨拶や準備が多く、特に年配の方や忙しい人ほど、お年玉を用意し忘れることがあります。
たとえば、こちらのようなケースです。
- 封筒を買い忘れた
- ポチ袋を用意していたけど鞄に入れ忘れた
- 「あとで渡そう」と思っていたらタイミングを逃してしまった
これらは悪意ではなく、単なる“うっかり”です。
また、子どもの人数が増えると「どの子に渡したっけ?」と混乱することも。
相手を責めるより、「そういうこともあるよね」と笑って流すほうが、長い付き合いでは賢い対応といえるでしょう。
お年玉をくれない親戚への対応法


お年玉をくれない親戚がいると、なんとなくモヤモヤした気持ちになりますよね。
「うちの子だけもらえなかった…」という状況は、親としても気まずいもの。
しかし、感情的に対応するのではなく、「どうすれば円満にお正月を過ごせるか」を冷静に考えることが大切です。
ここでは、トラブルを避けながら気持ちを整理するための3つの対応法を紹介します。
3つの方法はこちらです。
- 親戚間でルールを決める(話し合いでトラブル回避)
- 自分も渡すのをやめる(公平な判断として)
- 距離をおく・関係を見直す(無理せず穏やかに、気持ちの整理)
順番に解説していきます。
親戚間でルールを決める
まず一番おすすめなのは、「親戚同士でルールを明確にすること」です。
これまでに紹介した通り、お年玉に関する価値観は家庭によって様々です。
「高校卒業まであげる」「自分の子どもがもらわなくなったらやめる」など、各家庭の線引きにズレがあると、どうしても不公平感が生まれます。
年末年始に顔を合わせたときや、グループLINEなどを利用して、このように伝えてみてもいいでしょう。
「そろそろお年玉はナシにしませんか?」
「高校生までに統一しようか?」
金銭的な負担を軽くすることで、誰も嫌な思いをせずにすみ、親戚間の関係もスッキリ保てます。
自分も渡すのをやめる
相手が一方的にくれない場合、自分も渡すのをやめるという選択も立派な判断です。
片方だけがあげている状況は、長期的に見ても不満やストレスにつながります。
ただし、いきなりやめるのではなく、一度状況を観察してから決めるのがおすすめです。
たとえば、このようなケースでは、渡すのを控えることが自然です。
- 相手に子どもがいない
- 以前はもらっていたが、ここ数年なくなった
- あげてもお礼の一言もない
自分の家庭の負担を減らしながら、“対等な関係”を保つための判断として割り切りましょう。
距離をおく・関係を見直す
もしどうしてもモヤモヤが消えないなら、無理に良好な関係を続けようとしないことも大切です。
お年玉をめぐる価値観の違いは、金銭感覚や家庭環境の差に直結していることもあります。



「なんでうちだけ…」と考え続けると、お正月がストレスのもとになってます。
そんなときは、このように距離をおくことで自分と子どもの気持ちを守ることができます。
- 正月の集まりをパスしてみる
- 会ってもお金の話題を出さない
- 「あの人はそういう人」と割り切り、深く関わらない
大切なのは「お年玉よりも人間関係を穏やかに保つこと」。
親の落ち着いた対応は、子どもにとっても“お金より価値ある教え”になります。
お年玉をもらえなかった子どもへの対応


お年玉をもらえなかった子どもが「なんでうちはないの?」と聞いてくることもあります。
そんなときこそ、親として大切な考え方を伝えるチャンスです。
「もらえなかった=悪いことではない」と伝える
お年玉をもらえなかったとき、子どもが「自分が悪いのかな?」と感じてしまうことがあります。
まず大切なのは、“もらえない=価値がない”わけではないと伝えることです。
たとえば、このように優しく説明してみてください。
「お年玉はね、くれる人の気持ち次第なんだよ。もらえなくてもあなたが悪いわけじゃないよ。」
それだけでも子どもの気持ちはぐっと落ち着きます。
また、「もらえなかったこと」に焦点を当てるのではなく、“人とのつながりや経験の価値”を感じられる会話に切り替えるのがおすすめです。
このように伝えてみてはどうでしょうか?
「今年のお正月は誰と会えた?」
「おせちやおもち、何が一番おいしかった?」
親が冷静に受け止めることで、子どもも「お金=愛情の証」ではないと学べます。
この経験は、将来「比較」や「損得」だけで判断しない感性を育てることにもつながります。
お金以外の喜びをつくる
お年玉をもらえなかったとしても、お正月の「楽しい体験」を親が用意することで、子どもの満足度はぐっと高まります。
お金ではなく“楽しい思い出”を贈る工夫が効果的です。
- 家族で「福笑い」「すごろく」「トランプ」などの定番お正月遊びを楽しむ
- 「お年玉代わりのくじ引き大会」を家庭で開催(当たりはお菓子やミニご褒美)
- 「ママ・パパ銀行」をつくり、好きなことをするとポイントが貯まる仕組みを作る
また、「がんばりボーナス」「ありがとうチケット」など、感謝や努力を形にしたご褒美を渡すのもおすすめ。
子どもは「家族と笑い合えた」という経験を通して、お正月が”お年玉をもらう日”ではなく、”楽しいことをする日”と認識します。
お金が動かなくても、心が動く体験こそが、子どもにとって最高のお年玉です。
お年玉を親が準備する
お年玉は「お金をどう使うか・考えるか」を学ぶ絶好のチャンスです。
もらえなかった分のお年玉は親が代わりに用意し、「お金の使い方を考える時間」に変えてあげるのがおすすめです。
年齢に合わせて体験を工夫すると子どもも喜びます。
- 幼児なら「500円で好きな駄菓子を選ぶ」
- 小学生なら「1,000円を“使う・貯める・あげる”に分けてみる」
- 中学生以上なら「1,000円を使って家族の誰かを笑顔にする方法を考えてみる」
親から渡すことで「自由に使う前に考えるもの」という意識を自然に育てられます。
また、使い道を一緒に話し合うことも大切です。
「なんでそれを選んだの?」
「貯めておくのも立派な使い方だね」
こういった会話が家庭内で“お金をポジティブに語る”きっかけにもなります。
「お年玉=金額の多さ」ではなく、「お金をどう扱うか」という経験こそが、将来の金銭感覚を育てる大切な一歩です。
まとめ|お年玉トラブルを解消して気持ちよく新年を迎えよう
お年玉をくれない親戚にモヤモヤするのは自然な感情です。
しかし、「くれない理由」を理解し、「自分の考え」を持って対応することで、無駄なストレスを減らせます。
お年玉はあくまで「気持ちのやりとり」なので、お金にこだわりすぎず、家族が笑顔で過ごせるお正月を迎えましょう。
「お年玉文化」のまとめは次の通りでした。
- お年玉は「新しい年の幸せを分け合う」という意味をもつ昔ながらの風習である
- 金額の相場や誰に渡すかの範囲は家庭や地域によって異なるが、一般的には甥・姪や孫など身近な親戚に渡すことが多い。
- お年玉を渡す年齢の目安は高校卒業までとしている人が多い。
- 形式にとらわれすぎず、気持ちを込めて渡すことが大切。
親戚がお年玉をくれない理由のポイントは以下の5つです。
- お年玉文化を経験しておらず、お年玉を渡す概念がない
- 経済的な理由で余裕がない
- 「人は人、自分は自分」と割り切っており、他人の目を気にしていない
- 自分たちに子どもがおらず、お年玉をあげるメリットがない
- 単に忘れている・気づいていない
お年玉をくれない親戚への対応法のおすすめは次の3つです。
- 「どの年齢まで渡すか」など、親戚間でルールを決めることでトラブル回避する
- もし一方的に渡していて不公平だと感じるなら、自分もやめるという選択も
- モヤモヤが続く場合は、無理に関係を続けず距離をおくのも一つの方法
お年玉をもらえなかった子どもへの対応法は次の通りでした。
- 子どもが「なんでうちはもらえないの?」と感じたときは、まず安心させてあげることが大切。
- 「もらえなかったからといって悪いことじゃないよ」と伝える。
- 代わりに家族で遊んだり、小さなごほうびを作ったりして、お金以外の喜びを体験させてあげるのも効果的。
- 親が少額を用意して「どう使うか」を一緒に考えることで、お金の教育にもつながる。
お年玉をくれない親戚を見ると、つい「冷たい」「うちの子がかわいそう」と感じてしまいがちです。
しかし、実際には「文化の違い」「金銭的事情」「人付き合いのスタンス」など、さまざまな背景があります。
この記事が、そういった背景や対処法を理解するきっかけになっていればうれしいです。
お年玉トラブルを解決して気持ち良くお正月を迎えてくださいね。
夫婦水入らずでのお正月の過ごし方に迷っている方は、こちらの記事もぜひご覧ください。


最後までお読みいただきありがとうございました。


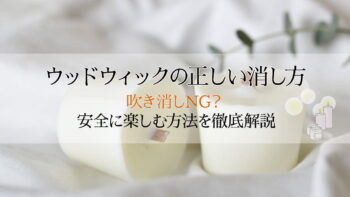

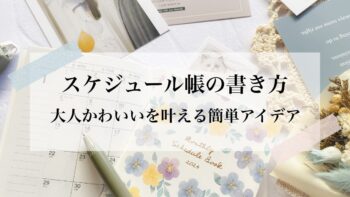
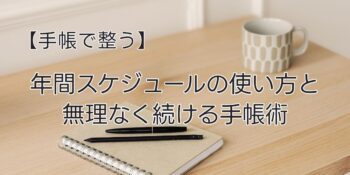
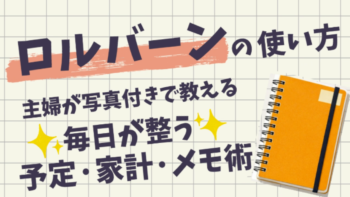


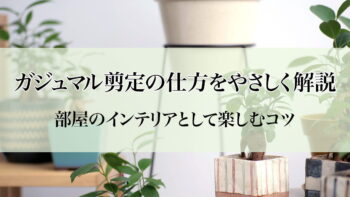
コメント