子育てと仕事に追われる忙しい毎日のなかでも、季節の催し事を大切にしたいという想いは、母親ならだれもが抱えているのではないでしょうか。
そうは言っても、ゆっくり時間をかけて準備することがなかなか難しいという現状もあります。
 読者さま
読者さまなにか、解決する方法はありませんか?



じつは、このようなときにおすすめなのが手作りキットです。
この記事では、忙しい主婦の「やりたい」を叶えるために、節分飾りキットの使い方から、飾る場所、節分期間を終えた後の片づけ方に至るまでをまとめています。
子どもとの楽しい思い出作りに、きっと役立つでしょう。
また、節分にまつわる基本的な知識も織り交ぜています。
読むと、節分飾り作りを通して、子どもに年中行事の意味を伝えられる貴重な時間を過ごすことも——。
今年は、家族との時間を充実させるために、ぜひ節分飾りキットを使ってみてください。
節分飾りのいろは


節分飾りの由来や、飾り付け期間などの基本的な知識をまとめました。
確認しておくことで、日本の文化をより深く楽しむことができますよ。
節分飾りとは?
節分飾りは、季節の変わり目に家の中へ入ろうとする、鬼もしくは邪気を払うための「魔除け」や「厄除け」として飾られてきました。
代表的な節分飾りには、「柊鰯」があります。
これは、柊の葉に焼いた鰯の頭を刺したものです。
このような節分飾りの習わしは、地域によって違いがあります。
情報化が進み、人々の生活圏も広がったことから、いまではさまざまな伝統に触れることができるようになりました。
現代のさまざまな節分飾り
節分は、平安時代頃に中国から伝わり、日本古来の考え方と調和して生まれたと考えられています。
「1年間、健康に過ごせますように」という願いを込め、悪いものを追い出すための行事とされてきたのです。
その道具として扱われてきた節分飾りも、いまや柊鰯だけではありません。
最近では、鬼の人形やお面、豆ますといった節分がモチーフの雑貨も、季節感を楽しむために飾られています。
そこで、さまざまある現代の節分飾りをまとめてみました。
| 節分飾り | 飾りについての詳細 |
|---|---|
| 柊鰯 | 柊の葉に、焼いたイワシの頭を刺したもの。臭いとトゲで鬼を追い払うという意味をもつ。地域によって、作り方に違いがある。 |
| 柊 | 「トゲのある葉が鬼の目を刺す」とされ、魔除けの意味を持つ。主に、玄関飾りとして使われる。 |
| トベラ | 強い香りで、邪気を払うとされている。玄関飾りに使われる。 |
| 節分草 | 節分の時期に咲く、小さな花。魔除けの効果がある。準絶滅危惧種に指定されているため、自生するものを摘み取ることは避ける。自宅で育てる、もしくはモチーフにするのがおすすめ。 |
| 南天 | 「難を転じる」という縁起の良い語呂から、魔除けの植物として飾られる。また、鮮やかな赤い実は鬼が嫌う色と考えられている。家内に福を呼び込むという意味合いもあるとされる。 |
| その他の縁起の良い植物 | 梅は節分の時期に咲くため、季節の変わり目を迎えるという意味合いで飾られる。榊は、お清めや祈りのために使われる神聖な植物のため、節分飾りとしても使われている。 |
| 鬼の面・置物 | 鬼の面や、張り子などの置物のこと。季節を感じられるものが多く、とくに決まりはない。 |
| 和雑貨 | 手毬や和紙を使った飾り、福ますなど、日本らしさを感じる雑貨のこと。 |
いつからいつまで飾るのか
節分飾りをいつからいつまで飾るのかという風習は、地域によって違います。
一般的には、正月行事が一段落する1月15日(小正月)から飾り、節分当日、もしくは2月4日頃(立春)に片づけます。
ほかには、以下のような期間があります。
- 2月3日(当日のみ)
- 2月3日~2月の終わりまで
- 2月3日~翌年の節分まで
生まれ育った地域の慣習に倣う、あるいは今お住まいの地域のやり方を取り入れるというのがいいでしょう。
節分飾りキットにはどのようなものがあるの?


節分飾りキットには、どのようなものがあるのかが気になります。
安心してキット選びができるよう、種類や特徴、さらにはキットを使うメリットとデメリット、選ぶときのコツをまとめました。
節分飾りキットの種類と特徴
節分飾りキットには、ガーランド、壁飾り、置物などがあります。
ここでは、上記の3つについてご紹介します。
ガーランド
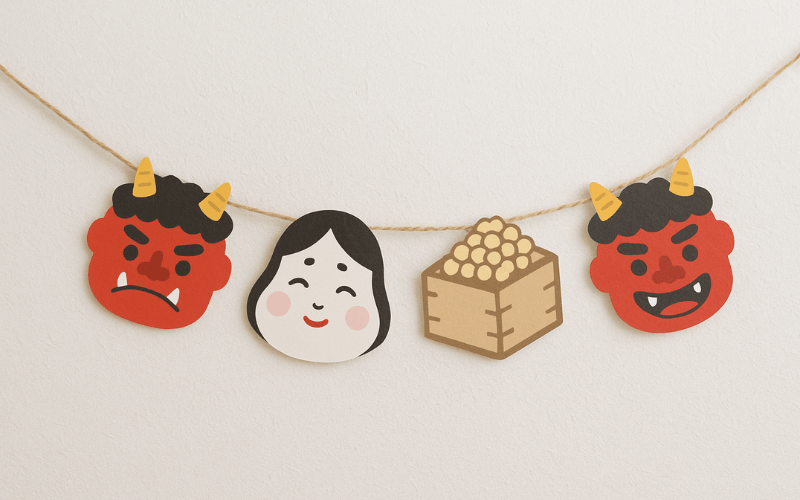
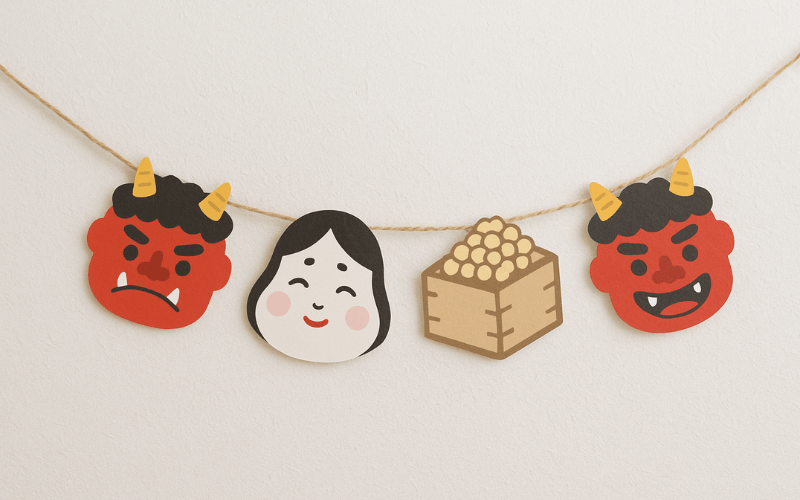
ガーランドとは、モチーフを使って作られた紐状の飾りのことです。
紙やフェルトを主に使います。
平面的なものは、わりと簡単で取り組みやすいでしょう。
壁飾り


壁飾りには、伝統的な柊鰯があります。
もし、本物の鰯を使って柊鰯を作るときには、状態が悪くなっていないか気にかける必要があるでしょう。
このほかにも、節分を思わせるモチーフで作られたものを最近はさまざま目にするようになりました。
飾る際、場所をとらないことがメリットです。
置物


立体的な仕上がりになるものが多いです。
具体的には、和紙や布を使った雑貨などがあります。
豆ますや毬を添えて飾り付けると、さらに季節感と日本らしさを演出することができるでしょう。
キットを使うメリット・デメリット
購入したあと悔やむことがないように、キットを使うメリットとデメリットを確認します。
- 道具の準備をする必要がほとんどないため、手軽に始められる
- 完成品のイメージをあらかじめ確認することができるため、失敗が少ない
- できあがりの質が安定しているため、安心
- 思い通りの仕上がりにならないこともある
- 内容によっては、想像以上に手間と時間がかかってしまうことも
キットを選ぶときのヒント
失敗しないキット選びのヒントは、3つあります。
失敗しないキット選びのヒント
- 購入前に、キットのなかに必要な材料がどの程度揃っているのかを確認する
- キットを使うことが初めてのときは、材料や工程が少ないものを選ぶ
- 自分で型を作る必要のないものを選ぶ
いざ始めようとしたときに道具が足りないと、一気にやる気を削がれます。
すでに家にあるものを使って作り始めることができるのか、確認してから購入するのがおすすめです。
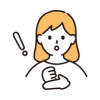
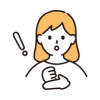
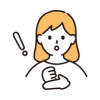
もし道具が足りないには、事前に買い足しておかなければいけませんね!
また、初めてキットを使うときには作業が簡単なものや、すでに型紙があったり、切り取り線が書かれているものを選ぶと、できあがりまで安心です。
節分飾りキットの基本的な使い方と子どもとの楽しみ方


節分飾りキットを購入し、手元に届いたあと、どのような手順で進めたら良いのかを確認します。
子どもと楽しく作るためのアイディアも、まとめました。
開封から飾りつけまでの手順
購入した節分飾りキットが届いたら、以下の手順で進めます。
まずはじめに、届いたキットのなかにすべてのパーツが揃っているのかを確認します。
説明書の記載を見ながら、「なにが何個あるか」を数え、種類ごとにわけておくと作る工程がはかどります。
パーツの確認を終えたら、作業に入る前に、一度すべての工程を読んでおきます。
はじまりから終わりまでの流れを理解しておくと、子どもと作るときの見通しを立てやすくなるからです。
説明に沿って、ひとつずつ作業工程を進めます。
手順番号などの読み間違いに注意しながら、ゆっくりと焦らずに取り組むことが、成功の秘訣です。
完成した節分飾りを、適切な時期に飾り付けます。



キットの完成が近づくほどわくわくするのが、楽しみのひとつです。
また、忙しい日常の中にふと季節を感じられるような飾りがあることは、きっと家族の癒しになるでしょう。
子どもと一緒に楽しむアイディア
節分飾りキットを子どもといっしょに楽しむためには、子どもの年齢にあった作業が含まれているものを選ぶようにします。
そうすることで、役割分担がしやすくなるからです。
また、子どもの自由な発想を尊重してあげられると、さらに充実した時間を過ごすことができます。
キットの工程に沿っていれば、完成イメージから大きくそれることはないはず——。
楽しむための注意点は、はさみやカッター、ホッチキスなどの扱い方です。
刃物類を使うときには目を離さないことや、使い終わった道具をあちこちに置かないよう気にかけます。
ケガなく終えられるよう、最後まで安全面への配慮を充分にする必要があるでしょう。
できあがった節分飾りと記念撮影などができると、家族のすてきな思い出になること間違いなしです。
「できあがった節分飾りはどこに飾る?」場所別アイディア


できあがった節分飾りは、家のどこに飾り付けたらいいのでしょうか。
伝統的なこと、現代の事情などありますが、大切なことはどのような想いを込めて飾るのかということです。
ぜひ、想像を膨らませてみてください。
玄関に飾るなら季節感を
節分飾りの本来の意味は、「魔除け」です。
そのため、いちばん効果的なのは「玄関の外」とされてきました。
しかし、時代と共に住宅事情が変わり、現代では「玄関の中」に飾るのが一般的になっています。
いずれにせよ、玄関は家の顔。
季節感のある節分飾りがあることで、家族だけではなく来客にも楽しんでもらうことができる、あたたかな「おもてなし」になります。
季節感を出すことに最適なのは、植物です。
ぜひ、柊や南天、梅などを、できあがった節分飾りに添えてみてください。
リビングに飾るなら華やかさを
家の中でもっとも広いリビングに飾るのであれば、華やかさを意識するというのはいかがでしょう。
飾り棚や壁を使って、子どもと作った節分飾りを置き、さらにデコレーションするのもおすすめです。
子どものいる賑やかさは、今しか味わうことができません。
家族が集まる場所に飾ることで、一緒に眺められる貴重な時間を噛みしめたいものです。
ダイニングやキッチンで楽しむなら小ぶりにして
ダイニングやキッチンに飾るのであれば、食卓になじむ小ぶりな節分飾りを選んでみてください。
食べ物の思い出は、大人になっても深く記憶に残っているものです。
その大切な空間に、季節を感じられるものがあるということは、子どもの情操教育にも良いと思います。
さりげなく、かつ食卓に彩を添えてくれるような節分飾りを、ぜひダイニングやキッチンに。
節分飾りが役目を終えた後の片づけ方や活用方法


節分飾りは、役目を終えたらどのように片づけるのが良いのでしょうか。
「魔除け」ということもあり、正しい片付け方が気になります。
また、枯れずに残った季節の植物や節分後も使えそうな雑貨を活用する方法も、知りたいところです。



せっかく子どもと作ったものなので、来年も飾りたいのですが……保管するときのコツなどはありますか?
気になることを、ひとつずつ調べてみました。
- 節分飾りの片づけ方は?
- アレンジして再利用する方法は?
- 来年に向けて保管しておくときのコツも知りたい
節分飾りの片づけ方
魔除けの道具として飾られた柊鰯などは、以下の方法で片づけることが基本とされています。
参考:村松虚空蔵尊だより「節分は地域で違いがある!興味深い特色や風習とは?」
- 灰になるまで焼いて玄関前に盛る
- 玄関先に埋める
- 塩で清めてから半紙に包んで捨てる
- 神社でお焚き上げをしてもらう
このなかで最も手軽なのは、「塩で清めてから半紙に包んで捨てる」という方法です。
いちばん手軽な、「塩で清めてから半紙に包んで処分する」手順
半紙と、塩を用意します。
半紙がないときには、白い紙、もしくは新聞紙などでもかまいません。
紙の上に節分飾りを置き、清めの塩をかけ、包んだらおしまいです。
あとは、地域の決まりにそって処分しましょう。
「せっかく作ったのだから、もう少し楽しみたい」「残しておきたい」と思う方もいるかもしれません。
その場合、鬼のお面や、季節を感じさせるための紙、布、木などで作られた節分飾りは長く飾ることや保管しておくこともできます。
しかし、柊鰯の鰯部分(鰯の頭部)は生もののため、衛生面を考えて再利用は避けましょう。
アレンジして再利用する方法
お面や、季節の植物、手毬や和紙の花などは、節分後もアレンジして再利用することができます。
それぞれのアイディアを表にまとめました。
| アレンジ できるもの | アレンジ方法 |
|---|---|
| 鬼のお面 | 色を塗り直したり、毛糸で髪をつけたりして、別のイベントに活用する。 |
| お多福 | 福を招く縁起物として、さまざまな場面に使われることがあるお多福は、節分後もインテリアとして飾ることができる。お面であれば、イベントやお祭りにつけていくもの良し。 |
| 季節の 植物 | 傷みやすい鰯の部分を取り除き、柊の葉を新しい花と組み合わせて飾る。ドライフラワーにして、リースやスワッグの素材にすることもできる。ほかの植物も同様。 |
| その他の 飾り | 和雑貨として飾る。 |
来年に向けて保管しておくときのコツ
一般的には、毎年新しいものを準備するのが慣習です。
しかし、なかには来年も飾りたいと思うような思い出の深いものもあるでしょう。
そのようなときには、型崩れに注意して収納します。



収納箱は、節分飾りの大きさに合ったサイズで準備することをおすすめします。
あらかじめ、省スペースで保管できる節分飾りを選ぶというのもひとつです。



ほかにも、飾りを残しておくためのアイディアはありますか?
上記のほかには、写真に残して、翌年はその写真を飾るという方法があります。
子どもとの思い出を写真に残し、「あの頃」と「今」を飾って比べてみるというのも楽しいものです。
写真であれば、保存状態を気にすることも、保管場所に困ることもほとんどありません。
まとめ|節分飾りキットで手軽に行事を楽しもう
節分飾りキットを使うことで、忙しい日々のなかでも子どもと一緒に年中行事を楽しむことができます。
お手軽にできるものがあるのは、主婦にとって大変助かりますね。
- 節分飾りを作るための材料が一式揃った商品のこと
- ガーランド、壁飾り、置物などがある
- 作業工程や材料の少ないものを選ぶと、忙しいときや初めての場合も取り組みやすい
- 子どもと一緒に作るときは、作業工程を事前に確認してからキットを選ぶ
- キットが届いたら、まずは中身の確認をし、説明書に沿って焦らず作るのが成功の秘訣
- 工程の範囲内で子どもの自由な発想を取り入れることができると、さらに、仕上がりを楽しむことができる
- できあがった飾りは、玄関、リビング、ダイニングやキッチンに飾り付けることができる
- 役目を終えた節分飾りは、塩で清めて半紙に包んで捨てる、あるいは神社でお焚き上げするのが一般的
- 季節の植物や、お面などは、節分期間が明けた後もアレンジして使うことができる
- 来年も飾る場合は、型崩れしないようサイズの合った入れ物にしまうのがおすすめ
節分には、節分飾り以外にも伝統があります。
「恵方巻」で楽しもうとお考えの方には、こちらの記事もおすすめです。


最後までお読みいただき、ありがとうございます。

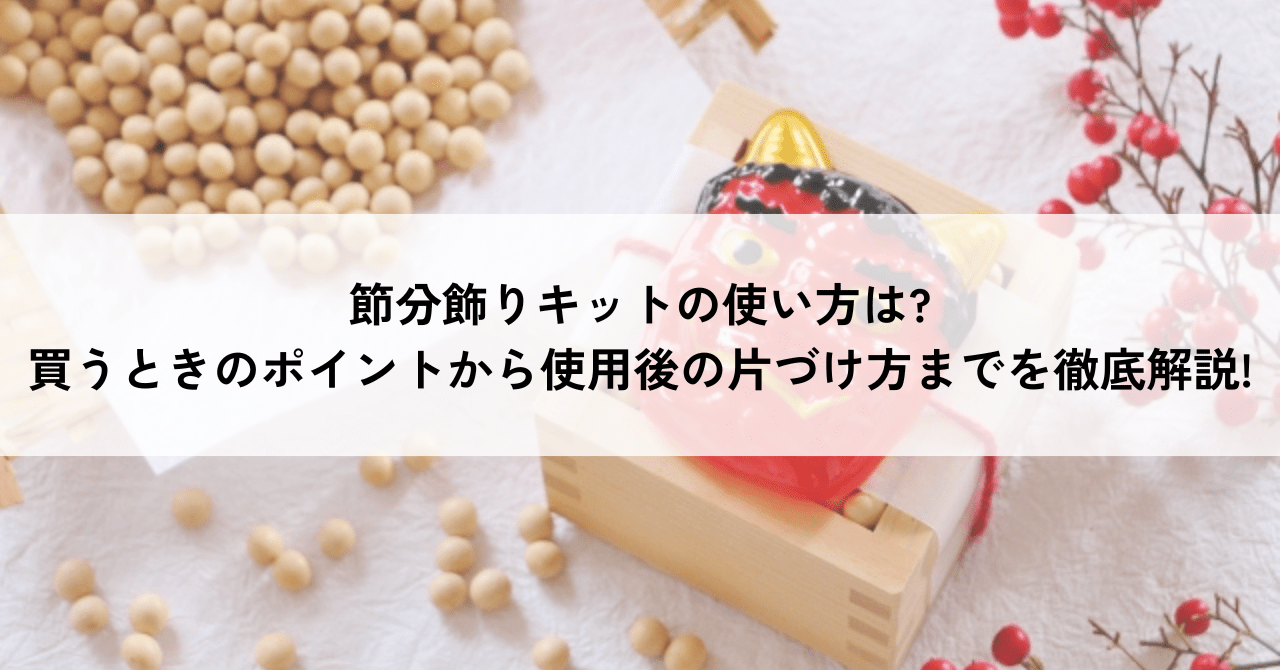
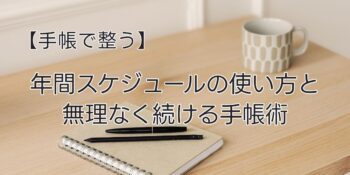
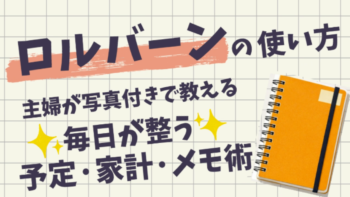


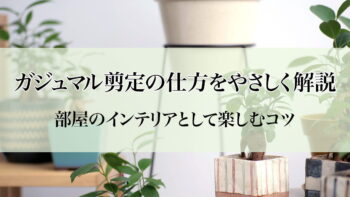



コメント