 読者様
読者様今年の節分はどんなお面にしよう…
そんな声が聞こえてくる季節がやってきましたね。
忙しい日々の中でも、安全で・手間がかからず・子どもが達成感を感じられる節分制作をしたいと感じる先生方も多いのではないでしょうか。



この記事では、保育歴15年以上の筆者が、年齢別の制作アイデアや準備のコツをお届けします。
子どもたちの「できた!」の笑顔が保護者や職員間の信頼にもつながる。
そんな制作活動をサポートします。
年齢別:子どもの「できた!」を育てる節分のお面づくり


節分制作は、年齢や発達段階に応じた工夫を取り入れることで、子どもたちが「自分で作れた!」という達成感が引き出され、制作時間がより意味あるものになります。
0〜2歳児向け:シンプルで安全な鬼のお面
0〜2歳児クラスでは、安全性と手軽さが第一。
紙皿や画用紙に目や口を貼るだけでも、目の前で少しずつ完成していく体験に子どもたちはワクワクします。
- 両面テープや大きめのシールを活用して貼る工程を簡単に
- 目の位置などを事前に薄く下描きしておくと、迷いなく制作に集中できる
完成したお面を手にすると、鏡を見てニコニコしたり、他の子と見せ合いっこをしたりする姿も。
小さな達成感が育つ、大切な工程です。
1歳児から楽しめる!ちぎり絵で作る鬼のお面(保育士バンク)
色紙をちぎって貼るだけなので、まだハサミが使えない年齢の子でも楽しめます。
👉 YouTubeで見る
出典:保育士バンク!公式チャンネル
年小・年中さん向け:自分で仕上げる喜びが味わえる工作
3〜4歳児になると、はさみやのりを使う工程も取り入れられるようになります。
輪郭を自分で切ったり、パーツを好きな場所に貼ったりすることで、「自分で仕上げた」という満足感が得られます。
- 色とりどりの折り紙や毛糸を使って髪の毛を表現
- パーツの貼り付け位置を好きなところに貼る
- 眉や牙などを自由に描き加える
お面の表情に個性が出て、完成後のやりとりにも花が咲きます。



制作中に「かっこいいね」「お面が似合ってるよ」と声をかけると、自信が育ちますよ。
制作中にポジティブな声かけをすることで、子どもたちが安心して表現できる環境になります。
特に「〜ができてるね」と具体的に伝えると効果的です。
年長さん向け:オリジナル性が出せるアレンジアイデア
5歳児になると、「こんなお面にしたい!」というイメージをもとに、自分なりに工夫しながら作ることができます。
完成イメージを共有しつつも、色や形、素材の選び方を自由にできるようにしておくと、創造性を存分に発揮できます。
- 牛乳パックをベースにした立体的なお面
- 金銀の折り紙で飾った“かっこいい鬼”
- あえて怖くない「にこにこ鬼」など、テーマを自由に決めてよい



完成後はクラスで「発表タイム」を設けると、表現する喜びが広がりますよ。
発表タイムを設けることで、作品に込めた想いや工夫を話す機会になります。
「自分の作品を人に見せよう」という意識にもつながり、達成感も高まります。
本格派!はりこで作る鬼のお面(KIDS SMILE LABO)
「ちょっと本格的な制作にチャレンジしてみたい」そんなときにぴったりな工作動画です。
新聞紙やのりを使った工程がわかりやすく紹介されており、子どもと一緒にじっくり取り組みたい方におすすめです♪
👉 YouTubeで見る
出典:KIDS SMILE LABO公式チャンネル
準備がラクになる素材選びと道具の工夫


節分の制作を楽しく行うには、準備のスムーズさも大切なポイントです。
ここでは、保育現場で使いやすく、安全でコスパも良い素材選びや道具の工夫をご紹介します。
安全・見映え・コスパも叶う素材選び
子どもが扱いやすく、見た目も可愛く、さらにコストも抑えられる素材として人気なのは、以下のようなアイテムです。
- 紙皿:丈夫で加工しやすく、輪郭を描きやすい。お面の土台としてぴったり。
- 画用紙・折り紙:色を自由に選べて、細かいパーツづくりにも最適。
- 毛糸やモール:髪の毛や眉毛、角の装飾にアクセントを加えられる。
- カラービニールテープ・マスキングテープ:貼り直しができて安全、色のアクセントにも。



100円ショップなどで揃うアイテムが多いため、低コストで多人数分の準備がしやすいのも魅力ですよね。
保育園で使いやすい道具&保管方法(紙皿・折り紙・布など)
使用する道具も、安全性と扱いやすさを意識して選ぶと、制作時のトラブルを減らせます。
- 両面テープやのり(スティックタイプ):乾きやすく、扱いやすい。
- 子ども用はさみ:握りやすさや刃の安全性を考慮したものを。
- ラミネート素材の下敷き:作業スペースが汚れにくく、管理がしやすい。



完成品やパーツを保管する際は、
以下のような方法を取り入れると整理がラクになりますよ。
- ジップ付き袋:細かいパーツもまとめやすく、湿気対策にも◎。
- A4封筒:下書きや薄い素材の保管に便利。
- 引き出し式ケース:ラベルを貼れば、年齢別・素材別に整理しやすい。
- ポリプロピレン製の書類ケース:中身が見えるタイプは一目で分かりやすい。
- チャック付きクリアファイル:薄手のパーツや下書きをまとめて保管可能。
- 仕切り付きボックス(100均など):色別・サイズ別に小物を整理できる。
テンプレートや下書き・下書き活用で準備もスムーズ
忙しい中で1からすべて準備するのは大変。
そんなときは、下絵やテンプレートを事前に用意しておくことで時短につながります。
- 顔の輪郭だけ描いたテンプレート
- 「角・目・口・眉」などのパーツ見本
- 子どもが選べるようにいくつかの表情バリエーションを用意
無料でダウンロードできるお面の素材を配布しているサイトもあります。
行事前に探しておくと、制作がぐっと楽になりますよ。



事前準備を少し工夫するだけで、「選ぶ→貼る→完成!」というスムーズな流れが作れますね。
節分のお面づくりを「行事」で終わらせないために





節分のお面づくりは、子どもの自信や達成感を育む大切な時間です。
ここでは、制作の意味づけや関わり方の工夫を通じて、行事を“心に残る体験”へと育てていくヒントをご紹介します。
単なる「行事の一環」ではなく、制作を通して子どもが自己表現できるように意識しましょう。
その経験は、園生活や家庭でも生きてきます。
子どもが主体的に取り組める関わり方
「どんな顔にしたい?」「ここに角をつけたらどうかな?」そんな問いかけを通じて、子ども自身が考え、選び、工夫していくプロセスを大切にしましょう。
たとえば、
- 完成見本はあえて複数にして「選べる」状態にしておく
- 正解を押しつけず、「どうしたい?」と聞いてみる
- 素材を自由に組み合わせられるように並べておく



小さな工夫で、子どもたちの主体性が引き出されやすくなります。
制作を通して“できたね”と共感できる声かけのコツ
完成したお面を見せてくれたときは、形の出来ばえよりも「気づき」や「工夫」に注目して声をかけてみましょう。
- 「自分で目の場所、決めたんだね」
- 「この色、どうして選んだの?」
- 「ここ、切るのがむずかしかったけど、がんばったね」
こうした言葉かけが、子どもの“できた”を深く根づかせる体験になります。
また、制作途中でも「楽しんでるね」「工夫してるね」と声をかけることで、過程そのものに価値が生まれます。
保護者・職員間の信頼にもつながる共有アイデア
完成したお面は、子どもたちにとっても保護者にとっても大切な成長の証。
制作中の様子や出来上がりを、次のような形で共有してみましょう。
- クラスだよりで写真付き紹介
- 廊下掲示や玄関ボードで展示
- 作品に添えて「○○ちゃんの工夫ポイント」を紹介
こうした工夫は、保護者が子どもの成長を実感する機会になると同時に、「先生が丁寧に関わってくれている」という安心感にもつながります。



職員同士でも制作アイデアを共有することで、チームとしての一体感も育っていきます。
まとめとワンポイントアドバイス
節分のお面づくりは、季節の行事を通して子どもの達成感や創造力を育む、貴重な時間です。
この記事では、素材や工程の工夫、声かけや発表の方法など、子どもの成長を支えながら保護者や同僚との関係も深められるアイデアを紹介してきました。
これらの工夫を取り入れることで、子ども目線の楽しさが行事全体に広がり、次の行事づくりにもつながります。



先生自身が安心して進められて、
笑顔の「鬼さん」がたくさん生まれますように。
ぜひ園での行事づくりに活かしてくださいね。
節分ってどんな日?飾りの意味や、子どもと一緒に楽しめる飾りアイデアをまとめた記事もあります♪


材料選びのコツや、安全に作るポイント、完成後の楽しみ方まで。節分をもっと楽しめる「鬼のお面づくり」を紹介しています!


最後までお読みいただきありがとうございました。




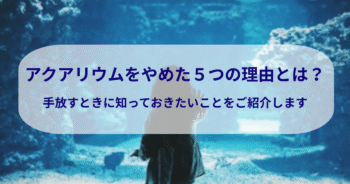

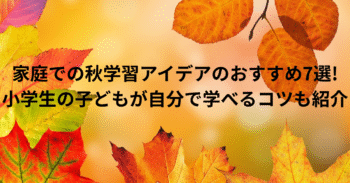
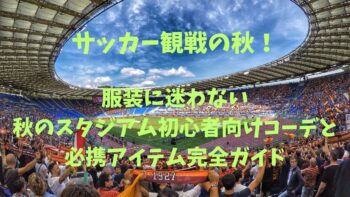
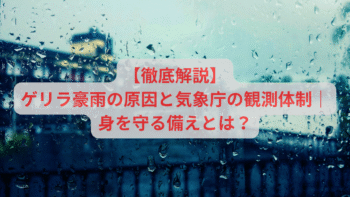
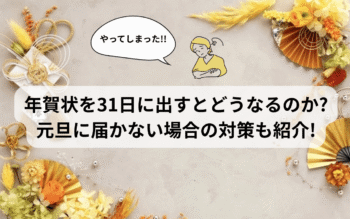
コメント