 読者様
読者様寒中見舞いのはがきって、いつまでに出せばいいの?
書き方もわからないし、失礼にならないか不安…



安心してください!
基本を押さえれば寒中見舞いを出すのは難しくありませんよ!
寒中見舞いのはがきは、一般的に1月7日(松の内)を過ぎてから立春(2月4日頃)までに送るのがマナーとされています。
ただし、喪中の方への挨拶として出す場合や、地域によって違いがあることも。
基本的なルールを押さえて、失礼のないタイミングで送りましょう。
この記事では、寒中見舞いについて初心者にもわかりやすく解説しています。
- 寒中見舞いの基本的なマナー
- 寒中見舞いの書き方やはがきの選び方
- シーン別の文例
これを読めば、寒中見舞いを適切なタイミングで送り、自信を持ってマナーを守ることができます。
ぜひ最後までご覧ください!
寒中見舞いとは?その意味と役割


「寒中見舞い」とは、日本の季節の挨拶状のひとつで、主に 寒さの厳しい時期に相手の健康を気遣うために送られます。
最近では、年賀状を送りそびれた際の代替手段や喪中の方への新年の挨拶としても活用されています。
年賀状を出せないときでも、寒中見舞いなら相手に失礼なく気持ちを伝えられますよ。
寒中見舞いのはがきはいつまでだせる?


寒中見舞いは、いつからいつまでの期間に送るのが適切なのか気になりますよね。
基本的な受付期間や遅れてしまった場合の対応まで、詳しく解説していきます。
寒中見舞いの受付期間はいつからいつまで?
寒中見舞いを送る適切な期間は「松の内が明けた1月8日から、立春(2月4日頃)まで」です。
これは一般的なルールで、地域によって松の内の期間が異なります。
| 地域 | 松の内の期間 | 寒中見舞いを送る時期 |
| 関東 | 1月7日まで | 1月8日~2月4日 |
| 関西 | 1月15日まで | 1月16日~2月4日 |



寒中見舞いを送る際は、相手の住んでいる地域の習慣も考慮しましょう!
最適な投函タイミングとは?
寒中見舞いは、相手にとって負担にならず、自然に受け取れる時期に送るのが理想的です。
- 1月8日~1月15日:年賀状の返事として送るのに適した時期
- 1月16日~1月31日:一般的な寒中見舞いとして最適な時期
- 2月1日~2月4日:ギリギリのタイミング。遅れすぎないよう注意
できるだけ1月中には投函し、相手に気持ちよく受け取ってもらえるようにしましょう。
2月5日以降はどうする?
2月5日になると立春を過ぎているため、「余寒見舞い」を送ることができます。
余寒見舞いは、寒中見舞いと同じく相手の健康を気遣う内容ですが、送る時期が異なります。
余寒見舞いは2月いっぱいまで送ることが可能です。
余裕をもって、できるだけ2月中旬までに届くように投函するようにしましょう。
寒中見舞いの書き方とポイント


寒中見舞いは、文面のマナーに気をつける必要があります。
誤った書き方をすると、相手に失礼になってしまうこともあるので注意しましょう。
また、縦書きと横書きの正式な決まりはありません。
横書きの方がカジュアルなイメージになるので、送る相手によって使い分けが必要です。
寒中見舞いの基本構成
寒中見舞いの文章は、次の5つの要素で構成されます。
- 季節の挨拶
- 相手の健康を気遣う言葉
- 近況報告や伝えたいこと、お礼の言葉
- 締めの挨拶、今後の健康や幸せを願う言葉
- 日付



この構成をもとに、送る相手に合わせて文章を変えていきましょう。
▼基本の文例
寒中お見舞い申し上げます。
厳しい寒さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
旧年中は大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
どうかお体にお気をつけて、温かくお過ごしください。
令和〇年〇月
宛名の書き方
文章と宛名の向き(縦書きまたは横書き)は合わせましょう。
縦書きの場合は漢数字、横書きの場合は算用数字を使用します。
夫婦や複数人の家族に送る場合は世帯主の名前を最初に書き、2人目以降は苗字なしで名前のみ並べます。
その場合は全員に「様」をつけましょう。
人数が多い場合は世帯主の名前のみ記載し、その横に「御家族御一同様」とまとめることもできます。
- 個人宛の場合:「様」を使用
- 会社宛の場合:「御中」を使用(例:〇〇株式会社 御中)
- ビジネス関係の個人宛の場合:「様」を使用(例:〇〇会社 営業部 部長 〇〇様)
避けるべき表現・注意点
寒中見舞いは、日頃の感謝を伝えるだけでなく、喪中の方への配慮としても使われる挨拶状です。
そのため、寒中見舞いでは不適切な表現を避けることが大切です。
- 賀詞(「新年おめでとうございます」「謹賀新年」など)
- お祝いの言葉(「おめでたい」「祝う」など)
- 宗教色の強い表現(「成仏」「天国で安らかに」など)
- 自分の近況報告やポジティブすぎる内容



年賀状と混同しないように気をつけましょう!
寒中見舞いの文例集
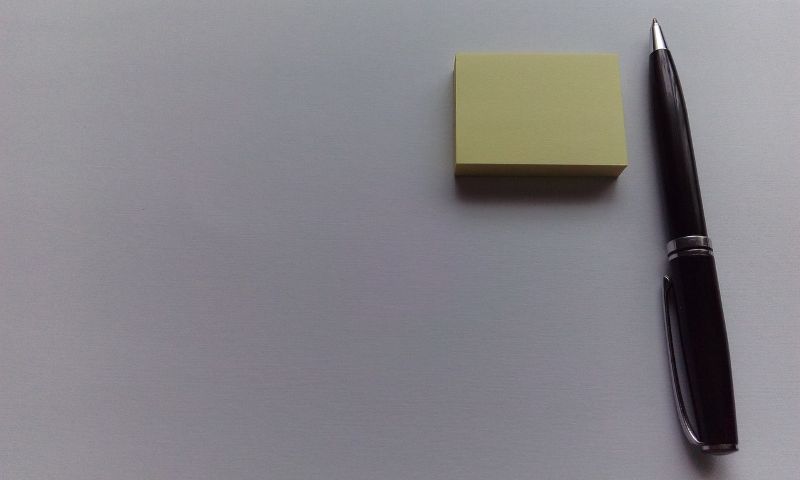
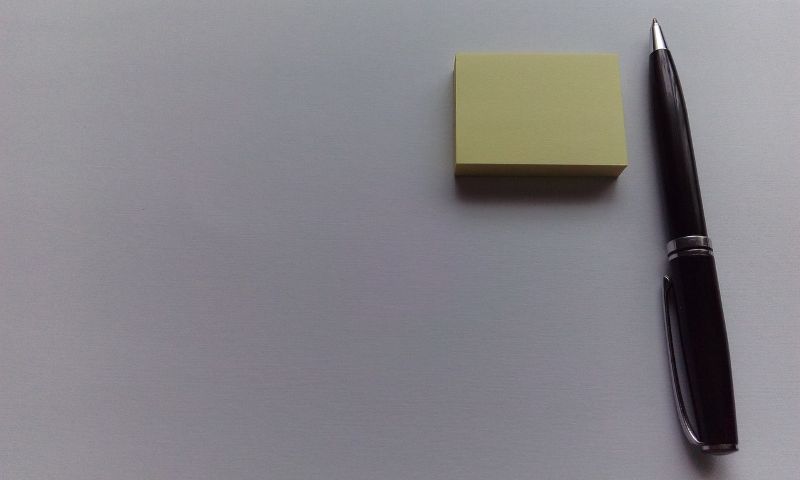
寒中見舞いの文章は、送る相手によって表現を変えましょう。
ここでは、「友人・親戚など一般向け」「ビジネス関係」「喪中の方」など、シーン別の文例をご紹介します。
友人・親戚など一般向けの文例
家族や親しい友人には、温かみのある言葉を添えましょう。
▼カジュアル(親しい友人向け)
寒中お見舞い申し上げます。
今年の冬は特に寒いですが、元気に過ごしていますか?
まだまだ寒い日が続くので、体調に気をつけてくださいね!
また落ち着いたら会えるのを楽しみにしています。
令和○年○月
▼フォーマル(親戚向け)
寒中お見舞い申し上げます。
ご家族の皆様におかれましては、お元気でお過ごしでしょうか。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
まだ寒い日が続きますので、くれぐれもご自愛くださいませ。
令和○年○月
▼送られてきた年賀状への返事(喪中ではない場合)
寒中お見舞い申し上げます。
皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしとのこと、心よりお喜び申し上げます。
丁寧な年賀状をいただきながら、ご挨拶が遅れまして大変失礼いたしました。
おかげさまで家族一同、元気に暮らしております。
今年も変わらぬお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。
令和○年○月



親しい間柄であれば、自身の近況報告を盛り込んで作成するのもおすすめです。
ビジネス関係の相手への文例
取引先や上司に送る場合は、フォーマルな表現を意識しましょう。
また、「お世話になった感謝」も明確に伝えましょう。
▼ビジネス向け全般
寒中お見舞い申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
本年も変わらぬご厚情を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
令和○年○月
▼取引先向け
寒中お見舞い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心より感謝申し上げます。
貴社のますますのご発展と皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
本年も変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和○年○月
▼上司・先輩向け
寒中お見舞い申し上げます。
旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
今年もより一層精進してまいりますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
まだまだ寒い日が続きますので、ご自愛ください。
令和○年○月



上司や先輩に対しては今年の抱負を添えると印象がアップしますよ。
喪中の方宛て、自身が喪中の場合の文例
喪中の方には、控えめで落ち着いた表現を使いましょう。
▼喪中の方へ送る場合
寒中お見舞い申し上げます。
ご服喪中と伺い、年頭のご挨拶を控えさせていただきました。
寒さ厳しき折、ご自愛くださいますようお祈り申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
令和○年○月
▼喪中はがきの返事
寒中お見舞い申し上げます。
ご服喪中と伺い、年頭のご挨拶を控えさせていただきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
この度の〇〇様のご他界を知り大変驚いておりますとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
寒さが一段と厳しくなります節柄、風邪などお召しになられませんようご自愛ください。
令和○年○月
▼喪中の際に送られてきた年賀状への返事
寒中お見舞い申し上げます。
ご丁寧なお年始状をいただきありがとうございました。
昨年〇月に〇〇が永眠し、年始のご挨拶を控えさせていただきました。
ご連絡が行き届かず、誠に失礼いたしました。
今年も変わらぬお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。
令和○年○月



喪中の方へ送るときは、相手を気遣う内容を心がけましょう。
寒中見舞いのデザインと選び方


寒中見舞いのはがきは、送る相手や目的に応じて適切なものを選ぶことが重要です。
ここでは、寒中見舞いに適したはがきの選び方やデザインの基本について解説します。
はがきの選び方
寒中見舞いを送る際は、はがきの種類にも注意が必要です。
年賀状と間違われないよう、通常のはがきを選びましょう。
- 官製はがき(切手が印刷されているもの)
- 私製はがき(切手を貼るタイプ)
- 寒中見舞い用のはがき
- 年賀はがき(お年玉付き年賀状は使用不可)



年賀状が余っていても使わないように注意しましょう!
寒中見舞いのデザインの基本
寒中見舞いのデザインは、落ち着いた雰囲気が一般的です。
年賀状とは異なり、華やかすぎないシンプルなデザインにしましょう。
寒中見舞いに適したデザイン
- 寒さを連想させる冬の風景(雪景色、富士山、梅の花など)
- 落ち着いた色合い(淡いブルー、グレー、ホワイトなど)
- シンプルな和柄や模様(水引、竹、波紋など)
避けるべきデザイン
- 干支や「おめでとう」などの賀詞を含むもの
- 派手すぎる色
- ポップなイラストやキャラクター(親しい友人向け以外では避ける)
寒中見舞いで心温まるご挨拶を
「寒中見舞い」とは、寒い時期に相手の健康を気遣うために送る季節の挨拶状です。
1月8日(松の内後)から2月4日頃(立春)までに出しましょう。
喪中の人へ年賀状の代わりとして送ることもできます。
立春を過ぎた場合は「余寒見舞い」として送りましょう。
寒中見舞いの書き方にはマナーがありますが、基本的な構造と注意点を守れば、誰でも失礼のない文章を書くことができます。
基本の書き方
- 季節の挨拶(寒中お見舞い申し上げます)
- 相手の健康を気遣う言葉(厳しい寒さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか)
- 近況報告やお礼の言葉(旧年中は大変お世話になり、心より感謝申し上げます)
- 締めの挨拶、今後の健康や幸せを願う言葉(本年もどうぞよろしくお願いいたします)
- 日付(令和〇年〇月)
寒中見舞いには、年賀状とは異なるポイントがあるので注意しましょう。
- 賀詞(「新年おめでとうございます」「謹賀新年」など)や「おめでたい」などのお祝いの言葉は避ける
- 年賀状は使わず、通常の郵便はがきや私製はがきを使用する
- 落ち着いた雰囲気のシンプルなデザインを選ぶ
心のこもった新年の挨拶で、良い1年をスタートさせましょう!
この記事が少しでも皆様の参考になることを願っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。

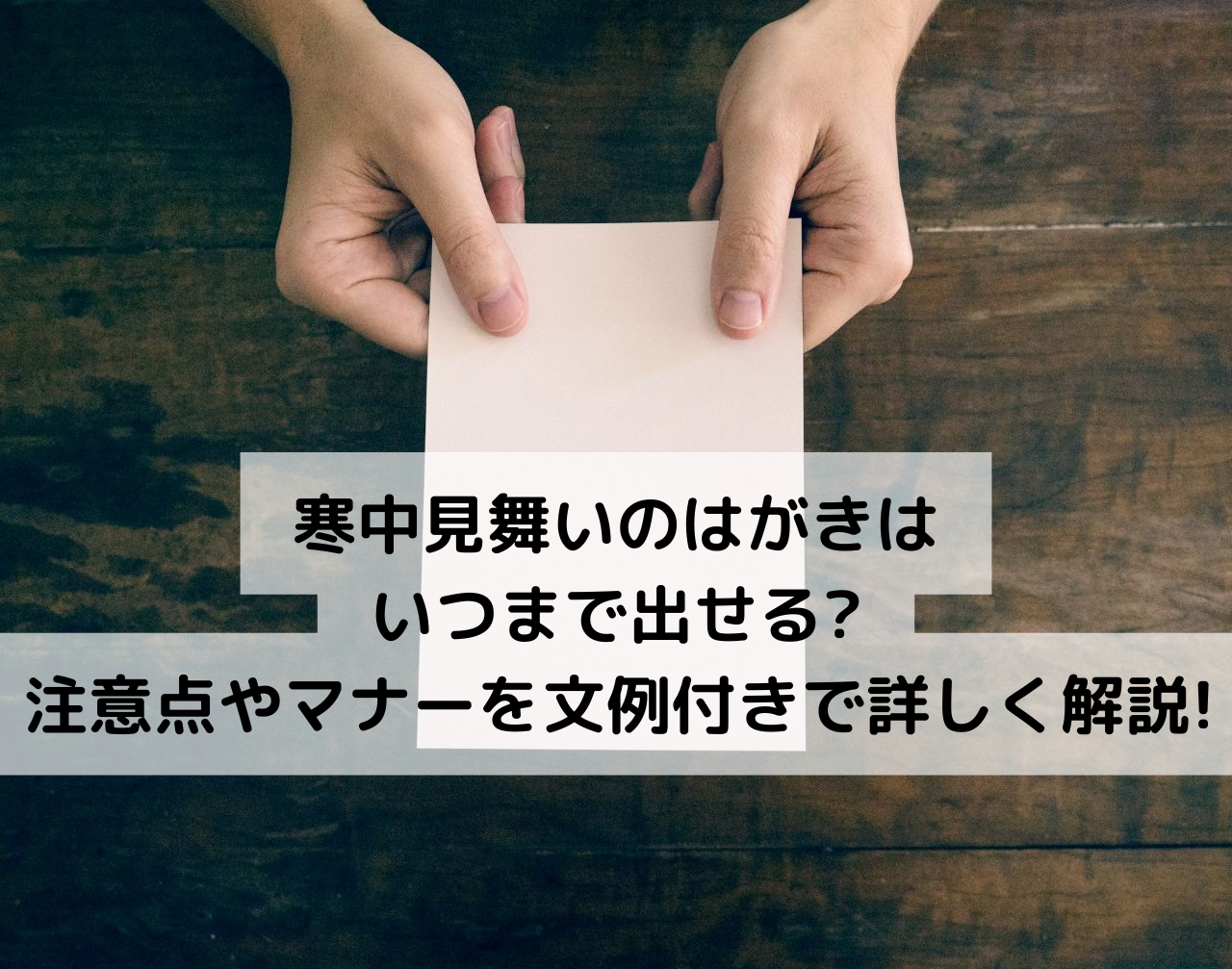

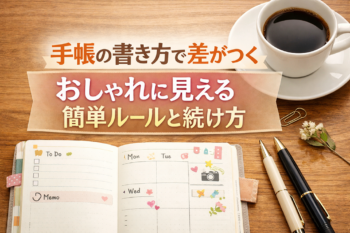
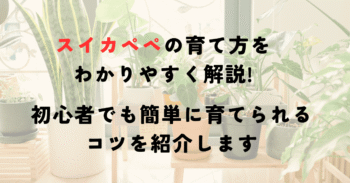
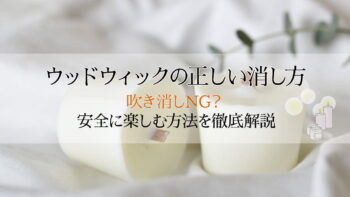
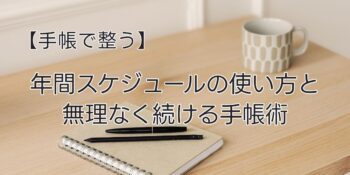
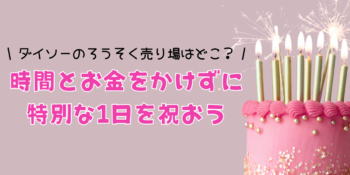
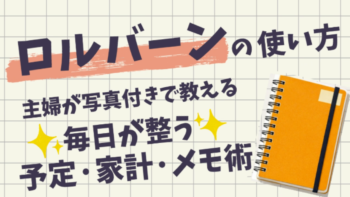
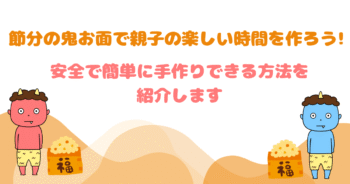
コメント