 読者さま
読者さま最近、親の体力が落ちてきたなと感じています。
このまま年を取って寝たきりになったらどうしよう⁉



寝たきりになったらと思うと介護のことも心配ですよね。
少しでも長く元気でいてもらうために、ロコモ予防について知っていきましょう。
加齢や病気、ケガなどが原因で運動器の障害がおこり、移動機能が低下した状態のことをロコモティブシンドローム(運動器症候群)といいます。
高齢になれば身体が動かなくなるのは仕方のないこと、と諦めていませんか。
動けない人の介護をすることは、介護する側にとって重労働なだけでなく、介護される方も申し訳なさや悔しさなどを感じているのではないでしょうか。
双方の負担を軽くするためにも健康寿命を延ばし、少しでも長い時間自力で身体を動かせるようにしておくことがとても重要です。
この記事ではロコモティブシンドロームを予防して、健康寿命を延ばす方法をご紹介します。
高齢者はもちろん、若いうちからの予防も効果がありますよ。
元気な老後を送るために、今からロコモ予防を始めましょう。
・ロコチェックで身体の状態を知る
・ロコトレで親世代も自分もロコモ予防する
・ロコモ予防に必要な栄養
ロコモティブシンドロームを知ろう


高齢になると筋肉や骨が弱くなって、動作がゆっくりになり、あまり動けないというイメージがありますよね。
骨密度が減ると骨折しやすくなり、動かないことにより筋肉が減ってしまいます。
筋肉が減ると動くことが困難になります。
負のスパイラルでだんだん動けなくなってしまう前にロコモティブシンドロームを予防しましょう。
ロコモティブシンドロームとは
ロコモティブシンドローム(運動器症候群)は平成19年に日本整形外科学会により提唱されました。
加齢や病気、ケガなどが原因で筋肉、骨、関節の障害がおこり、移動機能が低下した状態のことです。
ロコモが進行するとどうなるの?
高齢になると、歩くのが遅くなったり、立っているのが辛くなったりと、どうしても動く量が減ってしまいますね。
動く量が減ると筋肉が減ってしまいます。
また、加齢による骨密度の低下により骨折しやすくなったり関節が動かしにくくなったりすると、ますます動かしにくくなり筋肉が減っていきます。
このように負のスパイラルが起こると弱い身体になっていき、寝たきりになるリスクが高まります。
ロコモが良くなることはあるの?
ロコモティブシンドロームになってしまっても、筋肉を増やすことや骨密度をあげることは可能です。
少しでも健康で動けるうちから予防しましょう。
簡単なロコモ体操を続け、毎日の食事で筋肉や骨に大切な栄養を適切に摂りましょう。
いつまでも動ける身体になることが目標です。
少しずつでも続けていくことで健康寿命を延ばすことができます。
ロコモティブシンドロームのチェックをしよう


まずは身体の状態を知りましょう。
もしかしてロコモかも、を知りたい時は7つの項目の「ロコチェック」で確かめましょう。
当てはまることが何個あるのかをチェックします。
ロコモがどのくらい進行しているのかを知りたい時は「ロコモ度テスト」をしましょう。
ロコモ度は3段階で判断します。
ロコモ度1:移動機能の低下が始まっている状態
ロコモ度2:移動機能の低下が進行している状態
ロコモ度3:移動機能の低下が進行し、社会参加に支障をきたしている状態
ロコチェックをしてみよう
ロコチェックの項目は、骨、関節、筋肉などの運動器が衰えているサインです。
1.片脚立ちで靴下がはけない
2.家の中でつまづいたりすべったりする
3.階段を上がるのに手すりが必要である
4,家のやや重い仕事が困難である(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)
5.2kg程度の買い物をして持ち帰ることが困難である。(1リットルの牛乳パック2個程度)
6.15分くらい続けて歩くことができない
7.横断歩道を青信号で渡りきれない
ひとつでも当てはまればロコモになっている可能性があります。
ロコモ度テストをしてみよう
ロコモ度テストは3つです。
親世代のテストをする際は必ず付き添って、無理のないようにしましょう。
準備運動をしてからおこなってください。
・立ち上がりテスト(下肢筋力を調べる)…40センチの高さの椅子から、手を使わずに立ち上がります。
・ツーステップテスト(歩幅を調べる)…大股で2歩、歩幅を調べ、歩行能力を評価します。
・ロコモ25テスト(体の状態、生活状況を調べる)…25問の質問に答えます。
チェックをして出た「ロコモ度が一番高い数字」があなたのロコモ度です。
「ロコモONLINE」で詳しいチェックができますので、ぜひご覧ください。
ロコモティブシンドロームを予防する運動「ロコトレ」


ロコモ度がわかったら、さっそくロコトレを始めます。
簡単なことから始めて、無理なく続けましょう。
ロコトレの方法
ロコトレの基本は2つの運動です。
バランス能力をつける「片脚立ち」と、下肢筋力をつける「スクワット」です。
「片脚立ち」は片脚1分間ずつ立ちます。転倒しないように必ずつかまるものがある場所で行いましょう。
左右とも1分間で1セットを1日3セット行います。
「スクワット」は足を肩幅に広げて立ちます。
お尻を後ろに引くように2~3秒間かけてゆっくりと膝を曲げ、ゆっくり元に戻ります。
スクワットができない場合は、イスに腰かけ、机に手をついて立ち上がりの動作を繰り返します。
5~6回1セットを1日3セット行います。
基本の2つにプラスして、ふくらはぎの筋力をつける「ヒールレイズ」と、下肢の柔軟性、バランス能力、筋力をつける「フロントランジ」を行うと、より効果的です。
「ヒールレイズ」は両足で立った状態で踵を上げて、ゆっくり踵を降ろします。
自信のある人は、壁などに手をついて片脚だけでも行ってみましょう。
立位や歩行が不安定な人は、イスの背もたれなどに手をついて行いましょう。
10~20回を1日2~3セット行います。
「フロントランジ」は腰に両手をついて両脚で立ち、脚をゆっくり大きく前に踏み出します。
太ももが水平になるくらいに腰を深く下げます。
身体を上げて、踏み出した脚を元に戻します。
5~10回を1日2~3セット行います。
こちらの動画もぜひ参考にしてください。
ロコトレを親世代に勧めよう
すぐにでもロコトレを始めてもらって、元気でいてほしい親世代。
長く続けるコツとしては、ロコトレを前向きに楽しんでもらうことが一番ですよね。
しかし、高齢の方の中には無気力になっている方、「面倒だから」とやりたがらない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「高齢だから動けなくて当たり前」と考えていたり、「動かすと痛い」と言いづらくて「やりたくない」と拒否してしまう方もいらっしゃるでしょう。
消極的な方には無理に勧めることなく、気持ちに寄り添って少しづつでも声をかけ続けましょう。
思ったように動けずプライドが傷ついている方にも、さり気なく運動の良さを伝えるなど根気よく声をかけ続けることをお勧めします。
「あなたの身体の事を考えて言ってるのに……。」と、思いが伝わらないとイライラしてしまうこともありますよね。
体調が悪い日、気分が乗らない日など出来ない日があっても構いません。
お互いに楽しみながら動けるように一緒にロコトレをしていきましょう。
痛みがある方は早めに受診することもロコモ予防になります。
40代から始める予防の運動
ロコチェックに全く問題のない方も、今のうちから運動習慣をつけることが大切です。
親世代にロコモ体操を促しながら一緒に動くことは自分のためにもなります。
自分が長く楽しめる趣味のスポーツを見つけるのもいいかもしれません。
パートナーや友達とのコミュニケーションとしてスポーツを楽しんでもいいですね。
目標は健康寿命を延ばすことなので、無理なく長く続けられそうなスポーツを色々試してみましょう。
まずはスポーツジムの無料体験や、地区センターなどで行われる教室に参加して探てみてはいかがでしょうか。
ロコモティブシンドローム予防には食事も大切


筋肉や骨を作っているのは栄養です。
毎日の食事でロコモティブシンドロームを予防しましょう。
ロコモ予防に効く食べ物
骨や筋肉を作る食べ物は「さあにぎやか(に)いただく」の10の頭文字の食品です。
たんぱく質、カルシウム、ビタミンD、ビタミンKをしっかり摂りましょう。
| 頭文字 | 食品名 | 栄養、効果 |
| さ | 魚 | 動物性たんぱく質やカルシウム、ビタミンDが豊富 |
| あ | 油 | 適度な油脂分は細胞などを作るのに必要 |
| に | 肉 | 良質なたんぱく源の代表 |
| ぎ | 牛乳 | たんぱく質とカルシウムが豊富 |
| や | 野菜 | ビタミンや食物繊維を充分に摂れる |
| か(に) | 海藻 | 低エネルギーでもミネラルと食物繊維が豊富 |
| い | 芋 | 糖質でエネルギー補給。ビタミン、ミネラルも含む |
| た | 卵 | いろいろな調理法で簡単にたんぱく質が摂れる |
| だ | 大豆 | たんぱく質の素になる必須アミノ酸やカルシウムも豊富 |
| く | 果物 | ミネラル、ビタミンが多く食物繊維もとれる |
毎日の食事で7点以上を目指しましょう。
栄養がとりにくい時の工夫
親世代では食欲がない日など、大切な栄養を摂りにくい時も増えてきます。
足りない栄養が摂れるレシピを数種類、普段から用意していると対応が楽になりますね。
水分が足りないと口の中がパサパサするなど、食べにくくなるものです。
柔らかくて食べやすいもの、スープなど、表の栄養素が入ったもののインスタント食品などを常備しておくことも一つの手段です。
また、生活リズムを整えると食欲が出てくることがあります。
ロコトレで適度な運動をして食欲がわけば一石二鳥ですね。
ロコモティブシンドロームを予防して健康寿命を延ばしましょう
ロコモティブシンドロームは年齢とともに、またはケガによって運動機能が低下してしまう状態です。
自分や親世代の身体の状態を知るためにまずロコチェックをしましょう。
ロコチェックは7項目。
1.片脚立ちで靴下がはけない
2.家の中でつまづいたりすべったりする
3.階段を上がるのに手すりが必要である
4,家のやや重い仕事が困難である(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)
5.2kg程度の買い物をして持ち帰ることが困難である。(1リットルの牛乳パック2個程度)
6.15分くらい続けて歩くことができない
7.横断歩道を青信号で渡りきれない
ひとつでも当てはまればロコモの可能性があります。
ロコモ度を調べるためには3つの「ロコモ度テスト」をします。
必ず介助者をつけ、安全におこなってください。
・下肢筋力を調べる「立ち上がりテスト」
・歩幅を調べる「ツーステップテスト」
・体の状態、生活状況を調べる「ロコモ25テスト」
「ロコモ度1」~「ロコモ度3」の3段階で、もっとも高く出たものがあなたのロコモ度となります。
ロコモの可能性がある人は改善のため、チェックに引っかからなかった人も予防のためにロコトレを始めましょう。
ロコトレは基本の運動が2つ、基本にプラスして2つです。
・バランス能力をつける「片脚立ち」
・下肢筋力をつける「スクワット」
・ふくらはぎの筋力をつける「ヒールレイズ」
・下肢の柔軟性、バランス能力、筋力をつける「フロントランジ」
安全に気をつけて、無理なく続けてくださいね。
好きなスポーツを見つけて楽しむことも、ロコモの予防になります。
ロコモ予防では栄養にも気をつけましょう。
「さあにぎやか(に)いただく」を頭文字に持つ食品を食べて積極的に栄養を摂ることが予防につながります。
| さ | あ | に | ぎ | や | か | い | た | だ | く |
| 魚 | 油 | 肉 | 牛乳 | 野菜 | 海藻 | 芋 | 卵 | 大豆 | 果物 |
親世代は食欲がなく栄養が摂れない時もあります。
食べやすい食品を常備しておくなどの工夫をして栄養を摂りましょう。
健康寿命を延ばせば介護の負担が減り、介護する側もされる側も楽になります。
自分が健康であれば楽しい時間が増えますね。
楽しい時間を増やすために、ロコモの予防をしていきましょう。
皆が無理なく安心して暮らせるように、ロコモティブシンドロームを意識した毎日を送ってください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

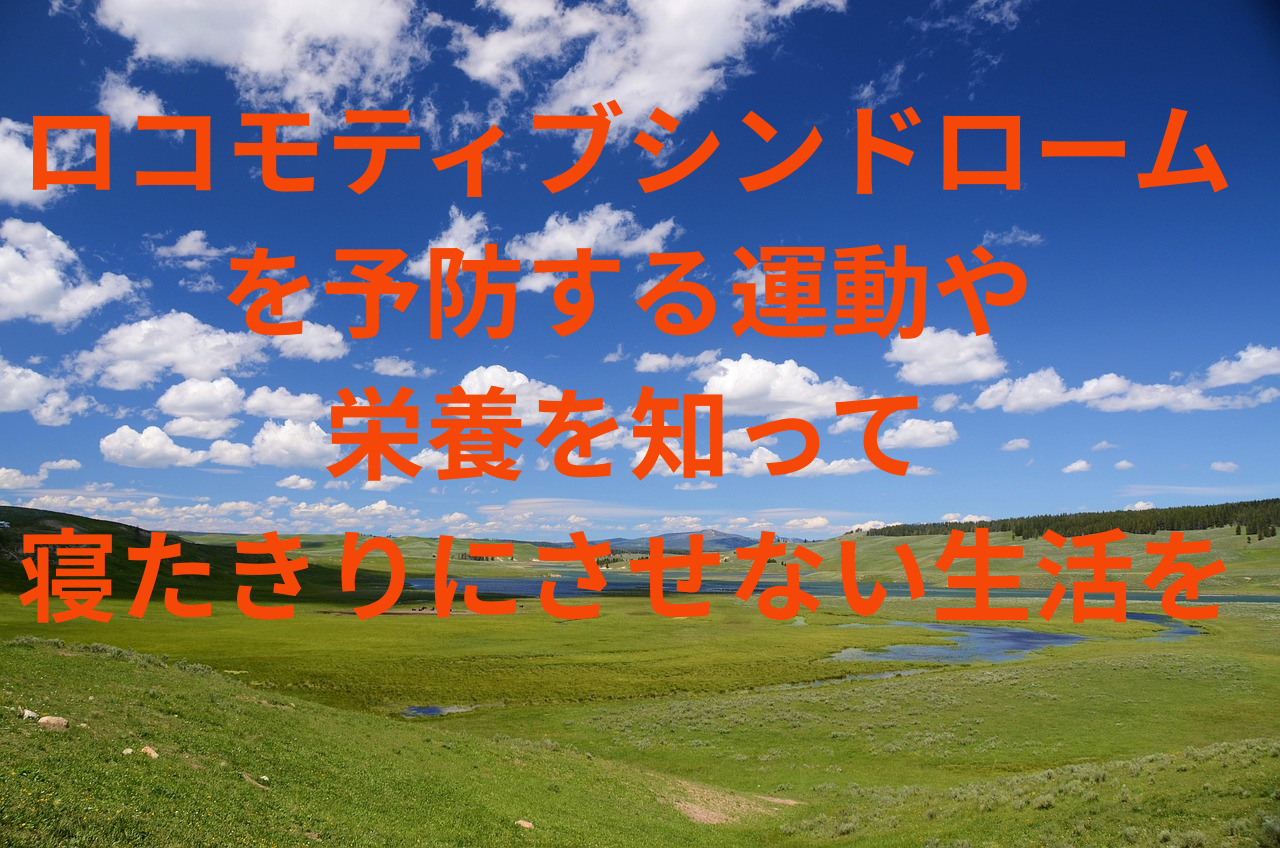
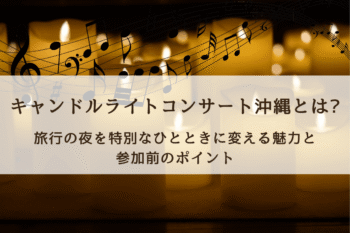
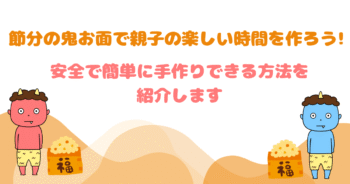
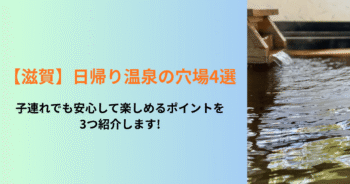


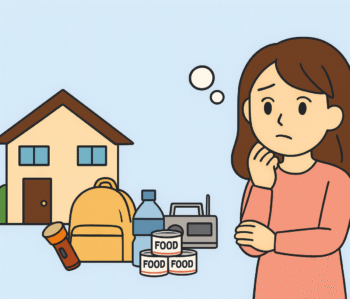
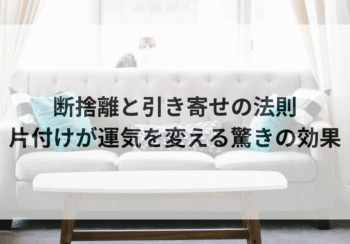
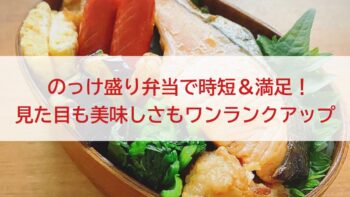
コメント