 読者さまA
読者さまAローストビーフの赤みや赤い汁、子供が口にしても大丈夫か気になる……



手づくりしてみたいけれど、生焼けで食中毒にならないか不安……



ローストビーフを安全においしく楽しみたいですよね
ローストビーフ、切ってみたら中が赤くて、食べていいのか迷ってしまう……。
そんな経験はありませんか?
ローストビーフが赤く見えるのは肉の特性によるもので、安全な状態であることがほとんどです。
ただし、加熱不足の場合もあるので注意も必要。
この記事では、赤い部分の正体や、安全においしく食べるための見分け方、調理ポイントまでわかりやすく紹介します。
- ローストビーフの中が赤い理由
- 食べても大丈夫安な状態かを判断する方法
- 食中毒を防ぐための「調理や保管の重要ポイント」
- おいしさを保つ、おすすめの温め直し方法
ぜひこの記事を読んで、ローストビーフの赤みに対する不安や疑問を解消してください。



家族みんなでローストビーフを安全においしくいただきましょう♪
ローストビーフの赤い部分は食べても大丈夫?


ローストビーフの中が赤いと、「火が通っていないのでは?」と心配になりますよね。
実は、その赤さは危険のサインではなく、“ロゼ”と呼ばれる理想的な焼き加減であることがほとんどです。
ここでは、赤く見える理由やその正体をくわしく解説します。
正しい判断方法を知っておけば、安心しておいしく味わえるようになりますよ。
ローストビーフが赤い理由は「ロゼ」だから
ローストビーフの中が赤く見えるのは、火が通っていないからではなく、「ロゼ」と呼ばれる理想的な焼き上がりだからです。
ロゼとはフランス語で「バラ色」という意味。
表面はしっかり加熱しながら、中心は60℃前後の低温を保ってじっくり火を通すことで、きれいなロゼ色が生まれます。
この温度帯では、肉のたんぱく質が完全に固まらず、ジューシーさと旨味をそのまま閉じ込められるのです。
一見「生」のように見えても、加熱温度や時間が適切ならば安全に食べられます。



赤みが残るローストビーフは、上手に火を通せたサインと言えますね。
赤い肉汁の理由と「ミオグロビン」の役割
ローストビーフを切ったとき、赤い液体が出ることがあります。
「血」だと思う人も多いですが、実は血ではなく「ミオグロビン」というたんぱく質によるものです。
ミオグロビンは、筋肉中で酸素を運ぶ働きを持つ成分。
加熱によって、赤からピンク、そして灰色へと変化します。
ローストビーフの場合、このミオグロビンがほどよく残っているため、赤みのある見た目になります。
ミオグロビンに肉の水分が混ざると、まるで血のように見えますが、しっかり加熱されていれば問題ありません。
むしろ、この赤い肉汁こそがローストビーフのうま味の1つ。
手作りした場合は、肉汁を落ち着かせるために切る前に10~15分ほど休ませましょう。
よりしっとりとした仕上がりになりますよ。
赤いローストビーフが安全か判断する方法


ローストビーフの赤みは「ロゼ」と呼ばれる理想的な仕上がりであることが多いですが、加熱が足りない場合は食中毒のリスクもあります。
そのため、見た目や感触だけでなく、温度計を使って確認することが大切です。
ここでは、安全チェック方法を2つ紹介します。
1.見た目や感触をチェックする
2.中心温度をはかる
ポイントを押さえておけば、赤いローストビーフを前に「これ大丈夫かな……?」と迷うこともなくなりますよ。
見た目や感触をチェックする
ローストビーフの赤みを見分けるときは、まず見た目と感触をチェックしてみましょう。
生焼けの場合は、切ったときに中からドロッとした赤い汁が出たり、表面がぬるっとしていたりします。
一方で、しっかり火が通っているロゼの状態なら、赤い部分があっても表面がしっとりしていて、肉汁が透明に近いのが特徴です。
指で軽く押したときに弾力があるかもチェックしましょう。
また、冷めてからでも赤みがきれいに保たれている場合は、加熱がしっかりされている証拠。
「見た目+触感+汁の色」の3つをセットで確認し、正確に判断するようにしましょう。
中心温度をはかる
見た目だけでは焼き加減の判断が難しい場合、確実なのが温度計を使って中心温度を確認する方法。
ローストビーフの場合、中心が63℃以上になっていれば、ほとんどの食中毒菌は死滅するといわれています。
測るときは、温度計の先を肉のいちばん厚い部分に差し込みます。
中心の温度が安定するまで時間をかけて測定してください。
もし温度が60℃以下なら、アルミホイルで包んで余熱で温めるか、再度短時間加熱すれば安心です。



温度計を使って感覚をつかんでおくと、見た目でも焼き加減を判断しやすくなりますよ。
食中毒を防ぐための調理・保存のポイント


ローストビーフは、温度管理や保存方法を間違えると食中毒の原因になることがあります。
特に家庭で手作りする場合は、焼くときの温度・保存のタイミング・冷却方法を意識することがとても大切。
ここでは、家庭でもできる「安全においしく食べるための基本ルール」を詳しく紹介します。
1つずつ見ていきましょう。
ローストビーフを安全に作る加熱ルール
ローストビーフを安全に作るには、次の2点が重要です。
- 表面の殺菌
- 中心温度の管理
まず、調理前にキッチンペーパーで余分な水分をふき取り、フライパンで表面をまんべんなく焼いてください。
この工程で、肉の表面についた菌をしっかり殺菌できます。
その後、オーブンやフライパンで中心温度が63℃以上になるように、弱火でじっくり加熱しましょう。
一度に高温で焼こうとすると外が焦げ、中が生焼けになってしまうため注意が必要です。
焼き上がったあとはアルミホイルで包み、15〜30分ほど休ませると、余熱で中までしっかり火が通ります。
冷却と保存の正しい手順
焼き上がったローストビーフは、すぐ冷蔵庫に入れてはいけません。
中がまだ温かい状態で冷蔵すると、菌が繁殖しやすくなり、食中毒の原因になることがあるからです。
大切なポイントは「粗熱を取ってから冷蔵/冷凍する」こと。
まずは常温で30分〜1時間ほど置き、粗熱をしっかり取りましょう。
その後、完全に冷めたらラップでぴったり包み、保存袋や密閉容器に入れて冷蔵庫へ。
冷蔵なら2〜3日、冷凍なら2〜3週間を目安に食べきりましょう。



冷凍する場合は、風味や食感を保つために、できるだけ空気を抜いて密封してくださいね。
調理後に確認してみよう
食べる前にも、加熱や保存が問題なくできていたかをしっかり確認しましょう。
冷蔵庫から出したローストビーフを切ったときに、中心が冷たすぎる・ぬるっとしている場合は、再加熱が必要です。
また、酸っぱい臭いやねばりがある場合は、傷んでいる可能性があるので食べないようにしてください。
安全においしく楽しむためには、「見た目」「匂い」「手触り」の3つをしっかりチェックするのが大切です。
手間をかけて作ったローストビーフを、安心しておいしく食べましょう。



残念ですが、少しでも違和感があれば、処分する勇気も大切ですね。
ローストビーフのおいしさを保つ再加熱のコツ


冷蔵庫に入れておいたローストビーフをそのまま食べると、少し固く感じることがあります。
温めることで解消されますが、加熱の仕方を間違えると、今度はパサパサになってしまうことも。
ここでは、しっとり感と旨味をキープしたまま温め直すコツを紹介します。



お好みの方法で、ローストビーフをおいしく温めてくださいね。
再加熱は湯せんが一番おすすめ
ローストビーフを温め直すには、湯せん(お湯で温める方法)が一番失敗しにくい方法です。
手順もとても簡単!
冷めたローストビーフをラップでしっかり包み、耐熱の袋に入れてから、60〜70℃くらいのお湯に5〜10分ほど浸すだけ。
お湯が熱すぎると固くなるので、沸騰させず「ちょっと熱いくらい」の温度を保ちましょう。
湯せんなら、肉の中まで均一に温まり、しっとりした食感をキープできます。
少し手間はかかりますが、他の方法よりもおいしく温められるので一番おすすめの方法です。
レンジで再加熱するときはここに注意!
ローストビーフを温め直すときは、熱を入れすぎないのが大事なポイントです。
電子レンジで加熱しすぎると、せっかくのしっとり感がなくなり、パサパサになってしまうことも。
温めるときは、ラップをかけて「短時間×弱めのワット数」で、様子を見ながら少しずつ温めましょう。
また、厚めに切ると中まで温まりにくいので、薄めにスライスしてから加熱するのがおすすめです。
全体的にほんのり温かいくらいになったらOK。
加熱しすぎないほうが、ローストビーフ本来のやわらかさと香りを楽しめます。
フライパンでも再加熱できる
湯せんのほかに、フライパンで温め直す方法もあります。
コツは、フライパンを弱火にして、少しの水とふたを使うこと。
フライパンに大さじ1〜2の水を入れてローストビーフをのせ、ふたをして1〜2分ほど蒸すように温めます。
「軽い蒸し焼き状態」にすることで、中までふんわり温まり、しっとり感もキープできます。
焦げないように様子を見ながら、じんわり温かくなったタイミングで火を止めましょう。



しっとりするように温めたいけれど、湯せんが面倒なときや少量だけ食べたいときにおすすめ♪
まとめ|ローストビーフは赤くても大丈夫!
この記事では、ローストビーフの中が赤い理由や、食べても大丈夫か判断するポイントについてお伝えしました。
まずは、赤くても食べて大丈夫な理由からふりかえってみましょう。
- 赤い部分は生焼けではなく「ロゼ」と呼ばれる理想の焼き加減であることが多い。
- 切ったときに出る赤い汁は血ではなくミオグロビンというたんぱく質。
- しっかり加熱されていれば赤くても大丈夫。
次に、安全かどうかの判断方法について紹介しました。
- 表面の状態・汁の透明感・弾力を確認すれば、おおよその安全性が判断できる。
- 温度計で中心温度を測り、63℃以上ならOK。
- 見た目に迷ったら「温度で確認」が最も確実な方法。
食中毒を防ぐための知識も、しっかり身につけておきましょう。
- 調理時はまず表面をしっかり焼いて殺菌し、中心温度63℃以上をキープする。
- 焼いたあとはすぐ冷蔵せず、30〜60分かけて粗熱を取ることが重要。
- 冷蔵なら2〜3日、冷凍なら2〜3週間を目安に食べきる。
- 酸っぱい臭いや粘りがあるときは食べずに処分。
最後に、温め直しのコツもお伝えしました。
ローストビーフのおいしさを、逃さないように温めてくださいね。
- 【おすすめ】湯せんなら60〜70℃で5〜10分、しっとりジューシーに温められる。
- 電子レンジでは「短時間×弱めのワット数」。
- フライパン再加熱は、少量の水+ふたで蒸し焼きにすると◎。
- 再加熱しすぎるとパサつくため、「ほんのり温かい」がベスト。
ローストビーフの赤さは、危険ではなく“おいしさの証”。
きちんと加熱されていればローストビーフは安心して食べられます。
今回紹介した温度や保存のコツを意識して、家族みんなでおいしく安全なローストビーフを楽しんでくださいね。
「手作りローストビーフに挑戦したいけれど、失敗はしたくない……」
そんなあなたにおすすめの「ジップロックとお湯で簡単に作れるレシピ」を、以下で詳しく紹介しています。
ぜひ、こちらもご覧ください!


最後までお読みいただきありがとうございました。


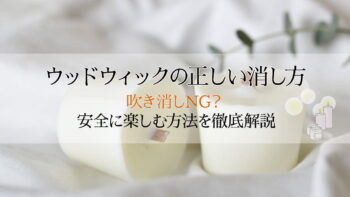

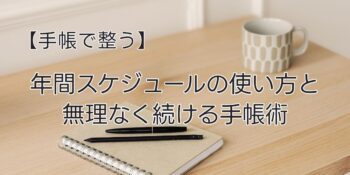
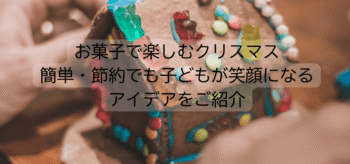


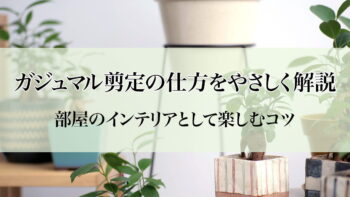
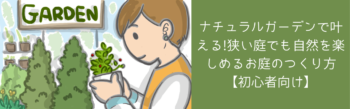
コメント