7月の行事といえば7月7日の七夕が思い浮かぶのではないでしょうか。
子ども達はお願いごとを考えたり、未満児の保護者の方も子どもたちの健康を願ったりと素敵な行事ですよね。
 読者さま
読者さま子どもたちにわかりやすく七夕の行事を説明するにはどうしたらいいんだろう……。
お願い事をするだけでも楽しめる行事ですが、せっかくなら由来や星空のことを学んで七夕への興味を深めてもらいたいですよね。



今回はパネルシアターを用いて七夕行事について簡単に理解できる企画をご紹介します!
この記事では、パネルシアターとは何かから始まり、七夕の物語の復習、そして実際にパネルシアターを作成するときのコツについてご紹介していきます。
普段の保育が忙しくなかなか作業時間の取れない忙しい保育士さんでも、時短でできる方法もお伝えしております。
ぜひ最後までお読みください。
七夕パネルシアターとは?


パネルシアターとは、毛羽立ちのあるフランネル紙や不織布を使用したパネルを舞台に、絵や文字を貼ったり外したりしながら、ストーリーを展開していく表現方法です。
行事保育で人気の理由
今回はパネルシアターを活用した、七夕の行事説明をご紹介しますが、そもそもパネルシアターが行事保育で人気の理由とは何でしょうか?
大きく2つあります。
- 子どもが集中して見やすい
- 視覚的に理解しやすい
1つ1つ詳しく説明していきますね。
子どもが集中して見やすい
パネルシアターでは、絵や文字のパネルが、現れたり消えたりして場面展開がどんどん行われていきます。
そのため、子どもたちの集中力が持続しやすいことが特徴です。
子どもたちも「次は何が出てくるのかな」と期待しながら見ることができます。
子どもたちの反応を見ながら絵を出し入れできるので、子どもたちのタイミングに合わせながらストーリーを進めていき、離脱を減らすことができます。
また、パネルが変形する・揺れるなどの工夫をすることで、さらに子どもたちのワクワク感を増幅させることができ、ストーリーにも動きが出せるんです。
視覚的に理解しやすい
語り手の言葉とともにパネルが動かされるので、視覚的にストーリーの内容を理解することができます。
パネルの数を増減させることによって場面展開の調節ができるので、年齢に合わせた理解を深めていくこともできます。
七夕との相性の良さ
上の2点に加えて、「七夕」×パネルシアターの相性の良さが、子ども達の興味関心をさらに広げることのできるポイントがあるので見ていきましょう。
- 夜空や星を表現しやすい
- ストーリーを短く伝えられる
夜空や星を表現しやすい
言葉や絵本のイラストだけでは理解しがたい夜空や星のお話も、1つ1つのパネルにわかれることでそれぞれの特徴をつかむことができるのが、パネルシアターのメリットです。
ストーリーを短く伝えられる
パネルの数を増やしたり減らしたりすることによって、ストーリーを調節できるので、ストーリーを省略することができ、未満児向けのお話にすることも可能です。
七夕パネルシアターの基本ストーリー


パネルシアターを作成する前に、七夕のストーリーについておさらいしておきましょう。
このストーリーをもとに、年齢によってストーリーを調整してみてください。
織姫と彦星の出会い
天の神様の娘、「織姫」は、世にも美しいはたを織っていました。
あまりに一生懸命にはたを織るので、自分の髪や服を構おうともしません。
そんな姿をかわいそうに思った神様は、織姫にふさわしい婿を探すことにしました。
天の神様が天の川の岸辺を歩いていると、牛の世話をしている「彦星」という若者と出会いました。
彦星も織姫と同じように、休む間もなくせっせと毎日真面目に仕事をしています。
これだけ働き者の若者なら、織姫と幸せに暮らしていける、と天の神様は彦星を織姫の婿に選びました。
仲良くなりすぎた二人
織姫も彦星も一瞬でお互いに恋に落ち、とても仲のいい夫婦になりました。
しかし、結婚後2人は遊んでばかりいて、ちっとも仕事をしなくなってしまいました。
心配した天の神様が2人に声をかけましたが、空返事だけで、仕事はしません。
織姫がはたを織らなくなったので、機織り機にはほこりをかぶり、神様たちの服はボロボロに。
彦星も牛の世話をしないので、牛はどんどん痩せこけてついに病気になってしまいました。
天の川で離ればなれ
「このままではだめだ」と怒った天の神様は2人を引き離すことを決めました。
織姫は天の川の西へ、彦星を天の川の東へと連れていき、広い広い天の川に挟まれた2人はお互いの姿を見ることができなくなりました。
それからというもの2人は働くどころか、会えないことに悲しむばかりで、ますます状況は悪化。
再び困ってしまった天の神様は2人が以前のようにまじめに働くことを条件に、7月7日、1年に1度だけ2人が会うことを許すことにしました。
2人は年に一度会える7月7日を楽しみにしながら、毎日せっせと働くようになりました。
七月七日に会える約束
織姫が再びはたを織るようになり、神様たちも喜びました。
彦星も一生懸命牛の世話を頑張ったので、牛は元気になりました。
待ちに待った7月7日の夜になると、2人は天の川を渡りデートを楽しみます。
しかし、雨が降ってしまうと天の川を渡ることができません。
そんなときは、どこからかカササギという鳥の群れがやってきて、橋の代わりとなり、2人を会わせてくれるのでした。
年齢別のアレンジ方法





七夕のストーリーは理解できました!
これでパネルシアターが作れそうです!



素晴らしい✨
しかし、年齢ごとに集中力や理解力に差がありますので、ストーリーを伝えるときに工夫が必要です!
3歳児向けシンプル版
3歳児は集中力に差がある時期です。
なるべくストーリーを簡潔に、天の川を中心に進めていき、親子で夜空を見上げる楽しさが伝わるようにしましょう。
4歳児向け定番ストーリー
4歳児は集中力も出てきて、パネルシアターに積極的に参加する子が多くみられます。
理解力も3歳児より高くなります。
出会いから再会までの場面を台詞を加えながら、ストーリーを進めていくといいでしょう。
5歳児向け発展版
5歳児では集中力や、パネルシアターに参加する様子なども見ながらストーリー展開を考えていきます。
複雑なストーリーもよく理解できるようになっていることが予想されます。
カササギの橋や願い事の場面を追加して、さらに七夕の理解を深めていくことができるようにしましょう。
演出の工夫ポイント


様々なパネルが出てくるのでスタンダードな演出でも十分に楽しめるパネルシアターですが、少し工夫を加えると、ぐっとお話しの世界に子どもたちが引き込まれます。



今回は七夕のストーリーを伝えるのにぴったりな演出をご紹介します!
夜空と星の見せ方
パネルシアターは白い背景を使用することが多いです。
しかし、ブラックシアターと言って、黒い背景に蛍光カラーのパネルを貼って夜空などの場面を表現することもあります。
七夕の舞台は夜空がメインになるので、序盤は白い背景→7月7日の天の川のシーンで黒い背景に切り替えるなどすると、子ども達の注目を再び集められるきっかけとなります。
子どもが参加できる仕掛け
子どもたちも、実はパネルをぺたぺた貼ってみたいという気持ちを持っています。
ストーリーを展開していく中で、短冊を貼ったり、星のパネルを置く体験などを取り入れることによって更に参加型のパネルシアターにすることができるので、工夫してみてください。
そしてその経験が、理解をより一層深めることにもつながります。
歌や手遊びとの組み合わせ
「たなばたさま」や「きらきら星」を挿入
3歳児の小さい際学年からでも簡単に取り入れられるのが、歌をパネルシアターで取り入れることです。
「ささのは さらさら~♪」
と歌ってもどんな情景なのかイメージすることは難しいですよね。
歌や手遊びするだけでなく、歌と一緒にパネルシアターで情景を再現しながら示すことによって、子どもたちがどんな歌詞の意味なのかをしっかりとイメージできるようになります。



パネルシアターだけでも十分楽しいけれど、演出を少し工夫するだけでさらに七夕に興味を持ってもらえそうですね!
七夕パネルシアターの準備と材料





いよいよパネルシアターの作成ですね!
でもなんだか時間がかかりそう……。



確かに様々な場面展開をしていくパネルシアターは、作成する数も多く大変そうなイメージですよね。
忙しい保育士があまり時間を割かずに作成できる方法があります。
パネルシアターを行う際には、必須な道具があります。
作成時に必要なものは基本的なものから、ちょっと工夫したい時に使う道具もご紹介してますので、順番に見ていきましょう!
基本の道具
まず、パネルシアターを作るための基本材料と道具をお伝えしていきます。
- Pペーパー
- パネル布
- 段ボールやポリスチレンロール、パネルボードなどの固い板
- スタンドorイーゼル(子どもたちの目線に合わせて)
Pペーパーに絵を描くことによって、パネルシアターにくっつく仕組みです。
Pペーパーもパネル布もアマゾンなどで購入することができます。
パネル布のみではふにゃふにゃなので、固い板を準備しそこに布を貼り付ける形にすると、丈夫な背景が完成しますよ。
子どもたちの目線や参加人数に合わせて、スタンドやイーゼル等に背景を置き、全体に見やすいようにしていきます。
- 鉛筆
- 油性ペン
- 絵の具セット
- カッター
- ボンド
- カッター
- 刺しゅう糸
- 裁縫セット など……
次に、Pペーパーにイラストを描く際に必要な画材を用意します。
Pペーパー1枚に1つのイラストというわけではないので、描き終わった後ははさみで切り取ります。
パネルシアターで登場する人物の手足を動かせるように、それぞれのパーツを作り1か所で縫い合わせるとゆらゆら揺れる可愛いパネルを作成することもできるんですよ。
そんなときに必要なのが裁縫セットです。
そのほかにも開く仕掛けを作ったり、ポケットに入れるような表現をしたいときにボンドやカッターを使用します。



初心者の方は画材のみで作成したパネルでも、子どもたちは十分に楽しんでくれますので安心してください!
手作りの工夫
1つ1つ手作りしていては、かなりの時間を要してしまいますよね。
保育雑誌の型紙を使用したり、ネットでも無料ダウンロードしたりすることができます。
型紙を印刷した後、Pペーパーに書き写して色づけすれば完成なので、とても簡単に作成することができるんです。
Pペーパーに直接カラー印刷をする方法もあります。
また、より時間がない場合にはminneやメルカリなどで手作りのパネルシアターを販売している方もいます。
背景も手作りする必要がある場合おススメの動画がありますので参考になさってください。
パネル布以外の材料はすべて100均でそろえることができます。
使いまわせるデザイン
星や空のパーツは他の行事にも応用
同じパーツでも七夕以外にも使用できるようにしておくと、毎回すべてのパーツを作らずに済みます。
七夕の場合は登場人物が「織姫」「彦星」と衣装が個性的なので他のシアターに使うことは難しいですが、星や空のパーツなどは他のお話でも活躍の場がありそうですね。
七夕パネルシアターで素敵な思い出を作ろう!
行事の由来は、大切な伝統として丁寧に子どもたちに伝えていきたいですよね。
由来やストーリーを伝えるときにとても有効的なのがパネルシアターです。
絵本や紙芝居と違い、子どもたちの年齢や成長度合いに合わせてお話の長さや複雑さを変えられるのが特徴です。
今回はそんなパネルシアターの特徴を、七夕のストーリーを伝えていくことに相性がいいことをお伝えしてきました。
最後にパネルシアターが選ばれる理由と、作成方法についておさらいしましょう。
- 子どもが集中して見やすい
- 視覚的に理解しやすい
- 夜空や星を表現しやすい
- ストーリーを短く伝えられる
パネルシアター作成時には、必須のものと画材などのプラスアルファのものがありました。
- Pペーパー
- パネル布
- 段ボールやポリスチレンロール、パネルボードなどの固い板
- スタンドorイーゼル(子どもたちの目線に合わせて)
- 鉛筆
- 油性ペン
- 絵の具セット
- カッター
- ボンド
- カッター
- 刺しゅう糸
- 裁縫セット など……
パネルシアターは行事だけでなく、普段の保育の中でも手遊びの代わりや、今月の歌のイメージ付けなど様々な場面で活躍します。
ぜひ作成したパネルシアターを保育の様々な場面で活用してみてください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

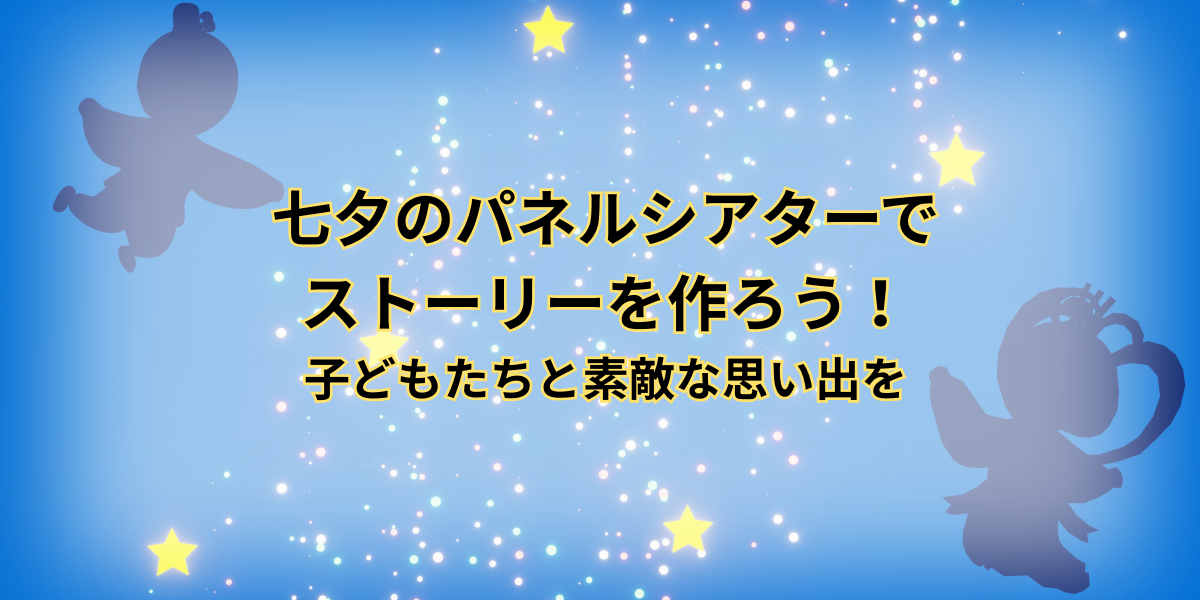
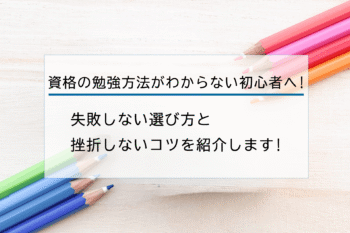
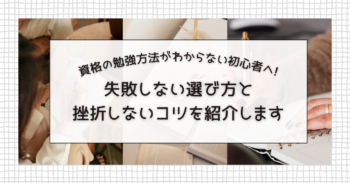
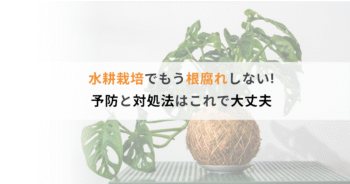

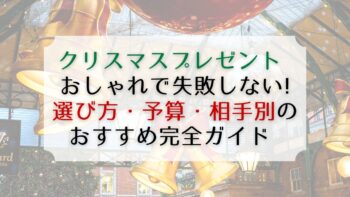
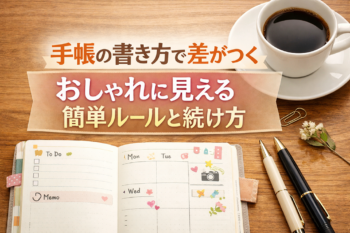

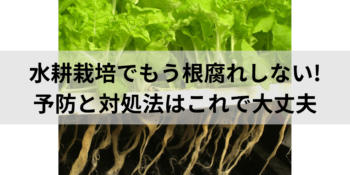
コメント