 読者様
読者様最近「エネルギーミックス」っていう言葉を聞くことがあるけど、よくわからない…。
みなさんは、私たちの生活に必要な電気がどう作られているか知っていますか?
日本では今、「2030年エネルギーミックス」という新しい目標を立てています。
これは、「火力発電だけでなく、太陽光や風力なども組み合わせることで安定して電気を作ろう」という考え方です。
でも、今の日本は火力発電に頼りすぎているのが現状です。
このままだと、地球温暖化が進んだり、燃料が足りなくなる心配もあります。
もし災害が起きたり、世界の情勢が変わったりしたら電気が足りなくなるかもしれません。
また、地球温暖化を進めてしまう温室効果ガスを減らすためにも、太陽光発電などの再生可能エネルギーを増やす必要があります。
この記事を読めば、エネルギーミックスの意味や目標、なぜ発電方法を変えなければいけないのかがわかります。
また、今日から私たちにできることも紹介しますので、ぜひ取り組んでみてください。



未来の地球と自分たちの生活を守るために、一緒に考えてみましょう!
エネルギーミックスとは?
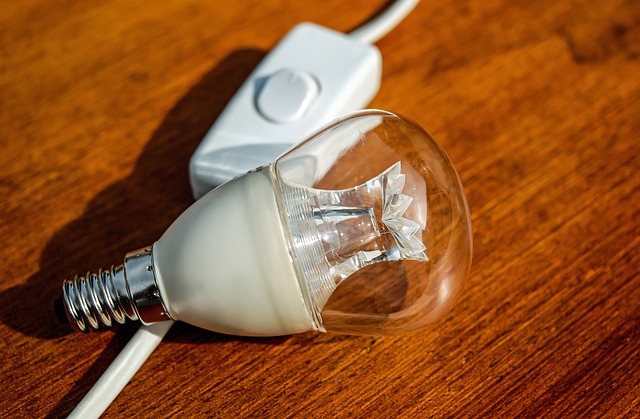
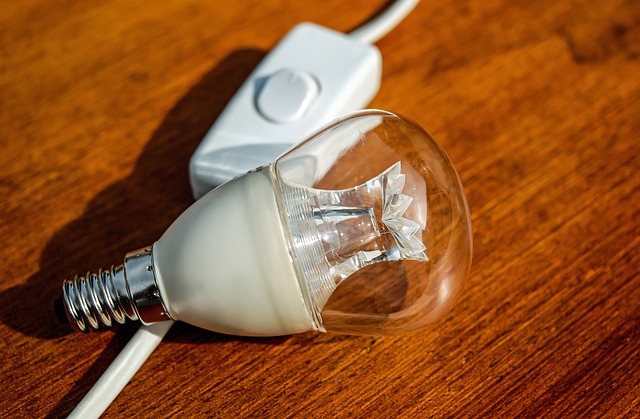



エネルギーミックスって具体的にどういうこと?
電力供給を特定の電源に依存せず、再生可能エネルギー・原子力・火力などを最適に組み合わせる戦略
日本の電気を作る方法をバランスよく組み合わせて、環境や安全、経済のことを考えながらエネルギーを使っていこうというものです。
日本のエネルギー政策の根幹を成す「3E+S」原則(経済性・環境性・供給安定性+安全性)に基づき、以下の4つの軸で構成されます。



ここからは、エネルギーミックスはどんなもので構成されているのか見ていきましょう。
エネルギーミックスに含まれる4つのエネルギー
エネルギーミックスを構成するエネルギーは大きく分けて以下の4つです。
一つずつ見ていきましょう。
再生可能エネルギー
太陽の光や風、水の流れ、地熱、木や植物など、自然の力を使って電気を作る方法です。
これらは使ってもなくならないエネルギーで、発電しても地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO₂)をほとんど出さないという大きなメリットがあります。
しかし、天気や季節によって発電量が変わりやすく、曇りや風が弱い日には電気があまり作れません。
また、たくさん発電しすぎて電気が余ると、発電を一時的に止めなければならないこともあります。
九州では太陽光発電が増えすぎて電気が余ったことがありました。
原子力発電
ウランという特別な燃料を使って、安定してたくさんの電気を作れる発電方法です。
天気に左右されず、二酸化炭素もほとんど出しませんが、2011年の福島第一原発事故のあと、安全のための厳しいルールができました。
今は日本に33基の原子炉がありますが、2023年時点で動いているのは10基のみ。
これから原子力発電を増やすには、もっと安全にする工夫と、地域の人たちの理解が必要です。
火力発電
石油や石炭、天然ガスなどを燃やして電気を作ります。
必要なときにすぐ発電量を増やせるので便利ですが、たくさんの二酸化炭素を出してしまうのが問題です。
最近は、アンモニアを混ぜて燃やす技術や、出た二酸化炭素を集めて地中に閉じ込める技術(CCS)も研究されています。
新技術(水素・アンモニア)
新しい技術として、水素やアンモニアを使った発電も注目されています。
水素を燃やしても二酸化炭素が出ないので、地球に優しい発電方法です。
アンモニアは今ある火力発電所でも使えるのが強みですが、作るのにお金がかかる、運ぶための設備がまだ十分ではないという課題もあります。



あまり意識していなかったけど、私たちが使っている電気の作り方はいろいろあるのね。
いろいろな種類の発電方法を組み合わせて使うことで、何か起きたときでも安定して電気を使えるようになります。
地震や台風などの災害が起きて一つの発電所が止まってしまっても、ほかの発電方法で電気を作り続けられるでしょう。
こうすることで、電気が止まるリスクを減らし、みんなの生活に必要な電気を安定して届けられるのです。
また、いろいろな発電方法をバランスよく使うことは、地球温暖化を防ぐためにも重要。
つまり、太陽光や風力、火力、原子力など、それぞれの特徴を活かして組み合わせることで、災害やトラブルに強く、環境にもやさしいエネルギーの使い方ができるのです。



エネルギーミックスは、災害時のリスクや地球温暖化を防ぐための重要な計画なんですね。
エネルギーミックスを実現するために、重要な考え方が、次に説明する3E+S原則です。
3E+S原則
日本のエネルギー政策の基本となる「3E+S」とは、以下の考え方です。
安全性(Safety)を最優先に
・安定供給(Energy Security)
・経済効率性(Economic Efficiency)
・環境適合(Environment)
の3つをバランスよく実現するためのルール
エネルギーミックスはこの考えに基づいているのです。



どうしてこの4つの考えが必要なの?



どれか一つが欠けても、エネルギーミックスは達成できないんです。
例えば、太陽光は環境に優しいですが、曇りの日は発電量が減ります。
原子力は安定供給できますが、安全対策が必須。
1つに頼らず「エネルギーミックス」で組み合わせることで、電気を止めず、環境を守り、家計にも優しい社会を目指しています。
「3E+S」について、一つずつ解説していきましょう。
安全性(S)
エネルギーを使うとき、事故や災害が起きないようにすることが一番大切です。
例えば、原子力発電所では地震や津波に備えた設計が義務付けられ、定期的な安全点検を実施。
太陽光パネルも台風で飛ばされないよう、強固な設置方法が求められます。
安定供給(E)
日本はエネルギーのほとんどを海外からの輸入に頼っているため、戦争や災害で供給が止まらないよう対策が必要です。
具体的には、LNG(天然ガス)の調達先を複数の国に分散させたり、再生可能エネルギーを増やして自給率を高めたりしています。
例えば、九州では太陽光発電が増えすぎて電気が余ることもありますが、蓄電池を活用して調整しています。
経済効率性(E)
電気代が高すぎると家計や企業への負担が避けられません。
負担をかけないためには、効率的な発電方法を選び、無駄を減らすことが重要です。
例えば、古い火力発電所を最新の高効率型に替えると、同じ燃料でも多くの電気を作れます。
また、家庭用のLED照明やエコキュートの普及を支援する省エネ補助金も活用されています。
環境適合(E)
地球温暖化を防ぐため、CO₂を出さない再生可能エネルギー(太陽光・風力など)の割合を増やしています。
2030年までに再エネ比率を36~38%に引き上げる目標のため、天候に左右されないよう、水素発電やアンモニア混焼技術の開発も進めています。



3E+Sは、私たちの生活を支えるエネルギーを「安全に」「安定的に」「安く」「環境に優しく」使うためのものなのね。
2030年目標とその課題は?


この章では、エネルギーミックスの2030年目標とは何か、そして現状の課題はどんなものがあるのかを解説します。
2030年目標とは
日本は2030年までに「温室効果ガスを2013年比で46%削減」することを目標に掲げています。
このため、再生可能エネルギー(太陽光など)の割合を36~38%に上げ、原子力発電を20~22%、火力発電を41%に減らす計画です。
この計画は2050年カーボンニュートラル実現に向けた中間段階で、2013年度比で温室効果ガス46%削減を目指す政策の根幹です。
簡単に言うと、「出した分だけ自然に戻す」ことで地球温暖化を止めようという取り組みです。
2030年の電源構成目標は、エネルギー基本計画(2021年策定)に基づき以下の数値が設定されています。


目標達成にあたっての課題とは?
課題には、以下のようなものがあります。
①自然エネルギーの不安定さ
②原子力への依存リスク
③コストと技術
日本が掲げる2030年のエネルギー目標を達成するためには、いくつかの大きな課題を解決する必要があります。
まず、自然エネルギーの不安定さ。
太陽光発電は曇りや夜間に発電できず、風力発電も風が弱いと停止してしまいます。
電力供給が不安定になる問題を解消するためには、余った電気を貯めておく「蓄電池」の普及が急がれているのです。
次に、原子力発電への依存リスク。
再稼働には地域住民の理解が不可欠ですが、事故への不安や使用済み核燃料の処分方法が未解決な点がハードルとなっています。
さらに、コストと技術面の課題も。
太陽光パネルや風力タービンの設置費用が高く、水素やアンモニアを効率的に製造する技術がまだ実用段階に達していません。
加えて、日本のエネルギー自給率(国内でまかなえるエネルギーの割合)は現在約12%と低く、2030年までに30%まで引き上げる必要があります。
海外からの燃料輸入に頼りすぎない社会を作るためには、再生可能エネルギーや原子力の活用が鍵となるでしょう。
目標達成のための取り組み


日本は2030年までに「温室効果ガスを2013年比で46%削減」する目標を掲げています。
その目標達成のために再生可能エネルギー(再エネ)の割合を36~38%に引き上げる計画です。
主な取り組みを3つのポイントで説明します。
①太陽光発電の拡大
②洋上風力発電の推進
③火力発電の削減
太陽光発電の拡大
工場や学校の屋根、空港、鉄道の施設などに太陽光パネルを増やす政策が進んでいます。
特に公共施設への設置を義務化し、地域主導の再エネプロジェクトを支援しています。
例えば、使われていない土地を太陽光発電所に変える「地域共生型再エネ」が各地で始まっており、今後も取り組みが広がっていくでしょう。
洋上風力発電の推進
海に大きな風車を立てる「洋上風力」を重点的に増やします。
日本は海が広いため、北海道や九州の洋上で大規模な風力発電所を建設し、2030年までに発電量を大幅に拡大する計画です。
火力発電の削減
石炭火力発電を段階的に減らし、代わりに天然ガスとアンモニアを混ぜて燃やす技術を導入します。
アンモニアは燃やしてもCO₂が出ないため、環境に優しい燃料として期待されています。



目標達成に向けたさまざまな取り組みが行われているのです。
これらの他にも、省エネ強化のため家庭や工場の電気使用量を減らすため、LED照明や高効率エアコンの普及を支援しています。
また、原子力発電所は安全性を確認した上で、停止中の原子力発電所を再び動かす予定です。
政府は「再エネを最優先する」と宣言し、企業や地域と協力しながら目標達成を目指しています。
例えば、太陽光パネルを設置する家庭には補助金が出る制度もあります。
このように、日本は「環境保護」と「エネルギーの安定供給」を両立させるため、さまざまな対策を進めているのです。
アメリカ・EUなど海外ではどんな取り組みをしている?





エネルギーのことって、日本だけの問題じゃないはず。日本以外の国では、どんな取り組みがされているの?
この章では、世界各国の中からアメリカとEU(ヨーロッパ連合)を取り上げ、その取り組みをご紹介します。
アメリカの取り組み
アメリカは2030年までに「温室効果ガスを2005年比で半分に減らす」という大きな目標を掲げています。
そのために、自然エネルギーを増やしたり、州ごとに独自の対策を打ち出したりしています。
①自然エネルギーの拡大
②州ごとの独自対策
③新しい技術の開発
自然エネルギーの拡大
太陽光パネルや風力発電をたくさん作る計画で、2035年までに電力の80%以上を自然エネルギーでまかなうことを目指しています。
例えば、工場や家庭の屋根に太陽光パネルを設置する取り組みが進んでいます。
州ごとの独自対策
カリフォルニア州やテキサス州など、地域の特徴に合わせた政策を実施。
日照時間が長い地域では太陽光、風が強い地域では風力発電を重点的に増やしています。
新しい技術の開発
電気自動車(EV)の充電スポットを増やしたり、火力発電の代わりに水素を使う研究にも力を入れたりしています。
政府はこれらの技術開発に多額の投資を惜しみません。
アメリカは「環境保護と経済発展を両立させる」ために、企業や市民も一緒に取り組んでいます。
例えば、電気自動車を買う人への補助金制度など、暮らしに直結した対策も進めています。
EU(ヨーロッパ連合)の取り組み
EU(ヨーロッパ連合)は、2030年までに自然エネルギーの割合を42.5%に引き上げることを目標にしています。
これは、2021年の約22%から約2倍に増やす計画です。
主な取り組みは次の3つです。
①自然エネルギーを増やす
②省エネ対策の強化
③ロシアからのエネルギー依存を脱却
自然エネルギーを増やす
太陽光発電を2030年までに600GW(2022年比約3倍)導入する計画を推進しています。
特に北海・バルト海を中心とした洋上風力発電を現在の11倍に拡大。
新築商業施設や公共建築物への太陽光パネル設置を法的に義務付ける「EUソーアルーフトップイニシアチブ」を展開しています。
こうした取り組みにより、再生可能エネルギーの容量を大幅に増加させる方針です。
省エネ対策の強化
2030年までに最終エネルギー消費量を11.7%削減(従来目標9%から強化)するため、建物の断熱改修義務化や省エネ家電普及を加速しています。
具体的には、公共施設や商業ビルのエネルギー性能基準を引き上げ、スペイン1国分に相当するエネルギー削減を目指す取り組みが進められています。
ロシアからのエネルギー依存を脱却
天然ガス輸入の約40%を占めていたロシア産燃料を、再生可能エネルギーとノルウェー・米国など他国からの調達多様化で代替。
2022年12月には再生エネルギー事業の許可手続きを最大9か月に短縮する緊急規制を導入し、プロジェクトの迅速化を図っています。
これらの政策を通じ、EUは気候変動対策とエネルギー安全保障の両立を目指しています。
また、EUでは「地球温暖化対策」と「エネルギー安全保障」を両立させるため、企業や市民も巻き込んだ取り組みも活発に。
例えば、自然エネルギーで作られた電気を選ぶ制度や、電気自動車の充電スポット増設など、暮らしに直結した変化が進んでいます。



世界中で、エネルギー問題解決に向けたさまざまな取り組みがされていますね!
私たちにできることは?





エネルギーミックスって地球規模の話だから、私たち個人にはあんまり関係ない?



いいえ!私たち個人でも地球のためにできることがあります。
個人が今日からできること
私たち個人でできることには、以下のようなものがあります。
- 再エネ電力の選択:新電力会社への切り替えで、家庭のCO2排出量を最大50%削減可能。
- 省エネ家電の導入:LED照明やエコキュートの購入で、年間約2万円の光熱費削減効果。
- 地域再エネプロジェクトへの参加:市民ファンドを通じた太陽光発電投資(例:みんな電力の「おひさまファンド」)。
エネルギーミックスの目標達成には、私たち一人ひとりの行動がとても重要。
まず、再生可能エネルギーを利用する新電力会社に切り替えることで、家庭のCO2排出量を最大50%削減できます。
また、省エネ家電の導入も効果的です。
例えば、LED照明やエコキュートを使用することで、年間約2万円の光熱費を節約できます。
さらに、地域の再生可能エネルギープロジェクトに参加する方法も。
市民ファンドを通じて太陽光発電に投資する「おひさまファンド」など、身近な形で再エネ普及に貢献できる取り組みが増えています。
これらの行動は環境負荷の軽減だけでなく、家計にもプラスとなる選択肢です。
政策に参加する方法
一般人でも、国や地域のエネルギー政策に意見を伝える方法が2つあります。
パブリックコメントとは、国がエネルギー計画を作り直すとき、一般の人から意見を募集すること。
インターネットで「エネルギー基本計画」と検索し、専用フォームに「自然エネルギーをもっと増やしてほしい」など具体的な提案を書き込んでみましょう。
過去には、国民の声が風力発電の支援策に反映された例があります。
市役所や町内会が開くワークショップでは、住民が「学校の屋根に太陽光パネルを付けよう」「公園に風車を立てよう」などアイデアを出し合っています。
北海道十勝地方では、住民の意見で小水力発電所が建設され、地域の電気代が安くなりました。
これらの方法を使えば、中学生でも未来のエネルギー政策を変える力を持てます。
まずは地元のホームページで「エネルギー勉強会」を探してみましょう。



私たちにも、こんなにできることがあるのね!
まとめ~エネルギーミックスを理解して、アクションを始めよう!
エネルギーミックスとは
電力供給を特定の電源に依存せず、再生可能エネルギー・原子力・火力などを最適に組み合わせる戦略
エネルギーミックスの計画は「3E+S」と呼ばれる考え方に基づいています。
安全性(Safety)を最優先に
・安定供給(Energy Security)
・経済効率性(Economic Efficiency)
・環境適合(Environment)
の3つをバランスよく実現するためのルール
エネルギーミックスが目指す目標は、再生可能エネルギー(太陽光など)の割合を36~38%に上げ、原子力発電を20~22%、火力発電を41%の比率にすること。
ですが、目標達成にはいくつかの課題があります。
①自然エネルギーの不安定さ
②原子力への依存リスク
③コストと技術
日本政府は現在、目標達成の以下のような取り組みを行っています。
①太陽光発電の拡大
②洋上風力発電の推進
③火力発電の削減
海外の事例としては、EUの再エネ拡大戦略や米国のクリーンエネルギー技術などがあります。
そして私たち個人でもできることが。
- 再エネ電力の選択:新電力会社への切り替えで、家庭のCO2排出量を最大50%削減可能。
- 省エネ家電の導入:LED照明やエコキュートの購入で、年間約2万円の光熱費削減効果。
- 地域再エネプロジェクトへの参加:市民ファンドを通じた太陽光発電投資(例:みんな電力の「おひさまファンド」)。
パブリックコメント(意見公募)を活用したり、地域のエネルギー会議に参加したりするのもよいでしょう。
2030年目標の達成には、技術革新だけでなく、私たちの意識改革と行動変容が不可欠です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



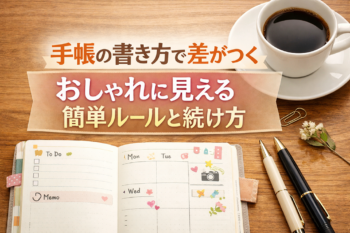
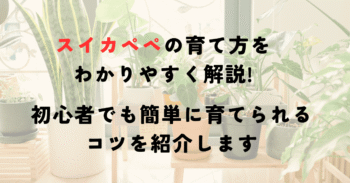
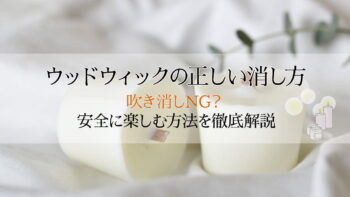
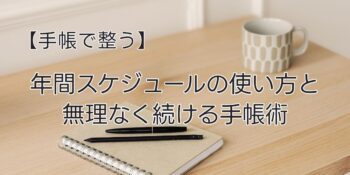
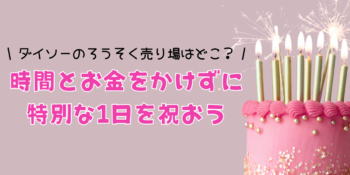
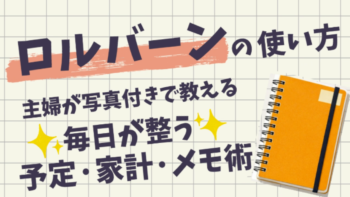
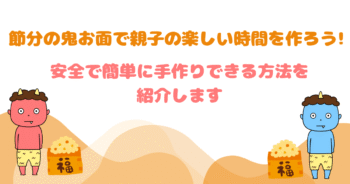
コメント