妊娠中は赤ちゃんとの大切でかけがえのない時間。
しあわせいっぱいの日々を送られていることと思います。
我が子の誕生を心待ちにしている一方で、将来どのくらいお金が必要なのか不安に思われている方もいるのではないでしょうか?
出産も金銭面で不安に思うひとつだと思います。
 読者さま
読者さま出産にもかなりお金がかかると聞くけど正直かなり不安・・・
会社に勤めていないと出産後に国から給付金は受け取れないのかな?
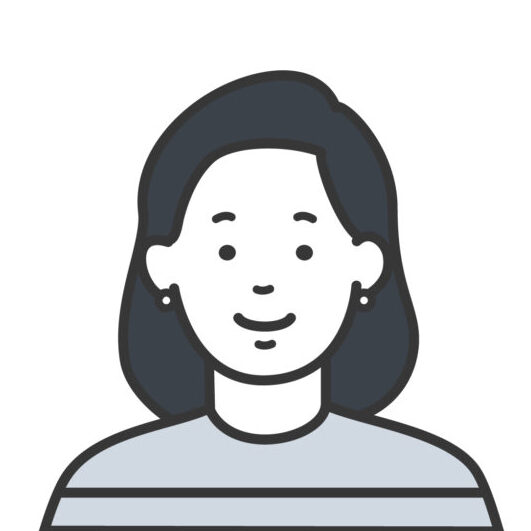
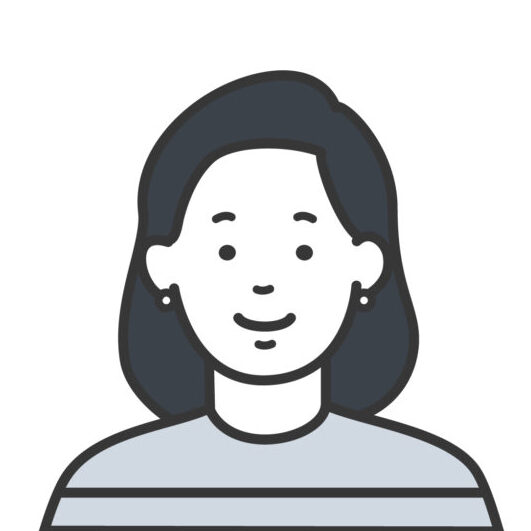
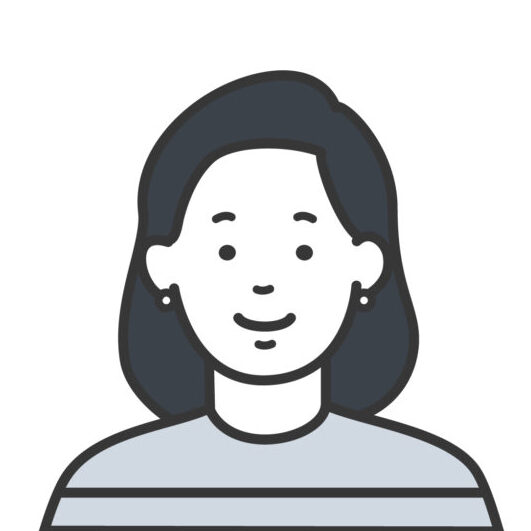
国民健康保険加入者の方でも受け取れる給付金があります。
国からの給付される出産育児一時金について詳しく見ていきましょう。
【出産育児一時金】国民健康保険加入者と被用者保険加入者の違い


病気やケガ、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度に健康保険があります。
健康保険の種類は国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度の3つです。
出産育児一時金とは、出産にかかった費用を一部補うためのもので、通常50万円(令和5年3月末まで42万円)が支給されます。
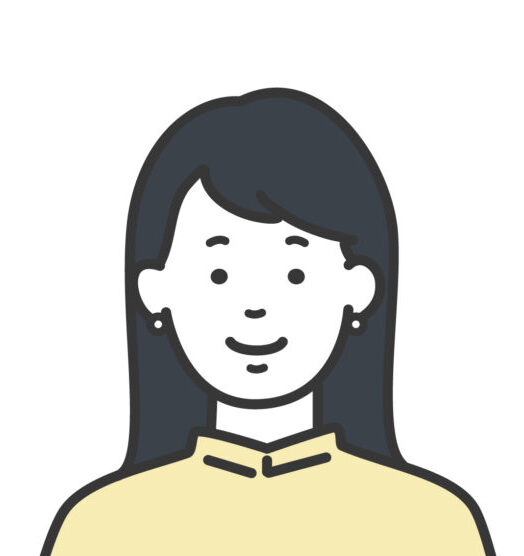
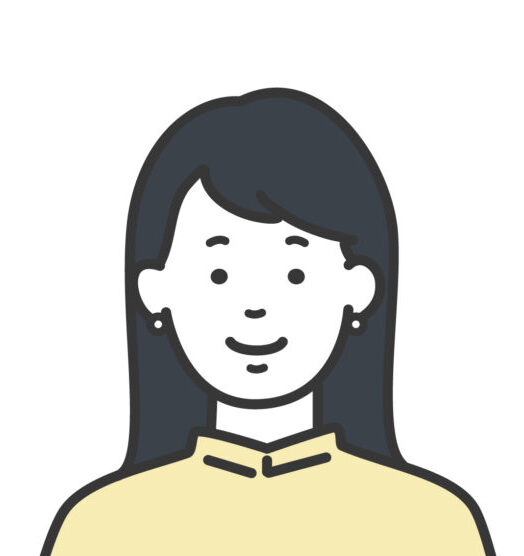
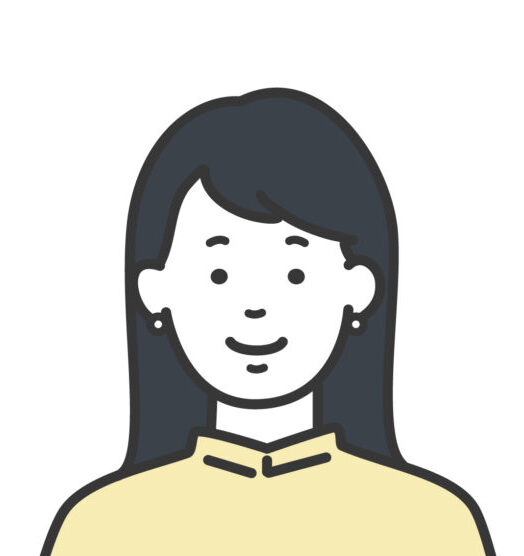
出産育児一時金として50万円給付金として受け取れるんだね。
出産育児一時金は、被用者保険加入者もしくは国民健康保険加入者が申請することで利用できる制度です。
国民健康保険と被用者保険はそもそもどう違うのでしょうか?
国民健康保険とは?誰が加入対象?
国民健康保険は、日本の公的医療保険制度の一つです。
会社員や公務員など、健康保険に加入していない個人事業主やフリーランス、学生、専業主婦夫などが加入対象となります。
被用者保険とは?誰が加入対象?
会社員や公務員は原則として全員が被用者保険に加入します。
また、 一定の基準を満たすパート・アルバイトの方も被用者保険に加入できます。
具体的には、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合
または以下の5つの条件すべてに該当する場合です。
- 1週間の所定労働時間が30時間以上
- 1ヶ月の所定労働日数が20日以上
- 1時間当たりの賃金が800円以上
- 雇用期間が3ヶ月以上
- 労働時間の変動が大きい場合であっても、年間の所定労働時間が1500時間以上
パート・アルバイトの方で条件を満たしている場合、被用者保険に加入している可能性もあるのでこの機会に確認してみましょう。
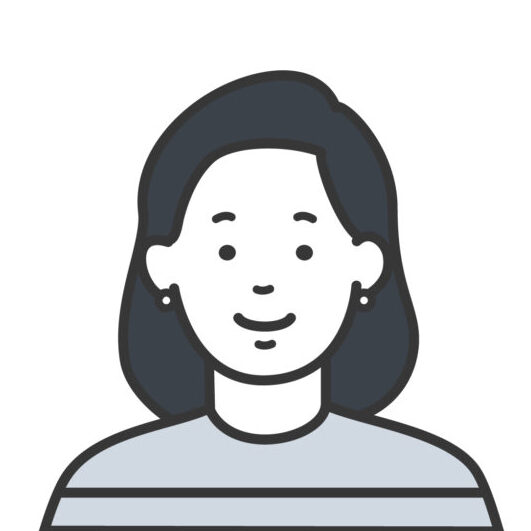
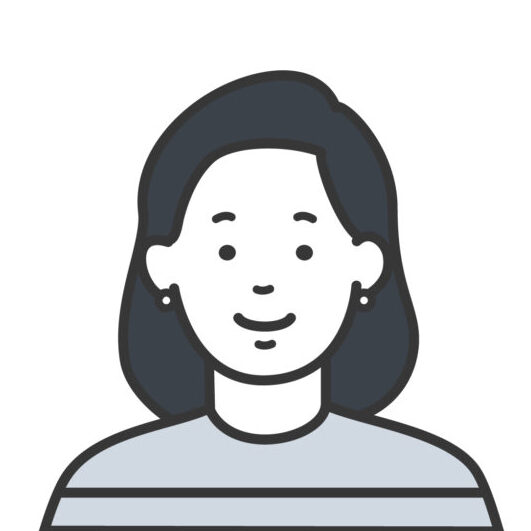
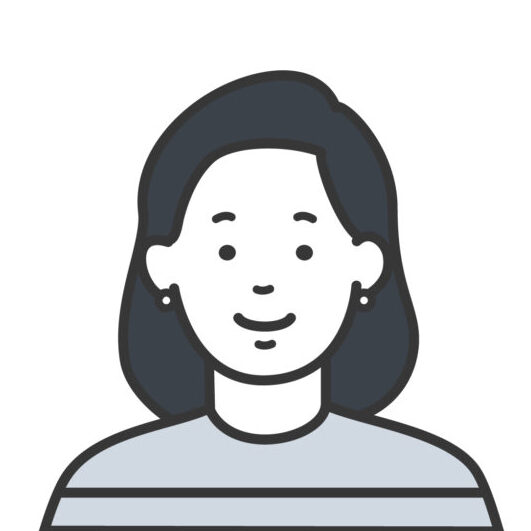
どうだったかな?と思われる方は、
保険証を確認するとご自身の加入状況が確認できますよ。
【出産育児一時金】受給方法


出産育児一時金の受給方法は、大きく分けて2つあります。
1つ目は直接支払制度です。
直接支払制度とは、出産育児一時金(原則50万円)を医療機関等に直接支払ってもらう制度です。
出産にかかる費用をすべて全額支払う必要がなく、多額の現金を用意する必要がありません。
また、請求手続きも医療機関に代行してもらえるため手間が少ないのも特徴です。申請は、出産予定日の1ヶ月前から可能です。
2つ目は受取代理制度です。
受取代理制度とは、出産育児一時金を(原則50万円)を超過した金額のみ支払うという点では直接支払制度と同じです。
違いとしては出産育児一時金の請求手続きは原則対象者が直接申請する必要があります。
また、出産前に事前申請が必要となります。(出産予定日まで2ヶ月以内になった後の請求)
出産する際の医療機関によって利用できる制度が異なるため、事前に確認しておきましょう。
申請に必要な書類
- 出産育児一時金請求書
- 母子健康手帳
- 出産証明書
- その他(医療機関等によって異なる場合があります。)
- 健康保険加入者は、加入している健康保険組合
- 国民健康保険加入者は、加入している市区町村の窓口
出産育児一時金だけじゃない!出産後に利用できる制度


出産育児一時金の他に、出産前後に申請すると給付金が利用できる制度がいくつあります。
事前に確認し、利用できるものがあれば申請しておきましょう。
被用者保険加入者が出産した場合に受給できる制度
出産育児一時金以外にも、被用者保険加入者が出産した場合に利用できる制度はいくつかあります。
- 育児休暇給付金 育児休暇取得中に会社から給与の8割を支給される制度
- 育児休業給付金 育児休暇取得中に社会保険から6割の給与を支給される制度
- 出産費用貸付制度 出産育児一時金の支給までの間、無利子で資金を貸し付ける制度
- 産前産後休暇 出産前後の一定期間、有給で休暇を取得できる制度
- 育児休暇 子どもの出生後、1歳になるまで、無給で休暇を取得できる制度
国民健康保険加入者が出産した場合に受給できる制度
国民健康保険加入者が出産した場合に受給できる制度は、健康保険加入者の場合とほぼ同じです。
しかし、健康保険と異なり産前産後休暇や育児休暇がありません。
そのため、国民保険加入者の方は注意が必要です。
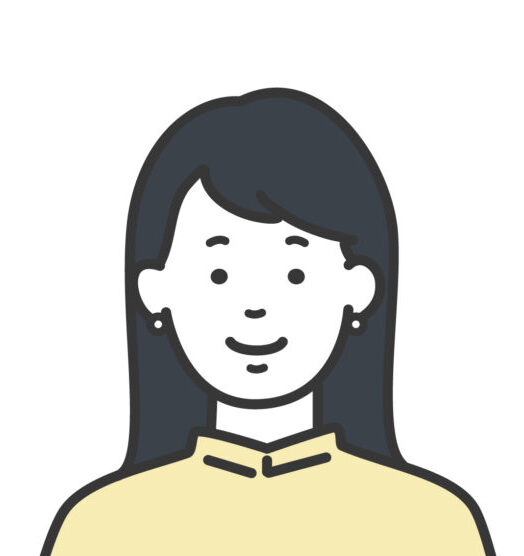
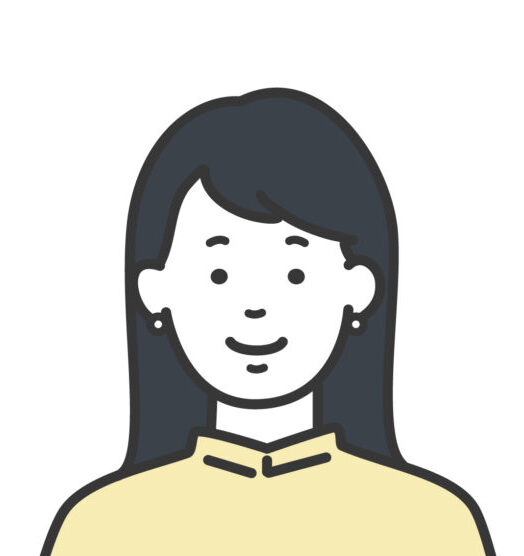
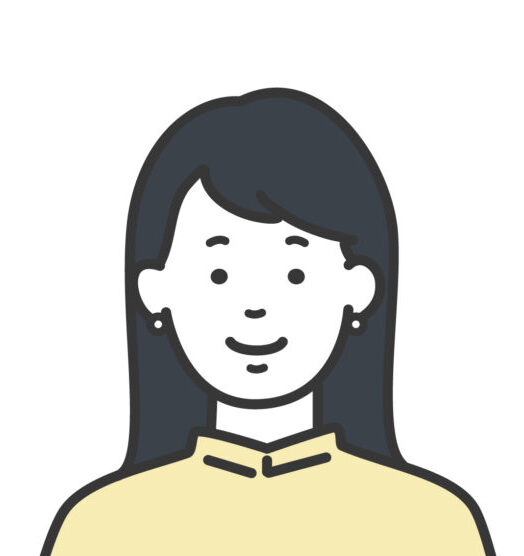
被用者保険に加入しているのか、国民健康保険に加入しているのかによって
利用できる制度に違いがあるんだね。
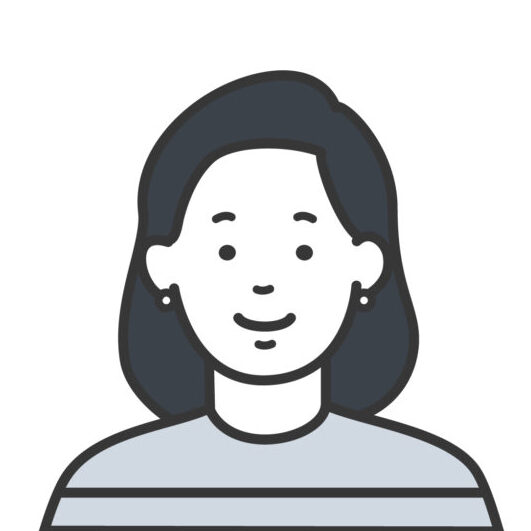
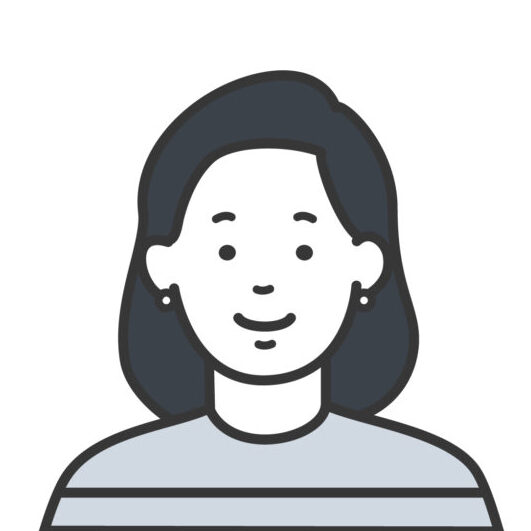
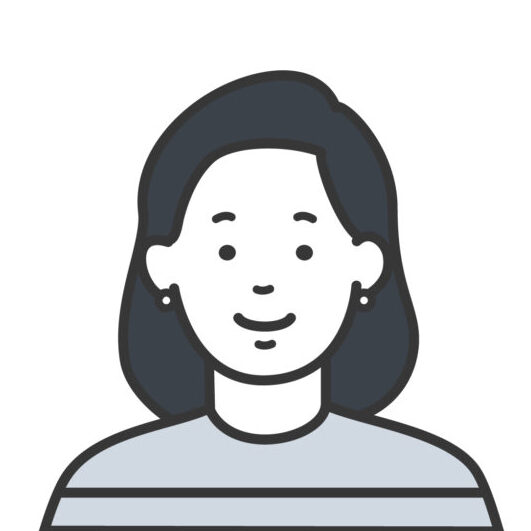
加入しているのが被用者保険なのか、国民健康保険なのかしっかり確認しておきましょう。
【出産育児一時金】誰が受け取れる?〜幸せなマタニティライフを〜まとめ
出産にかかるお金を一部補うための出産育児給付金をはじめ、出産前後に利用できる制度について紹介しました。
- 出産育児一時金は原則50万円
- 出産育児一時金は被用者保険加入者または国民健康保険加入者が申請できる
- 受給方法は直接支払制度または受取代理制度の2パターン
- 出産育児一時金の他に利用できる制度がある
加入している保険の違いによって利用できる制度が異なります。
| 国民健康保険加入者 | 被用者保険加入者 |
|---|---|
| 個人事業主 フリーランス 学生 専業主婦夫など | 会社員 公務員 一定の条件を満たしたアルバイト・パート |
被用者保険加入者と国民年金保険加入者で申請できる給付金の違いをまとめました。
| 給付金・制度 | 被用者保険加入者 | 国民健康保険加入者 |
|---|---|---|
| 育児休暇給付金 | ◯ | ◯ |
| 育児休業給付金 | ◯ | ◯ |
| 出産費用貸付制度 | ◯ | ◯ |
| 産前産後休暇 | ◯ | × |
| 育児休暇 | ◯ | × |
国民年金保険加入者には受給できない制度があるので注意が必要です。
事前に確認し、利用できる制度があれば申請していきましょう。
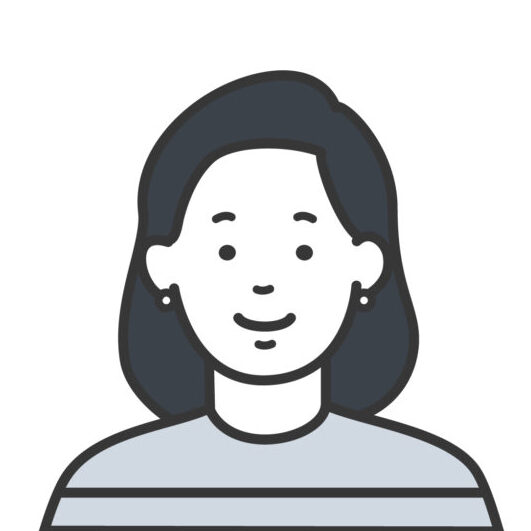
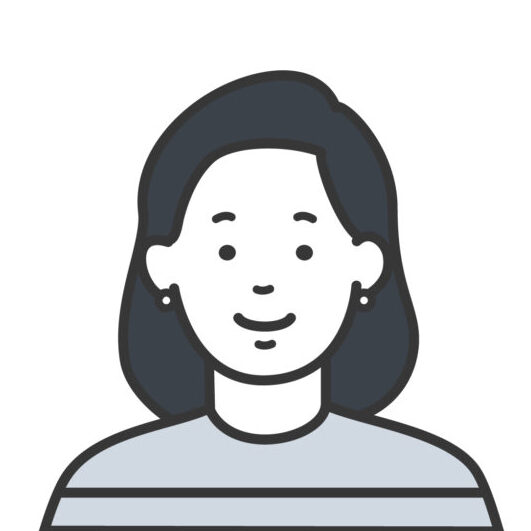
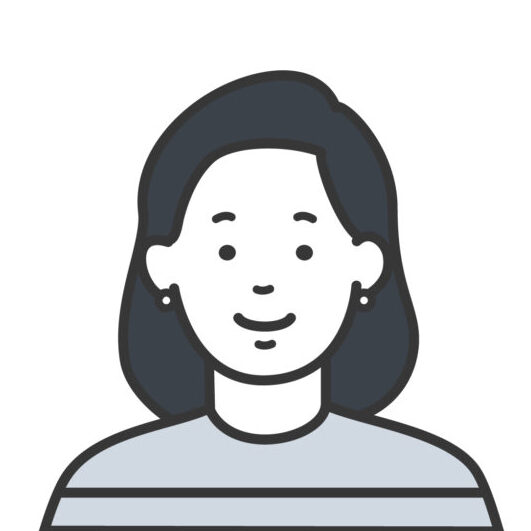
今しかない時間を楽しんでくださいね。
母子ともに無事出産を終えれることを祈っています。


最後までお読みいただきありがとうございました。

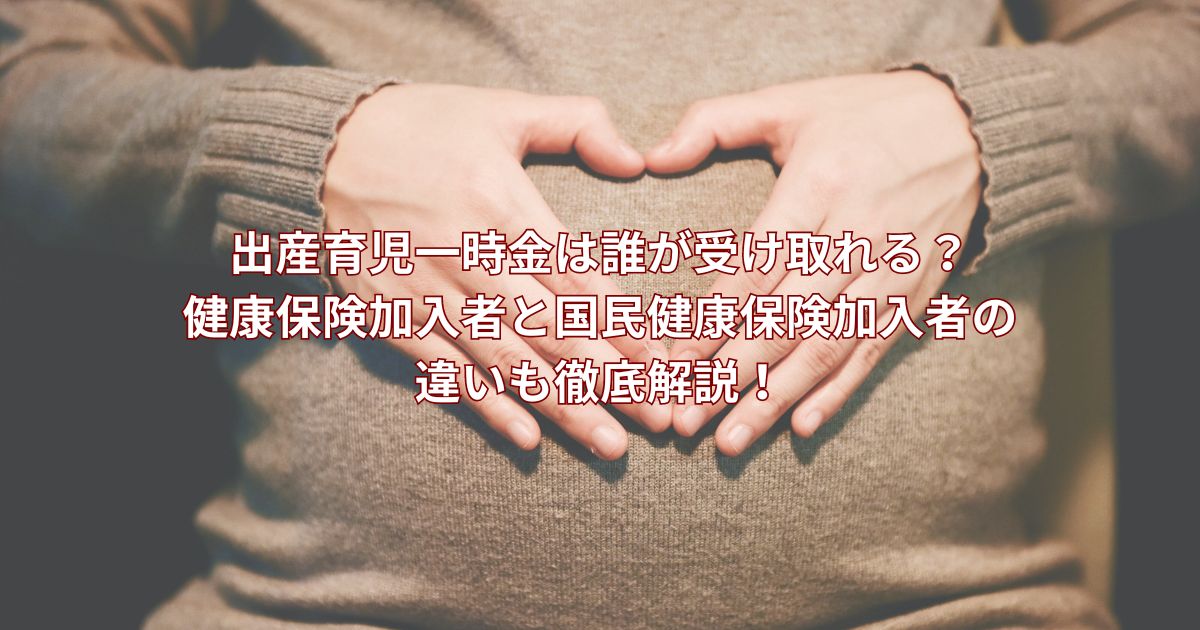


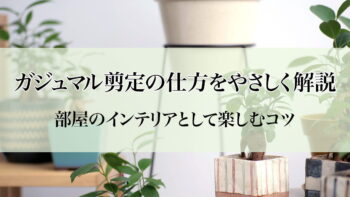




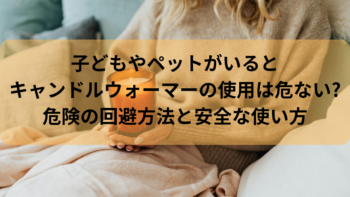
コメント