 読者さま
読者さま時候の挨拶はたくさんあるけど、どれを使うのが正しいのかな……
梅雨時期から7月にかけて使える挨拶はなにがあるの?
そんなお悩みはありませんか?
その時期にあった挨拶文は、季節の移り変わりを表現するだけでなく、相手の体調を気遣う一言も添えることができます。
しかし、同じ月の中でも使える期間が限られていたり、シーンによって言葉遣いを変える必要もあります。
この記事では、梅雨の時期から7月中の時候の挨拶をご紹介します。
- 時候の挨拶の種類
- 梅雨時期の時候の挨拶
- 7月中の時候の挨拶
- 時候の挨拶を使った手紙の書き方



親しき仲にも礼儀あり、というように大切な人に季節の挨拶を使った手紙を書いてみませんか?
時候の挨拶とは?


時候の挨拶とは、手紙の書きはじめに添える挨拶文のことです。
これは四季のある日本ならではの文化です。
一文添えるだけで季節の移り変わりを表現したり、相手を気遣うことができます。



一文で相手に良い印象を与えることができますよ!
また、季節感を取り入れた挨拶文はコミュニケーションに役立ちます。
漢語調と口語調の違い
時候の挨拶には2種類あります。
手紙の書き始めに相手や季節にあった挨拶を入れてくださいね。
- あらたまった場面で使う漢語調の挨拶
- 友人や親しい人に対して使う口語調の挨拶
漢語調は、古い中国の言葉が用いられた形態の表現です。
できるだけシンプルに表現することが求められます。
「春陽の候(しゅんようのこう)」「初夏の候(しょかのこう)」といった表現で、受け取った相手にあらたまった印象を与えます。
また、『候(こう)』は『折(おり)』『みぎり』などに置き変えることもできます。
口語調は、友人や付き合いが長い相手に使う表現です。
「新緑が美しい季節となりました」「暑い日が続いておりますが」といった話言葉で表現します。
相手に親しみやすい印象を与えます。
手紙を送る相手やシーンに合わせて「漢語調」と「口語調」を使い分けてくださいね。
時候の挨拶が不要な場合
書き始めの挨拶は必ず必要というわけではありません。
- お詫びのメール、手紙
- 緊急の要件
- 同じ案件で何度もやりとりをしているとき
- 見積書や請求書などの一般的なビジネス文書
上記の場合は、やりとりをスムーズにするために挨拶を省きましょう。
梅雨時期の時候の挨拶


梅雨時期に使える挨拶をご紹介します。
一般的に梅雨入りは6月上旬から中旬と言われています。
天候が変わりやすい時期なので、使うときは時期に合わせて挨拶を変えましょう。
また、蒸し暑く体調も崩しやすいので、相手を気遣う言葉を入れるといいですよ。
漢語調の挨拶
漢語調の挨拶は以下の通りです。
- 入梅の候(にゅうばいのこう)…梅雨入りを表す。
- 梅雨の候(つゆのこう)…梅雨時期の長雨を表す。
- 長雨の候(ながあめのこう)…梅雨に入り、長い雨の季節を表す。
- 梅雨晴れの候(つゆばれのこう)…梅雨の合間の晴天を表す。
「入梅の候」は6月上旬、「梅雨の候」「長雨の候」は6月中旬頃に使われることが多いです。
「梅雨晴れの候」は6月中旬から下旬まで使えますが、特に天候を気をつける必要があります。
雨が降り続けると気分も重くなりますが、そんな晴れた日に使いたい挨拶ですね。
口語調の挨拶
口語調の挨拶は以下の通りです。
- 入梅も間近となり不安定な空模様が続いております。
- 今年も梅雨入りの時期を迎えました。
- 紫陽花の色が美しく映える季節となりました。
- 長雨が続きますが、お元気にお過ごしでしょうか。
- 梅雨明けが待ち遠しく感じられる今日この頃でございます。
「梅雨」「長雨」といった言葉が使いやすい時期です。
雨についてだけでなく、季節の花や空模様など風景について入れると雰囲気が変わりますよ。
7月に使える時候の挨拶


7月は本格的な暑さが到来します。
暑中見舞いやお中元のやりとりがあるので、ぜひ季節にあった挨拶を入れた手紙を書いてみてください。
暑中見舞いは二十四節気の小暑から立秋の前日にかけて、お中元は7月上旬から7月15日頃までに送るのが一般的です。
7月上旬頃は梅雨明け、中旬からは暑さについて一文添えるといいでしょう。
また、近年は7月半ばでも梅雨が明けないこともあるので、月のみで挨拶文を考えるのではなく、気候にあった挨拶を取り入れましょう。
漢語調の挨拶
漢語調の挨拶は以下の通りです。
- 盛夏の候(せいかのこう)…夏の盛りを意味する。
- 猛暑の候(もうしょのこう)…猛暑日が続いてから使う。
- 向暑の候(こうしょのこう)…初夏の訪れを指す言葉。小暑(7日7頃)まで使える。
- 酷暑の候(こくしょのこう)…最も暑い頃を意味し、8月上旬まで使える。
- 炎暑の候(えんしょのこう)…燃えるように暑いという意味で8月上旬まで使える。
- 大暑の候(たいしょのこう)…大暑(7月23日頃)以降使える。
漢語調では、使える時期が決まっている表現もあるので注意が必要です。
例えば、盛夏の候は7月上旬から8月上旬まで使えます。
8月をイメージする人が多いかもしれませんが、「盛夏」は7月の季語として使用されることもあります。
また、手紙を書いたときは使える挨拶でも、相手が読むときには時期がずれていることがないように挨拶を選んでください。
口語調の挨拶
口語調の挨拶は以下の通りです。
- 梅雨明けも近づき、海や山が恋しい頃となりました。
- 梅雨が明け、太陽がまぶしい季節となってまいりました。
- いよいよ本格的な夏の到来を感じるこの頃です。
- 猛暑到来となりました。
- うだるような暑さが続いております。
- 夏空が眩しく輝く頃となりました。
梅雨明けや暑さについて書くと季節にあった挨拶になります。
一般的に梅雨明けは7月上旬頃といわれているので、6月を過ぎていても使えますよ。
「海」「山」といったその月の印象を受ける言葉を取り入れるのもいいですね。



手紙を送る場合は、相手が手紙を読む頃に合わせて言葉を選ぶといいですよ!
時候の挨拶を使った手紙の書き方


最後に、時候の挨拶を入れた手紙の書き方をご紹介します。
手紙は、以下のように4つの段落に分類されます。
- 前文
- 主文
- 末文
- 後付
ひとつずつ説明しますね。
「拝啓」など、はじめの挨拶にあたる頭語、時候の挨拶、相手を気遣う言葉の3つの要素を書き入れる。
「さて」「ところで」「実は」などの起語を用いて手紙の目的、要件を簡潔に述べる。
一通の手紙に要件を2つ以上入れないように注意が必要。
相手の健康や無事を願う言葉、要件を総括する言葉を述べ、頭語に呼応する結語を添える。
書いた日付、差出人、宛名を書く。
次に、漢語調、口語調の挨拶の使い方を例文でご紹介します。
漢語調の時候の挨拶を使った例文
漢語調の挨拶を使った例文をご紹介します。
拝啓
盛夏の候、○○様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、日頃の感謝を込めてお菓子をお送りいたしました。○○様が、洋菓子がお好きと伺ったので、召し上がっていただけましたら嬉しいです。
酷暑が続きますが、くれぐれも体調を崩されませんようご自愛ください。
敬具
今回は、お中元に添える手紙を例にしました。
お中元を贈る時期に合わせて「盛夏の候」で書き始めました。
頭語が「盛夏の候」なので、末文では「酷暑」という言葉を入れて時期を統一します。
また最後には、「暑さにより体調を崩さないように」と締めることで相手の無事を願う文末で終わるようにしました。
口語調の時候の挨拶を使った例文
口語調の挨拶を使った例文をご紹介します。
拝啓
梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
さて、○月○日に同窓会を開こうと思っております。担任の○○先生にはご出席のお返事をいただいております。一人でも多くのご出席をお待ちしています。
だんだんと暑さが厳しくなりますが、夏バテなどになりませんようお身体ご自愛ください。
敬具
今回は、梅雨時期に書いた同窓会の招待状を例にしました。
時候の挨拶に「梅雨明け」という言葉を使ったので、末文には「厳しくなる暑さによって体調を崩さないように」と相手の健康を願う文章で締めました。



ぜひ参考にしてみてください!
梅雨時期から7月の時候の挨拶を正しく使おう
以上、梅雨時期から7月中に使える時候の挨拶をご紹介してきました。
送る相手や場面に合わせて漢語調と口語調を使い分けてみてください。
あらたまった場面で使う挨拶。
『候(こう)』『折(おり)』『みぎり』などを後ろにつける。
友人や親しい人に対して使う挨拶。
話言葉で書くので、柔らかい印象を受ける。
手紙の場合は送る相手が読む頃を想定して時候の挨拶を入れるといいですよ。
【漢語調】
- 入梅の候(にゅうばいのこう)
- 梅雨の候(つゆのこう)
- 長雨の候(ながあめのこう)
- 梅雨晴れの候(つゆばれのこう)
【口語調】
- 入梅も間近となり不安定な空模様が続いております。
- 今年も梅雨入りの時期を迎えました。
- 紫陽花の色が美しく映える季節となりました。
- 長雨が続きますが、お元気にお過ごしでしょうか。
- 梅雨明けが待ち遠しく感じられる今日この頃でございます。
【漢語調】
- 盛夏の候(せいかのこう)
- 猛暑の候(もうしょのこう)
- 向暑の候(こうしょのこう)
- 酷暑の候(こくしょのこう)
- 炎暑の候(えんしょのこう)
- 大暑の候(たいしょのこう)
【口語調】
- 梅雨明けも近づき、海や山が恋しい頃となりました。
- 梅雨が明け、太陽がまぶしい季節となってまいりました。
- いよいよ本格的な夏の到来を感じるこの頃です。
- 猛暑到来となりました。
- うだるような暑さが続いております。
- 夏空が眩しく輝く頃となりました。



季節を取り入れた挨拶はきっと喜ばれますよ。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

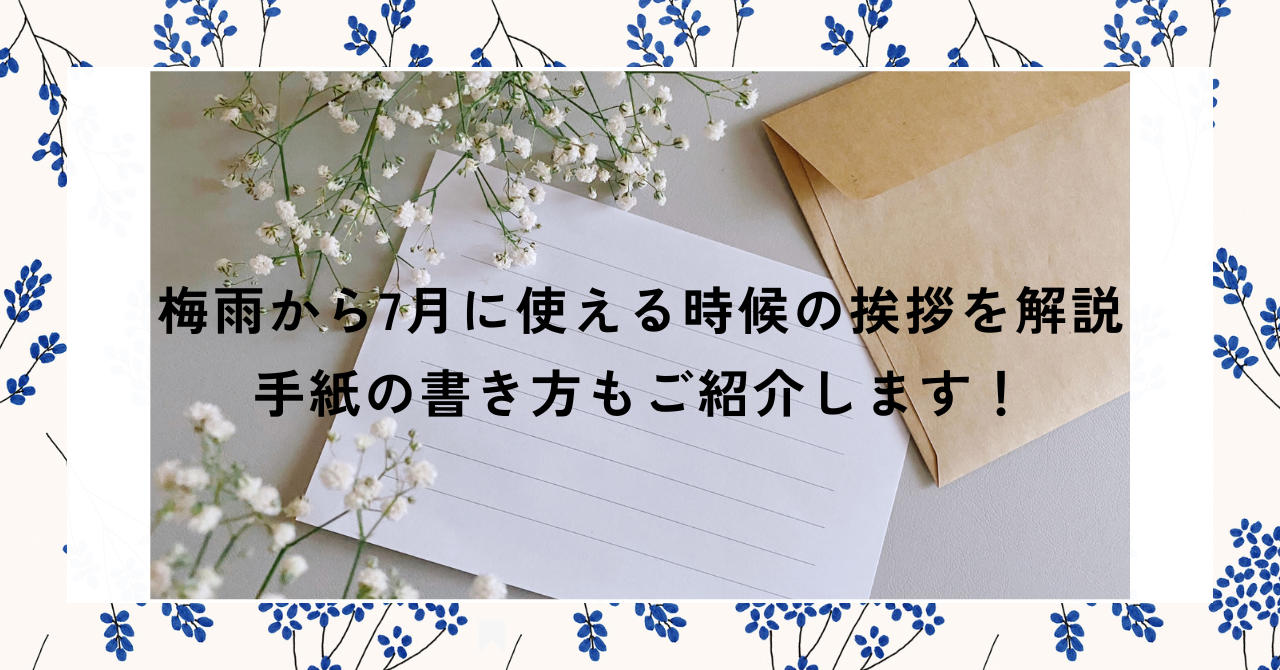
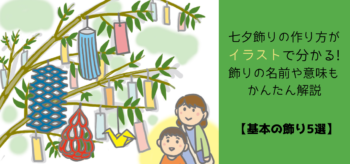


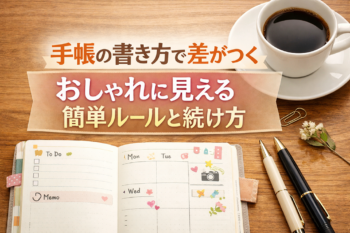
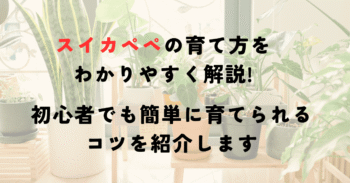
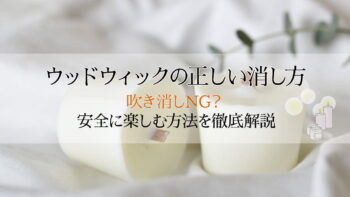
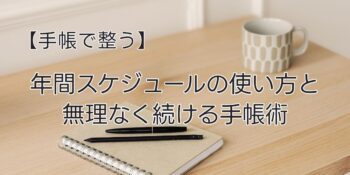
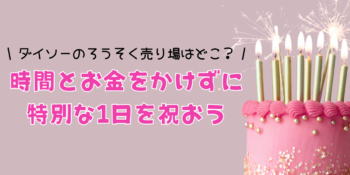
コメント