 読者さま
読者さま門松は具体的にいつから飾ればいいの?
そんな疑問を持つ方は意外と多いものです。
せっかくなら、縁起の良い日を選んで支度を整え、清々しい気持ちで新年を迎えたいところですよね。
「29日や30日は飾らないほうが良い」という話は耳にしたことはあっても、その背景や正しい時期までは意外と知られていないものです。
この記事では、以下の3つの点について順を追ってお伝えしていきます。
- 飾り始めにおすすめの日取り
- 29日・30日が敬遠される理由
- 飾る場所を選ぶときのコツ
これを読み進めるうちに、「いつ・どこに・どんなふうに飾るべきか」が自然と理解できます。
意味や背景を理解すると、門松は単なる飾りではなく家族の幸せを願うための大切な習慣だと感じられるはずです。
今年は、縁起を意識したタイミングで門松を用意して、福を迎え入れる新年を過ごしましょう。
門松はいつ飾る?


お正月飾りの中でも、とくに印象的な存在である門松。
新しい年にやって来る年神様をお迎えするためのサインとして、古くから大切にされてきました。
とはいえ、「実際にはいつ頃から飾り始めれば良いのか?」と迷う方も少なくありません。
ここでは、飾り始めにおすすめの日取りと、29日・30日が敬遠される理由についてわかりやすく説明します。
飾り始めのベストタイミングは12月26日~28日
門松の飾り始めに適している時期は、12月26日〜28日のあいだです。



この時期は「松迎え」とされ、年神様を迎えるための準備期間と考えられてきました。
クリスマスが終わった頃から家を整えるのは、清らかな状態で新年を迎えるための大切な習わしとされています。
昔から「新しい年の神様をお迎えするにあたっては、家を清める」という意味があるからです。
年神様は新年に各家庭を訪れ、家族の健康や幸せを授けると伝えられています。
そのため、年神様が迷わず家までたどり着けるように、門松は少し早めに準備しておくとよいとされています。
家族で掃除を済ませてから門松を飾ることで「一年の締めくくり」を意識でき、新しい年を迎える実感もより深まっていきます。
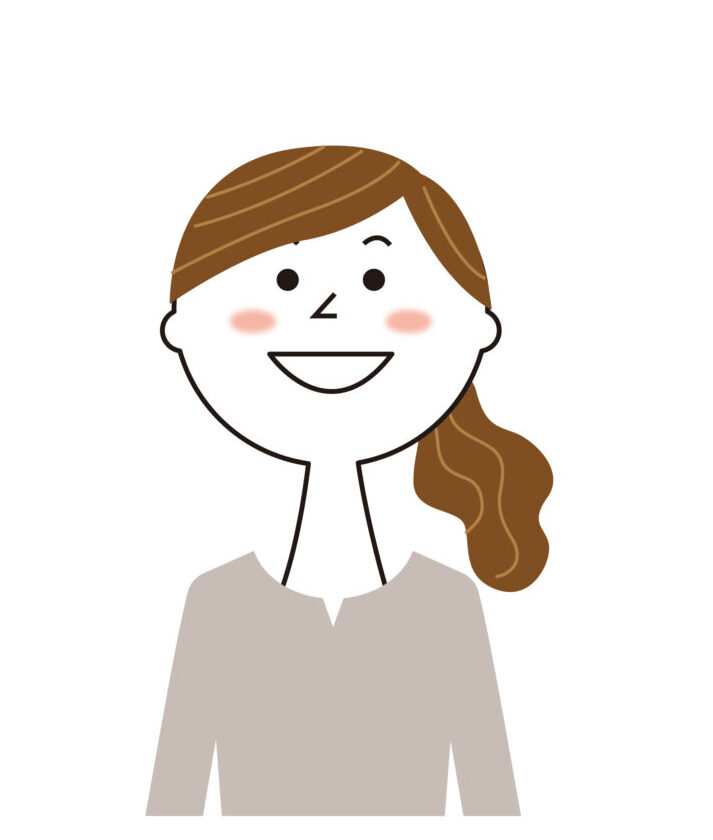
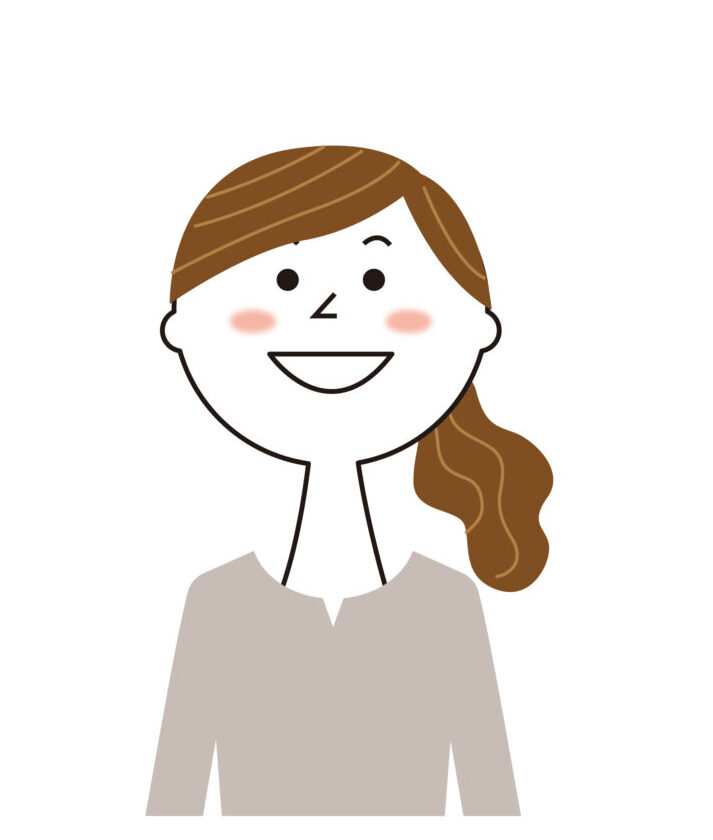
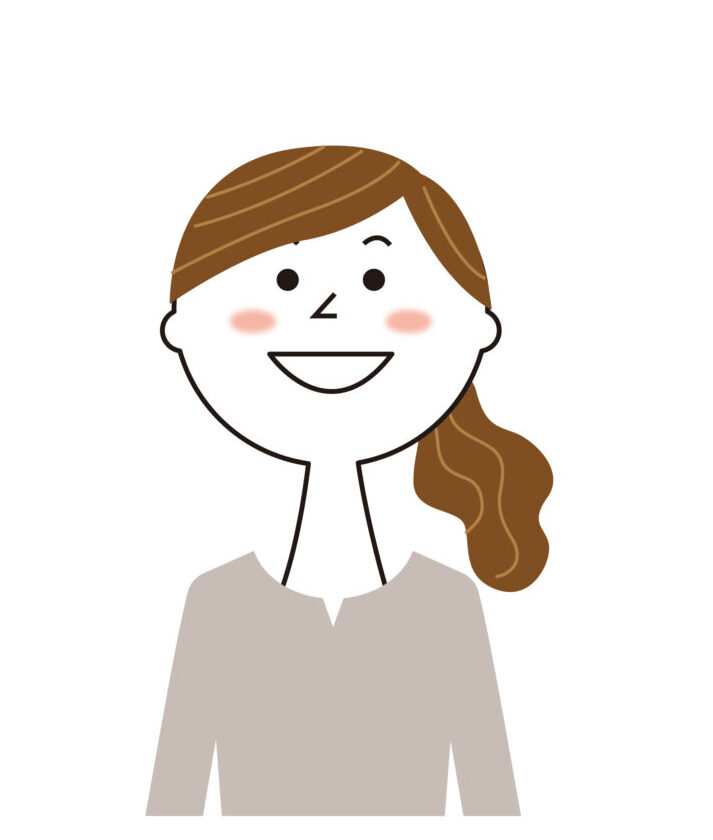
昔からの風習には、きちんとした理由があることがわかります。
意味を理解すると、お正月の準備がより楽しみになりますね。
この時期に整えておくことで、慌ただしい年末でも心に余裕をもって新年を迎えられるようになるのです。
少し余裕をもって飾り付けを整え、福と良い運気が入ってくるような、新しい一年を穏やかに迎えましょう。
- 最も適した飾り始めの時期は、12月26日から28日ごろ
- この時期は「年神様を迎える準備を整える期間」と言われてきた
29日・31日はなぜ避けるべきなのか?
門松を飾るタイミングとして、12月29日と31日は避けたほうが良いとされています。
どちらの日も、古くから縁起が良くない日といわれています。



せっかく飾るのであれば、より良い日を選んで新年を迎えたいものですね。
準備の時間には、気持ちを整える意味合いがあると考えられており、慌てて準備するのではなく落ち着いて飾ること自体に意味があります。
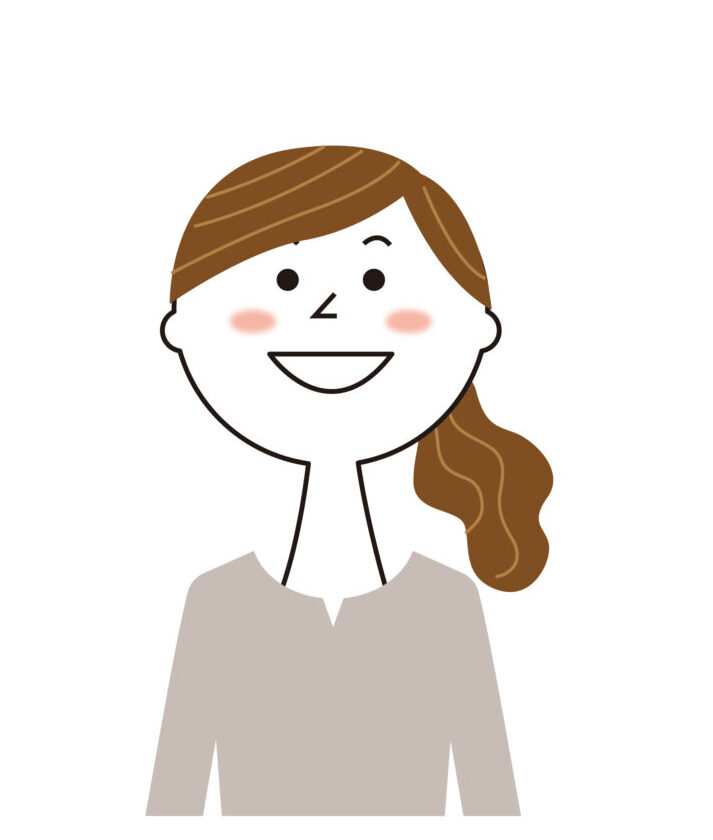
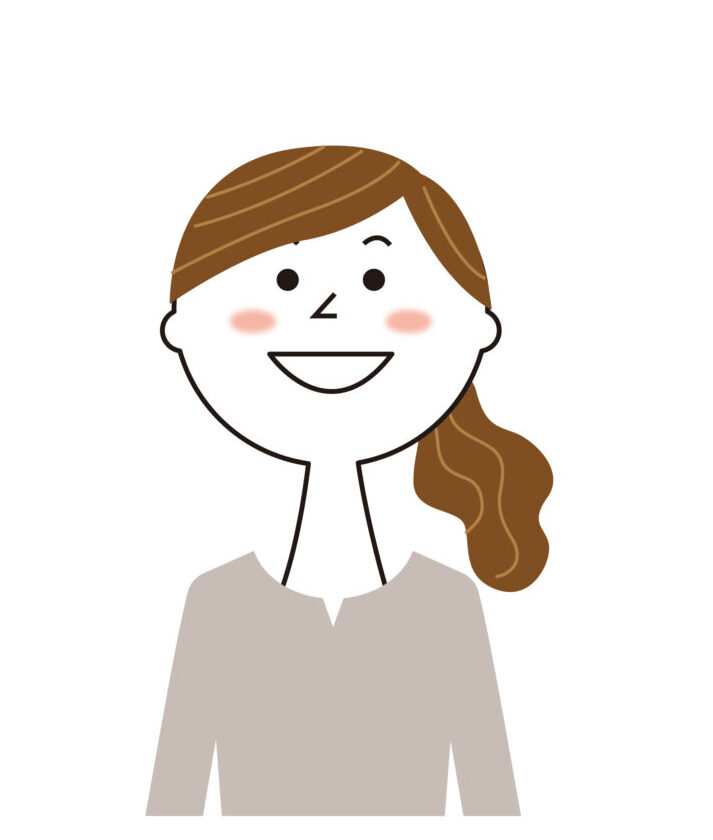
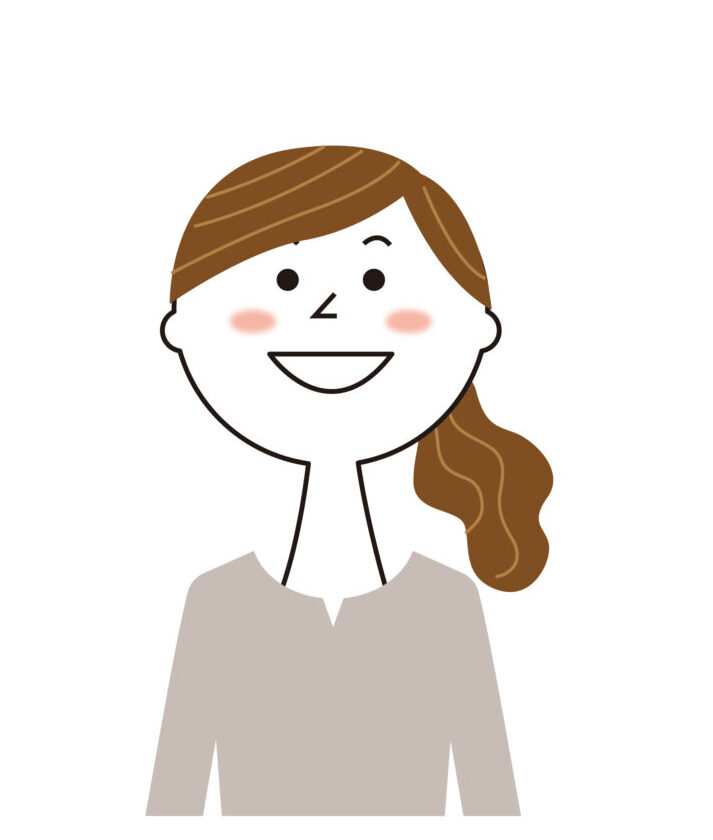
なるほど、予定が遅れてしまいそうなときでも、30日であれば問題なく飾れるのですね。安心しました!
早めに準備を整えておくことで、気持ちにもゆとりが生まれ、落ち着いた心で新しい年を迎えやすくなるでしょう。
29日と31日を避けつつ、26〜28日、もしくは30日に飾るのが安心です。
門松はいつまで飾る?片付けの目安も確認





心を込めて飾った門松を、いつ片付けるのが良いのだろう?
この点について悩んでしまう方も、珍しくありません。
実は、門松を飾る期間にも古くから伝わる考え方が残っています。
ここでは、門松を片付けるタイミングと、その際のマナーについて解説します。
一般的には「松の内」まで(地域差あり)
松の内とは、年神様が家に滞在しているとされる期間のことです。
門松を飾る期間の目安は「松の内」と呼ばれる時期までです。
松の内を過ぎると門松の役目が終わり、感謝の気持ちを込めて片付けるのが良いとされています。
この差は、昔の暦や各地域に残る風習の違いによるものです。
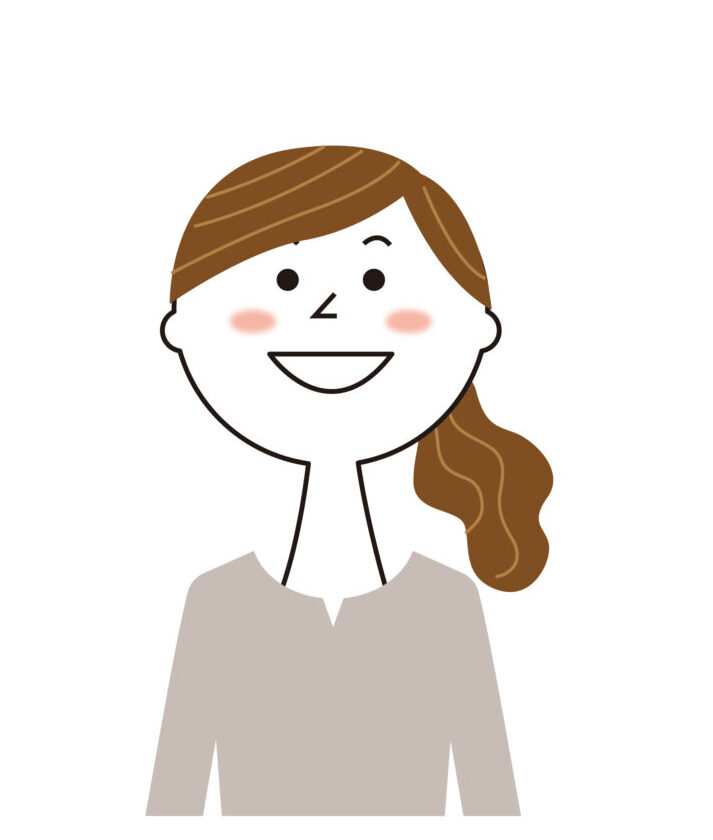
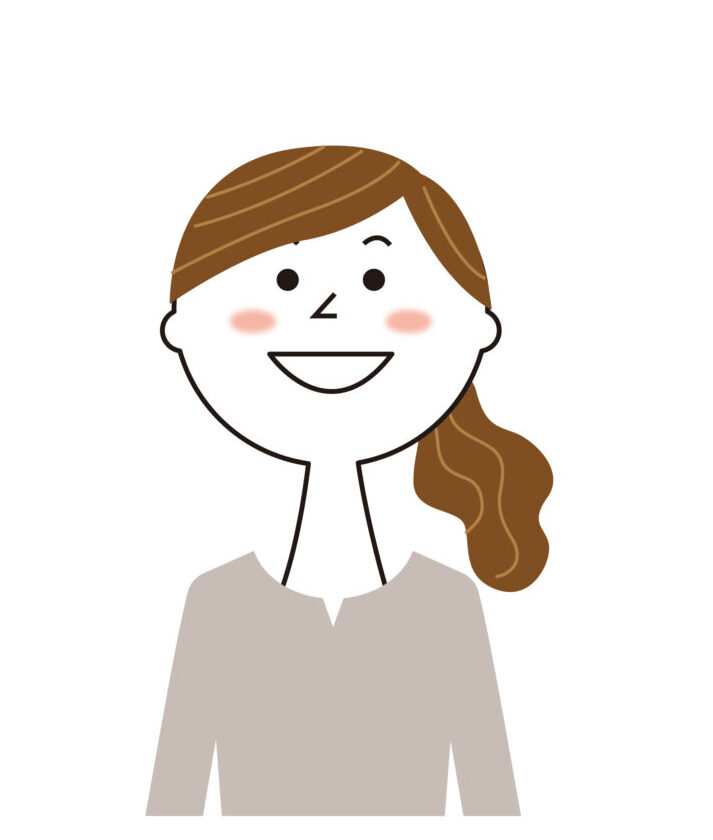
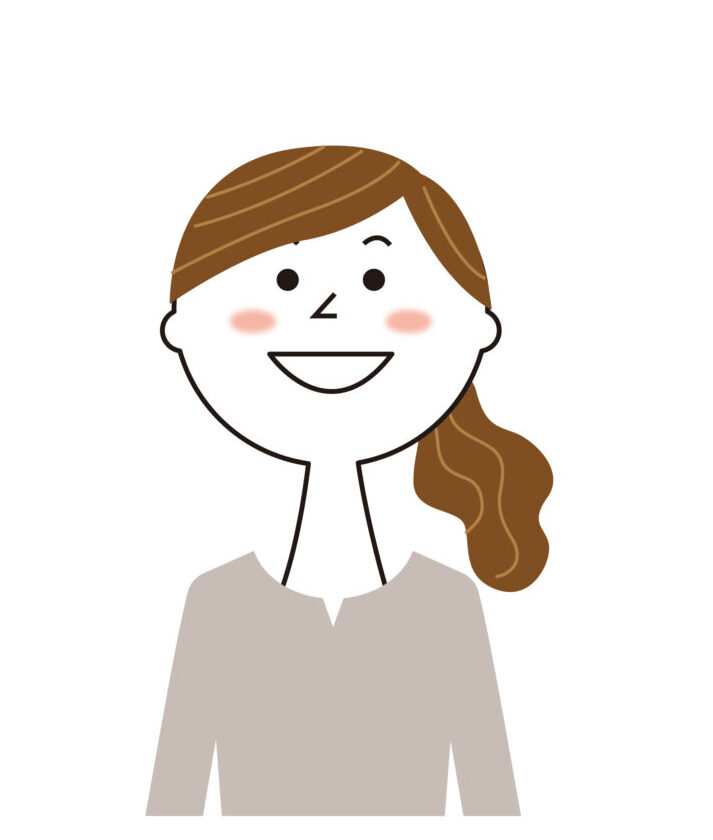
同じ日本でも、地域によって飾る期間に違いがあるのも興味深いです!



迷ったときは、近くの神社や地域の案内を確認すると安心です。
- 門松を飾る時期の目安は、「松の内」が明けるまでという考え方が一般的です。
- 関東では1月7日頃まで、関西では1月15日頃までを目安にしましょう。
門松の片付けと処分方法
門松を片付けるタイミングは、「松の内」が終わった翌日に門松をしまう、というのが一般的な目安になっています。
年神様をお見送りしたタイミングで門松を片付けることは、「今年もよろしくお願いします」という感謝の気持ちを込めて片付ける、大切な習わしとされています。
処分の方法にも意味があり、丁寧に行うことで新しい年をすっきりとした気持ちでスタートできます。
門松の片付け方と処分は以下の手順で進めると良いでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外す時期 | 松の内が終わった翌日(関東:1月8日頃/関西:1月16日頃)が目安 年神様をお見送りしたあとに片付ける習慣がある |
| 処分の方法(風習) | 「どんど焼き(左義長)」に持参して焼いてもらうのが、もっとも丁寧な方法 火にくべることで年神様を空へ送り出す、という意味が込められている |
| 自宅での処分方法 | ①門松を細かく解体し②塩で清め③半紙などの白い紙に包んでから可燃ごみとして出す |
このようにして、松の内が過ぎたら「今年もよろしくお願いします」という思いを込めて、丁寧に片付けていくことが門松の正しい片付けとされています。



その行事に込められた意味を理解し、心を込めて片付けると家の中も気持ちもすっきり整い、清々しく新年を迎えられますね。
玄関に門松を飾る理由と意味


玄関に門松を飾る意味とは?
飾るタイミングや片付け方の目安を押さえたところで、次に気になるのは「なぜ玄関に飾るのか」という理由ではないでしょうか。
門松は、年神様が道に迷うことなく家を訪ねてこられるよう導く、”道しるべ”のような役割を担ってきました。
ここでは、門松に込められている意味や、玄関に飾る理由についてわかりやすくお伝えしていきます。
門松は「年神様」を迎えるための目印
門松は、年神様をお迎えするために据えられる、いわば”目印”のような存在です。
古くから日本では、新しい年の幸福をもたらす「年神様」が各家庭に訪れると信じられてきました。
そのため、松や竹といった生命力を象徴する植物を玄関先に立てて「この家では、神様を迎える準備が整っています」という合図として飾られているのです。
門松によく使われる主な素材と、その意味合いは次の通りです。
| 素材 | 意味・由来 |
|---|---|
| 松 | 一年中青々としていることから、長寿や繁栄を象徴するとされる |
| 竹 | まっすぐに伸び、折れにくい性質から、成長やしなやかな強さを表す |
| 梅 | 寒さの中でいち早く花を咲かせることから、新たな門出や前向きな兆しを表す縁起物とされている |
お正月には、神社やお寺の参道入口などに門松がずらりと並んでいる様子を目にすることがありますよね。
こうした門松にも、神様をお迎えするための道しるべとしての役割が込められています。
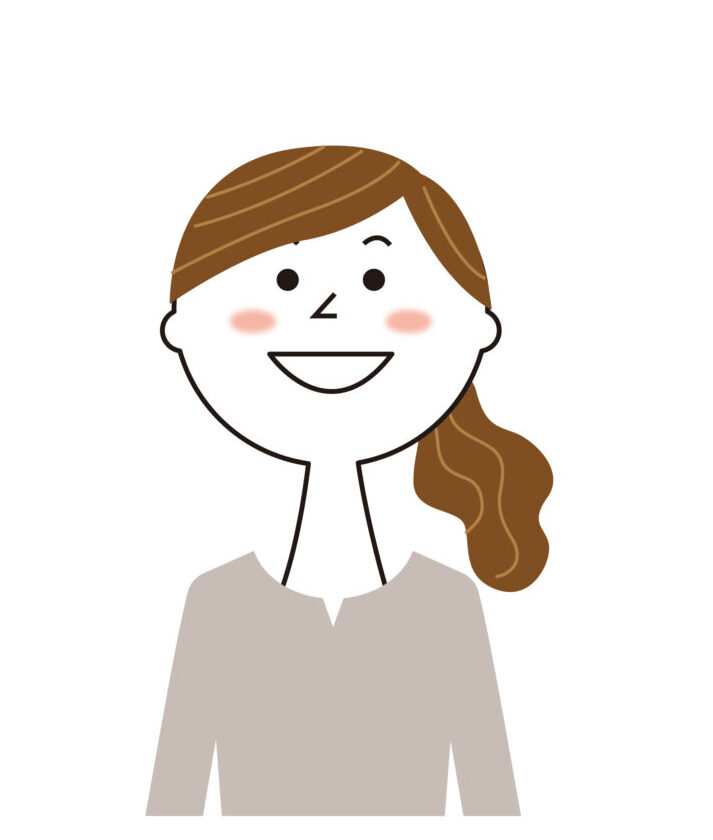
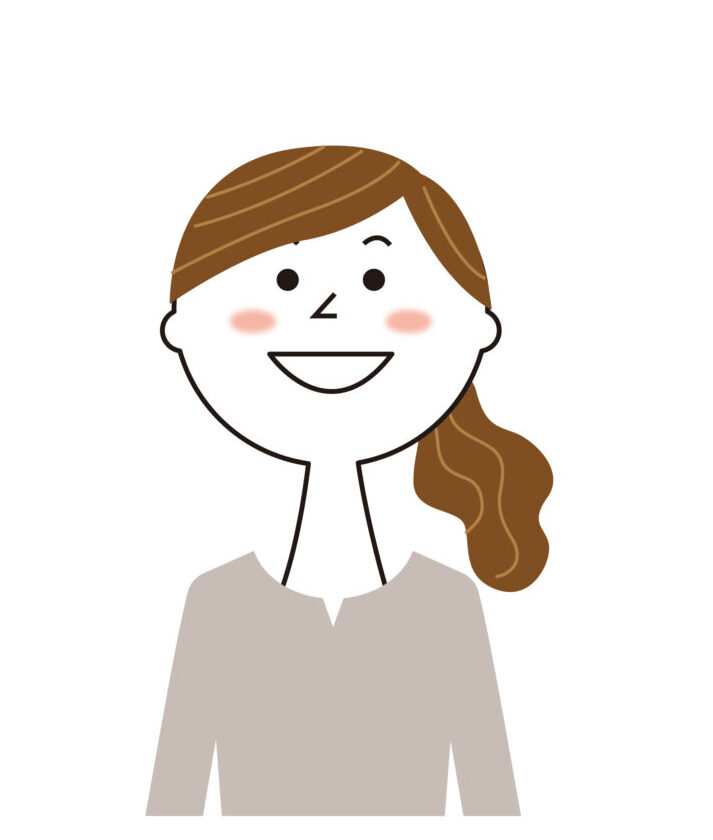
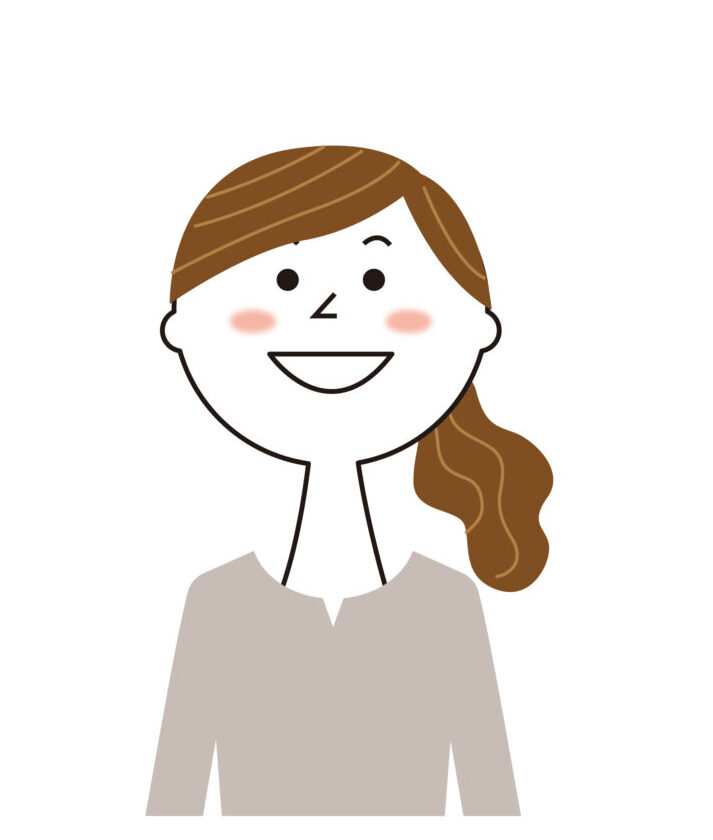
門松は単なる正月飾りではなく、年神様を迎えるための大切な合図ともいえる存在ですね。
意味を知ったうえで準備をすると、お正月の支度そのものがより深く味わいのある時間になっていくでしょう。
玄関は神様を迎える場所
玄関は、年神様を迎える大切な場所とされています。
さらに玄関は、年神様が一番はじめに訪れる場所だと考えられています。
年末には、玄関まわりを掃除して清めておき、明るく整えることが大切とされています。



きちんと片付けた玄関先に門松を飾ることは、「気持ちよくお迎えします」という思いを形にすることにもつながります。
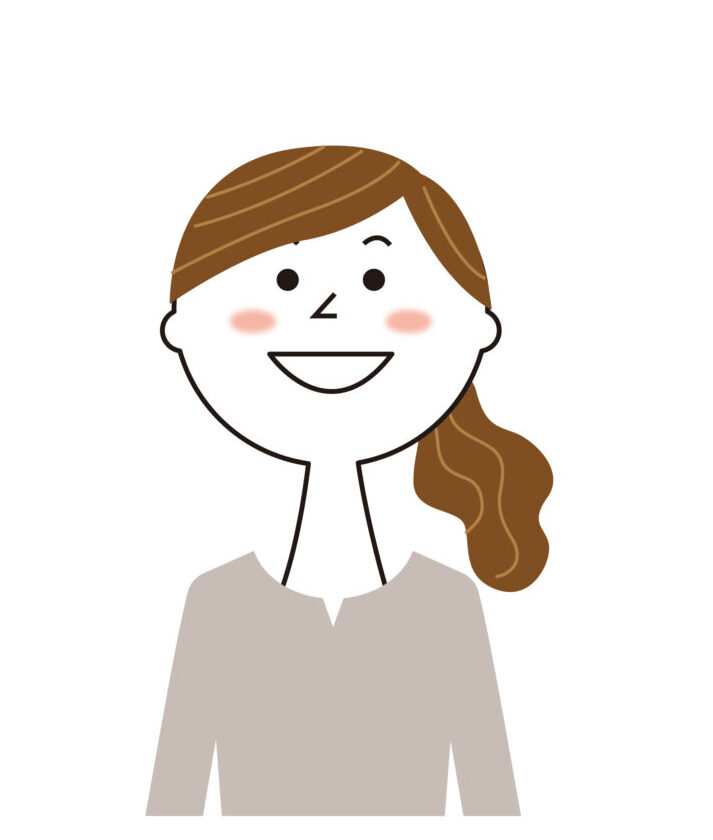
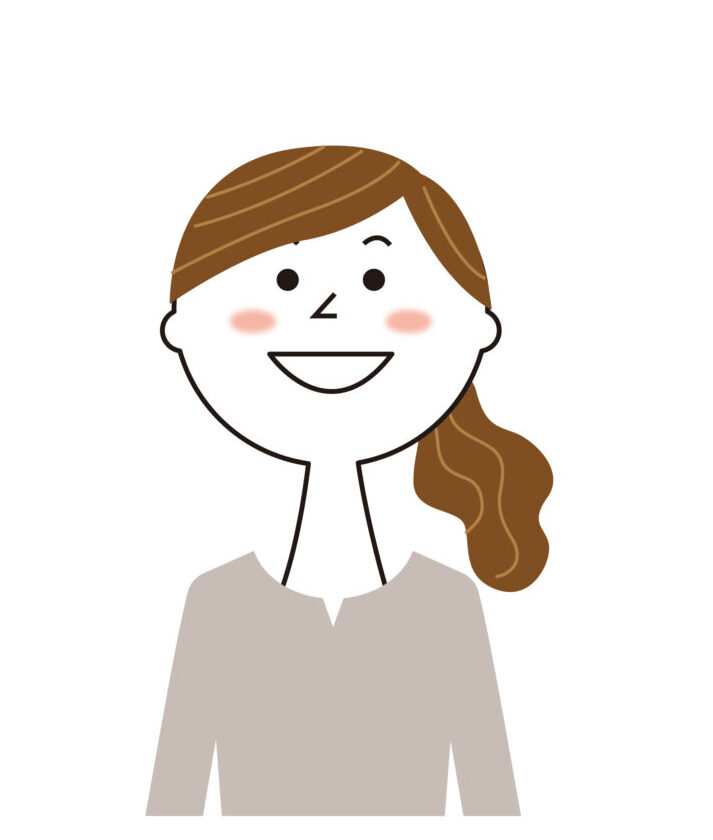
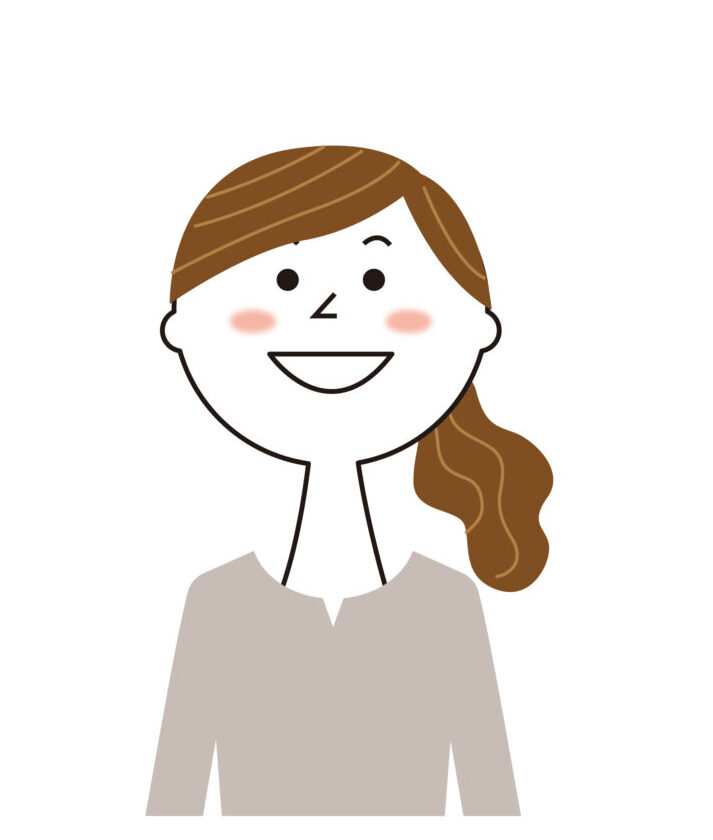
神様を迎えると聞くと少し難しく聞こえますが「感謝の気持ちで玄関を整えてみよう」と考えると、ぐっと身近に感じられますね。
玄関を整えておくことは、年神様を迎える準備にもつながり、家の中に清々しい空気が流れ気持ちよく新しい年を迎えられるでしょう。
門松の飾り方と場所の選び方のポイント


門松の飾り方や置き場所を考えるうえでのポイントが見えてくると「では実際にはどこに、どんな置き方をすればいいの?」という疑問も出てきます。
せっかくなら、年神様にも気持ちよく訪れてもらえるような飾り方にしたいですよね。
ここからは、住まいのタイプに合わせた基本の配置例や、飾るときのポイントをご紹介します。
飾る場所の基本ルール
門松を置く場所の基本は、「家の入口まわり」です。
年神様が家に入りやすいように、入口から見て左右対称になるように並べるのが良いとされています。



門松には、年神様が迷わずその家へと向かえるよう導く役割が託されているとされています。
具体的な配置の例として、住まいのタイプ別に3パターンを下表に整理しました。
| 住まいのタイプ | 飾る位置 |
|---|---|
| 一戸建て | 門の両側、玄関ポーチの左右 |
| マンション・集合住宅 | 玄関ドアの横、室内の入口近く |
| 店舗・事務所 | 出入口の外側、受付まわり |
いずれの場合も、人の出入りの邪魔にならないことと、清潔に整えた場所に置くことを意識すると、見た目にも気持ちの面でも心地よくなります。
飾る位置のイメージは、次の図のようになります。
(外から見たときの配置)
─────────────────
【雄松】 入口 【雌松】
(左) (右)
外から見て左側に雄松(おまつ)、右側に雌松(めまつ)を置く並び方がよく用いられます。
この配置は、「家庭の調和」や「円満な関係」を象徴するといわれています。
左右のバランスを意識して並べた門松は、見た目が美しいだけでなく「新年を迎える準備が整っている」という気配りも伝わります。
向きやバランスに決まりはある?
「向きや配置にも細かい決まりがあるのかな?」と気になる方もいるかもしれません。
どの向きに置くかについて、門松には細かな決まりごとはありません。
大切なのは、全体を見たときに「きちんと整っていて、気持ちよく神様をお迎えできそうだな」と感じられることです。
門松を気持ちよく飾るために、意識しておきたいポイントは、次の5つです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 高さをそろえる | 左右の高さや角度をそろえて、全体のバランスを整える |
| 左右を対称に並べる | 入口側から見て均等になるように並べ、美しさを意識する |
| 清潔に整える | 飾る前に周囲を掃除し、すっきりした状態で設置する |
| 無理のないサイズで飾る | 住まいの広さや環境に合った大きさを選び、安定して置けることを意識する |
| 風が強い地域では工夫する | 鉢に重りを入れる、ひもで固定するなど倒れないように対策する |



住宅の状況によっては、片方だけ飾る形でもかまいません。
手作りの小さな門松や卓上サイズのものでも、心を込めて丁寧に整えることが何より大切です。
丁寧に飾られた門松は、訪れた人の心をふっと和ませ家の中に明るく清らかな空気をもたらしてくれるでしょう。
縁起の良い日に門松を飾って新年を迎えよう
ここまで、門松を飾るおすすめの時期や、控えたほうが良い日、片付け方のポイント、門松に託された願いや、飾る位置をどう考えるかといった点についても紹介してきました。
最後にもう一度、この記事の大切なポイントを整理しておきます。
- 飾りに適した日:12月26〜28日(※29日・31日は縁起面から避けるのが無難)
- 飾っておく期間の目安:松の内のあいだ
(関東ならおおむね1月7日頃まで、関西では1月15日頃まで)
➡ その翌日を目安に片付けるのが一般的 - 処分方法:地域の「どんど焼き」に持って行き焼いてもらうか、塩で清めてから手放す
- 門松の意味
・年神様を迎える“目印”として飾り、家族の無病息災や幸せを祈る象徴とされる
・松・竹・梅には「長寿」「成長」「新たな希望」を表す意味合いがある - 飾る場所:玄関や門の両脇など、出入りしやすく清潔な位置に置く
- 飾り方のコツ
そろえる/左右対称に並べる/清潔に整える/家に合うサイズを選ぶ/風への対策もしておく
こうした点を意識しながら、ふさわしい時期に門松を飾ることは、家を整え、心を整えることでもあります。



慌ただしい年末だからこそ、家族で玄関をきれいに整えながら、「今年もありがとう」「新しい一年もよろしくね」と気持ちを込めて準備ができたら素敵です。
今年はぜひ、良い日取りを選んで門松を整え、福を招き入れる気持ちのよい新年を迎えてみてください。
玄関まわりを整え、門松を飾った家には、自然とやわらかな空気が流れ込みます。
新しい年が、あなたとご家族にとって穏やかで実りある時間となりますように。
おせち料理に込められた意味をご存じでしょうか?
お正月の行事をさらに楽しみたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
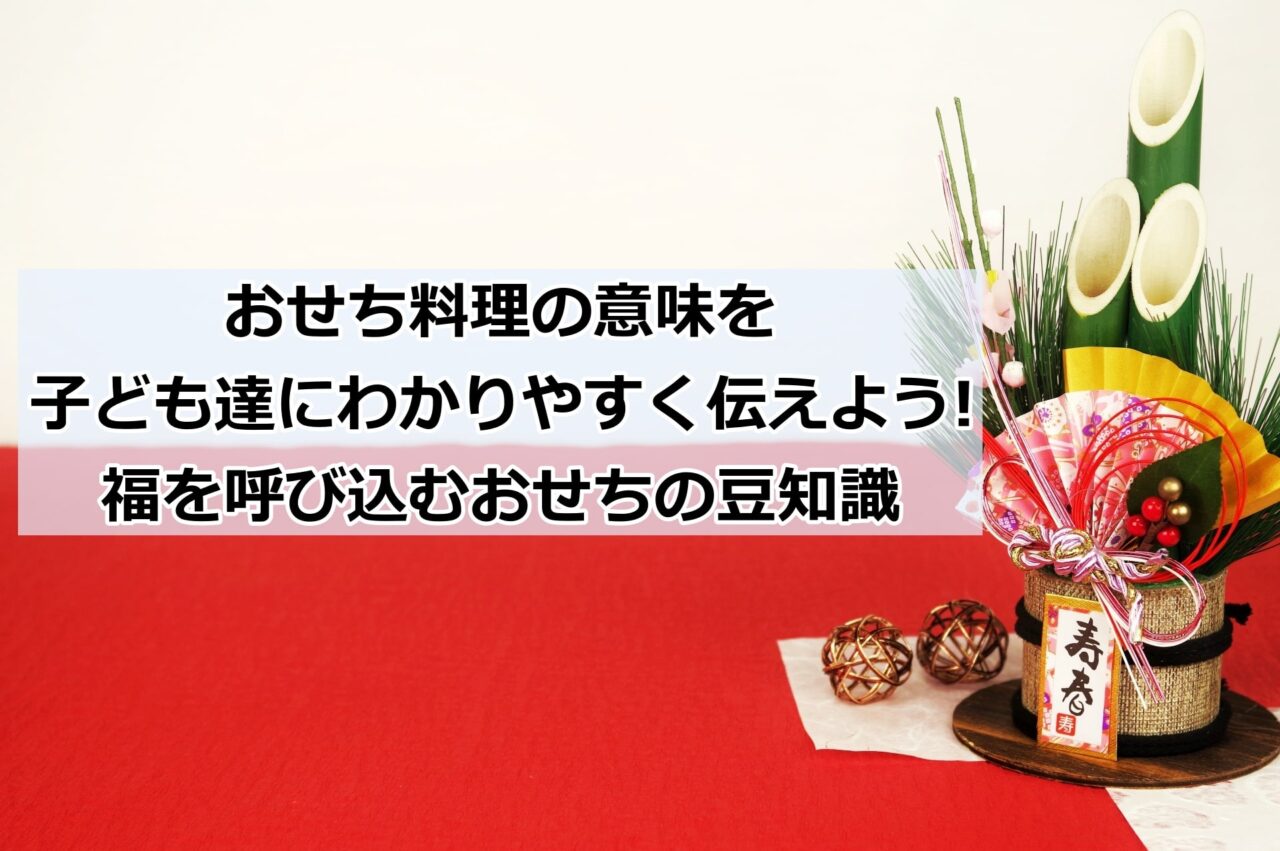
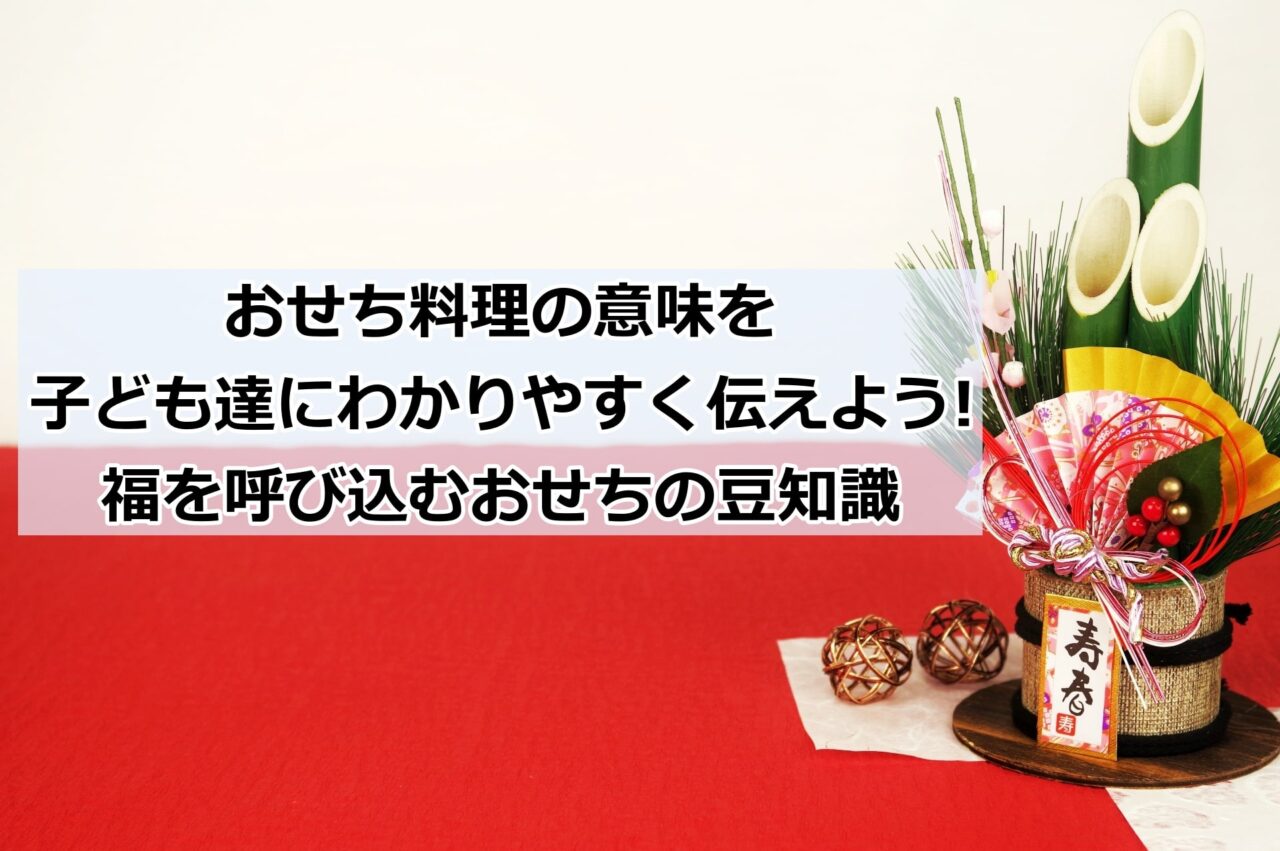
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


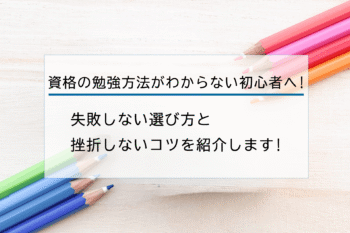

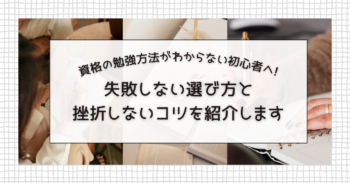
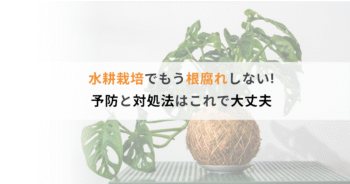

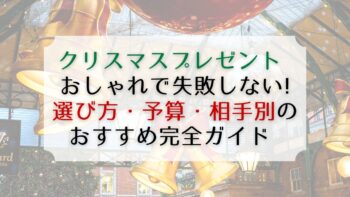
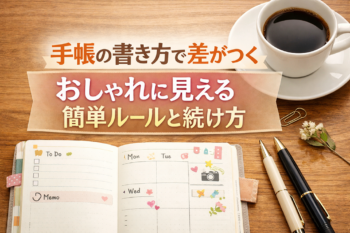

コメント