 読者さま
読者さま正月飾りをするのに縁起が悪い日があるって聞いたんだけど、いつなんだろう……。
新年を気持ちよく迎えるための正月飾りは、いつ飾ると縁起が良いのか気になる方も多いのではないでしょうか。
新しい一年を気持ちよく迎えるための正月飾りですが、実はこの日に飾ると「翌年の幸福が増す」とされる日があります。
その一方で、語呂合わせが良くないことから、「避けたほうが良い日」もあるのです。
せっかくなら良い運気を迎える準備を整えて、新年を清々しい気持ちでスタートしたいですよね。
この記事では、正月飾りを飾るのに適した日や、気を付けたいポイントをわかりやすくお伝えします。
- 正月とはどんな行事か
- 門松、しめ縄、鏡餅のそれぞれの役割
- 正月飾りを飾ると縁起の良い日・避けたい日
- 正月飾りの片付け方
- 手軽に正月飾りを楽しむ方法
正月や正月飾りの意味を理解し、晴れやかに新年を迎えましょう。
正月飾りを飾る意味と基本の種類


本来、正月とはどんな行事なのでしょう?
新しい年をお祝いする日?家族で集まっておせちを食べる日?
どれも正解ですが、それだけではありません。
正月は一年の健康や幸せを願って神様を家にお迎えする大事な行事なのです。
神様に失礼のないよう、お迎えの準備や、正月本来の意味を一緒に見ていきましょう。
正月飾りの由来と意味
一年の始まりには、年神様が家々を訪れて幸せを配ってくださると言われています。
年神様とは、日本神話の『古事記』に登場する神様で農耕を司る神様です。
昔の日本人の生活にとって重要な農耕の神様。
大切にすることで五穀豊穣・家内安全・無病息災・商売繁盛などさまざまなご利益があります。
正月とはこの年神様を自宅に招いてもてなし、家族の一年の健康や繁栄を願う大切な行事なのです。
門松やしめ縄などの正月飾りは、年神様が迷わず家に来られるよう示す目印であり、神様が訪れるのにふさわしい清浄な空間であることを示します。
主な飾りの種類(門松・しめ縄・鏡餅ち)
正月飾りの種類や役割について確認していきましょう。
門松
門松は神様が迷わず家にやってくるための目印です。
家の玄関や門の前に置かれ、神様の来訪を願います。
門松は松や竹、梅など縁起のいいもので華やかに飾られます。
- 松 一年中葉を落とさないことから強い生命力を表す
- 竹 成長が早く、まっすぐ伸びることから明るい未来・希望を象徴
- 梅 厳しい冬に花を咲かせる姿は生命力・忍耐・高潔さを感じさせる


しめ飾り・しめ縄
しめ飾りは神様が滞在するのにふさわしい場所であることを示す飾りです。
不浄なものや災いから家を守る結界であり、清らかな場所であることを伝えます。
しめ飾りにも種類があるので解説していきますね。
ごぼうじめ
左右の太さに違いがあります。右側が太く、左が細くなるように飾るのが一般的ですが地域によって異なります。
神棚に飾り、神域と俗世を分けます。
玉飾り
しめ縄と一緒に扇子やエビなどの縁起ものが飾られている正月飾りです。
左右を考える必要がなく、玄関に飾ると華やかになります。
輪飾り
もともと簡易的なしめ縄として室内を清めるために飾られていましたが、最近では玄関に飾る家庭も増えてきました。


鏡餅
年神様の依り代です。
昔から鏡には神様が宿ると考えられており、神様が宿る餅として鏡餅といわれるようになりました。
神棚や床の間に飾るのが正式ですが、最近の住環境をふまえ、家族が集まる場所・リビングやダイニングに飾るようになりました。
正月が過ぎたあとは「鏡開き」を行い、神様が宿ったお餅をいただくことで、一年の健康を祈ります。
鏡開きの際は、神様を傷つけないよう刃物は使わずに、手や小槌で割るようにします。


正月の飾りはいつ飾るのが良い?


年神様を迎える準備である正月の飾りつけは、飾りつけを行う日も重要です。
「正月事始め」といわれる12月13日を過ぎれば飾りつけを始めても大丈夫ですが、最近ではクリスマスを終えてから飾りつけを行うことが一般的です。
縁起のいい日や、避けた方がいい日もあるので確認していきましょう。
一般的に縁起が良いとされる日(28日)
正月飾りに最適な日は12月28日です。
漢字の「八」は末広がりで、幸福が広がっていくとされていて非常に縁起がいいです。
正月飾りに最もいい日は28日。
難しければ26日、27日。
遅くとも30日までには飾りつけを行いましょう。
避けた方がいい日(29日、31日)
縁起が良い日がある一方、語呂が悪く正月飾りに向かない日もあります。
12月29日
29日は「二重苦」とされ、翌年の繁栄を願う飾りつけを行う日には向きません。
12月31日
大晦日の一夜だけで正月飾りを用意することを「一夜飾り」と呼びます。
正月を迎える前日に慌ただしく飾りつけを行うことは神様に対して失礼にあたります。
また、葬式の飾りが一夜で行われることから不吉であるとされるので、この日も避けたいですね。
正月飾りに最もおすすめの日→28日
正月飾りを避けたい日→29日、31日
正月飾りを外す時期と片付け方


正月飾りは「松の内」と呼ばれる期間のあいだ飾られます。
松の内とは新年を表す期間のことで、地域によって差があります。
この章では松の内の地域ごとの期間の違いと、正月飾りを外す日。
外した飾りの片付け方について見ていきましょう。
松の内の終わりと外す日
松の内は地域によって期間が異なります。
関東・東北・北海道・中国・九州地方⇒1月1日~1月7日まで
関西・四国⇒1月1日~1月15日
松の内が明けてから、20日までのあいだに正月飾りをしまいましょう。
鏡開きは関東では1月11日。
関西では1月15日から20日までのあいだに行い、お雑煮やお汁粉にしていただきます。
外した飾りの片付け方
外した飾りの片付け方は大きく分けて3つあります。
どんど焼き
最も丁寧な片付け方です。
小正月の1月15日に神社やお寺で、お札やお守りと一緒にお焚き上げしてもらいます。
この火の煙に乗って年神様は帰っていくとも言われていて、神様を見送る儀式でもあります。
煙を浴びると一年健康で過ごせると伝えらえています。
神社の「古札納め所」に出す
どんど焼きを行っていなくても常設で古札を収める箱が設置されている神社も多いです。
1月15日に都合がつかない方はこちらに収めるのもおすすめです。
自宅で清める
マナーを守れば個人で片付けることも可能です。
手順
- 感謝の気持ちをこめて汚れを軽く拭く
- 塩でお清めする
- 白い紙や半紙に包む
- 他のごみとは分けて袋に入れる
※他のごみと一緒にするのは失礼になるので避けましょう
地域の分別ルールに従って出しましょう。
忙しくてもできる正月飾りの工夫


毎日忙しくてなかなか正月の準備にまで手が回らない方のために、手軽に用意できる正月飾りをご紹介します。
手軽にできる飾り方のコツ
ぜひチェックしていただきたいのは100円ショップ。
ダイソーやセリアなどでは、毎年11月頃からお正月飾りが販売され始めます。
アパートやマンションでも飾りやすい小さいサイズの門松や、リースタイプの華やかなしめ飾りなど種類も豊富です。
デザインがかわいいのはもちろん、リースタイプは左右を気にせず玄関のドアに飾るだけなので手軽です。
コンパクトなサイズが多いのも、現代の住環境に適していていいですね。
飾る場所と方角の基本
正月飾りを飾る方角に厳密な決まりはありませんが、陽の光が入りやすく明るい南や東の方角がいいでしょう。
飾る場所については以下です。
家の前や門前⇒門松
玄関⇒しめ飾り(玉飾り・輪飾り)
神棚⇒しめ縄や鏡餅
リビング・ダイニング⇒鏡餅
正月飾りをする前にしっかり家を清めて、敬意を持って飾りつけましょう。
まとめ|縁起よく年神様を迎えるために
この記事では正月飾りの役割や飾る時期について解説しました。
ひとつひとつの意味を知ることでよりいっそう気持ちがこもり、丁寧に準備に取り組めるのではないでしょうか。
正月は年神様をお迎えするための大事な行事です。
年末の大掃除で家を清め、正月飾りを飾ることで神様をお迎えするのにふさわしい空間にします。
正月飾りの役割は神様を家にお招きするための準備です。
- 門松⇒神様をお迎えするための目印
- しめ縄・しめ飾り⇒神聖な場所を守るための結界
- 鏡餅⇒神様の依り代
正月飾りを飾るのに縁起の良い日・避けたい日も確認しておきましょう。
縁起の良い日⇒12月28日
避けたい日⇒12月29日、12月31日
クリスマスを終えた26日から30日のあいだに飾りつけをしましょう。
飾りつけを外す日は以下です。
関東・東北・北海道・中国・九州地方⇒1月7日~1月20日
鏡開きは11日
関西・四国⇒1月15日~1月20日
鏡開きは15日~20日
正月飾りの片付け方も確認しておきましょう。
- どんど焼き⇒神社でお焚き上げしてもらう
- 神社の古札収め所に出す
- 各家庭にて塩で清めて処分する
新しい一年を迎えられることに感謝し、晴れやかな気持ちで年明けを迎えましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。


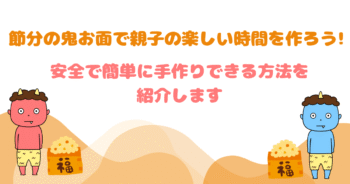
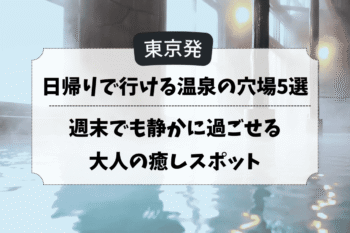
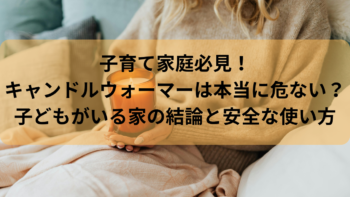


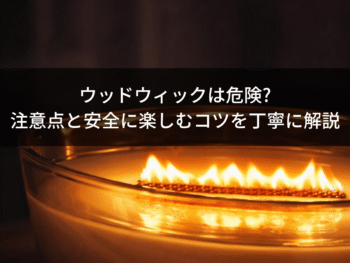

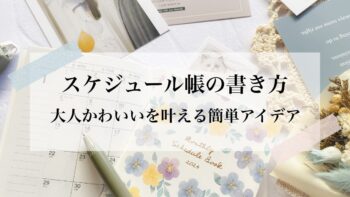
コメント